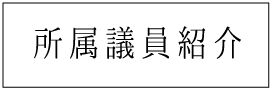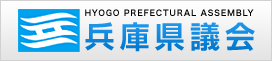概要 / 代表・一般質問 / 議案に対する態度と考え方 / 意見書案 / 提案説明 / 討論
質 問 日:令和7年2月25日(火)
質 問 者:上野 英一(ひょうご県民連合)
質問形式:一問一答

はじめに
議員による不信任決議を受けて、知事は出直し選挙に出馬、昨年の11月17日には見事再選を果たされました。このことは大変大きなことで、私も重く受け止めています。
しかし、再選を果たされたといっても、今なお元西播磨県民局長の公益通報における様々な問題(告発文書7項目の真偽、公益通報制度・同通報者保護法違反、個人情報漏洩問題)、新たに公職選挙法違反問題などの疑惑が渦巻いています。
「ワンチームで県政を支えたい。大切なのはコミュニケーション。中堅や若手職員との対話の場を作りたい。風通しの良い職場づくりを進めたい」。と知事はおっしゃっていますが、そのためには何をしなければならないかお考えがありますか。私は、申し上げたこれらの疑惑の解消なしではありえないと考えています。
以下それぞれの課題について質問いたしますので、県民誰もが納得できる具体的に心のこもった答弁をお願いいたします。
1 個人情報の漏洩について
(1)個人情報保護の重要性について
行政が県民から信頼を得るために、知事は何が必要とお考えですか。私は、行政に最大限求められることは、「県民の人権の尊重」だと思います。そして、その第1に、「個人情報の保護」すなわち職員の秘密の保持義務が挙げられると考えています。知事は如何お考えですか。
(2)個人情報漏洩事実の認識について
今回不幸にも、元西播磨県民局長が内部告発をいたしました。それは斎藤県政の中に多くの問題が発生しているという告発であり、そんな県政を少しでも正常化したいとの思いからだと私は思っています。
しかし、知事はその公益通報を正常に取り扱わず、通報者探し、公用パソコンの押収の結果、私的情報を不正に取得したと私は考えています。
そして、その大切な元西播磨県民局長の個人情報が漏洩しました。それも担当部署の責任者である元総務部長からの可能性が大と言われています。 私は、その個人情報を県当局が取得した調査も、違法な調査だったと考えています。
週刊文春が7月17日に初めてその漏洩問題を報道しました。その記事からすると、元総務部長の行動は4月上・中旬です。報道が7月17日、百条委員会での二人の県議への聞き取り調査が12月11日に行われ、議事録を閲覧に供したのが12月25日です。百条委員会聞き取り調査の中では、「元総務部長から、元県民局長の公用パソコンにあった個人情報を見せられた。」と二人の県議から証言があり、見せられたとされる時期は、週刊文春で報じられた元総務部長の行動の時期と一致していました。知事はそのことを承知されていますか。それに対し、そのことをどのように捉え、どのように対応されましたでしょうか。
(3)守秘義務違反者に対する刑事告訴について
一般職の公務員の場合、「地方公務員法では第34条1項で守秘義務が課せられており、違反者は、1年以下の懲役、3万円以下の罰金に処せられる。」となっています。漏洩の事実を認識した場合、知事がまずやらなければならないことは、できるだけ速やかに刑事告訴することではないですか。それが知事の責務と考えますが如何ですか。
(4)速やかに刑事告訴しない理由について
なぜ速やかに、刑事告訴しないのですか。何かまずいことがあるのですか。
もしかすると、元総務部長単独の行動でなく知事の承認の下で行われていたとか、元副知事などを含めて牛タンクラブと称される側近での共通認識であったとか、すなわち、個人情報を暴露することで元西播磨県民局長の人格を貶め、告発文書はそんな男の行動であると、中身は嘘っぱちであると、印象操作をするためではないかと、勘ぐってしまうのですが、その辺りについての知事ご自身の認識は如何ですか。
(5)知事が設置をした2つの第三者調査委員会について
行政の基本は条例主義・予算主義であります。その条例は、法律に基づいて、条例制定されます。また、その条例に基づいて施策は予算化されます。
地方自治体における附属機関は、調停、審査、諮問又は調査のために、地方自治法第138条の4第3項に基づいて設置されます。
地方自治法第138条の4第3項抜粋では、普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。とされています。
知事は人事課と法務文書課所管で2つの第三者調査委員会なるものを設置されていますが、その設置根拠と予算根拠についてお伺いします。
2 公益通報制度・同通報者保護法違反について
(1)告発文書入手時における公益通報との認識について
百条委員会では、知事および片山元副知事は、公益通報制度・同通報者保護法に違反していないとおっしゃっています。お二人の答弁を県の見解であるとして、以下質問いたします。
3月21日に秘書課を通じて、知事、片山副知事、幹部職員が一堂に会し、知事より告発文書を示され徹底的に調査せよと言われ、告発者探索、取り調べが行われました。3月21日の段階では、公益通報との認識は全く議論されていない。ここがそもそもの重大な誤りの出発点であり、不幸な県政1年の始まりであったと考えます。
3月21日以降数回の対策会議が行われ、そして3月27日には決定的な元西播磨県民局長へのパワハラとも思える会見が行われました。知事にはこのとき、公益通報の認識はありましたか。
(2)調査の正当性、及び不正な目的があれば、公益通報に当たらないとの主張について
県の告発者探索について、片山元副知事は、「この騒動の、基本的には不正な目的があるということ。それから一つは、民間企業さんの名前が出ていましたので、(中略)、それに伴って県庁の信頼が落ちる可能性があると考えた。」と調査の正当性を述べています。
また、片山元副知事は、「告発者を探しだそうとしたことは全くご指摘のとおりやと思います。ただ、その後どうするかということは念頭にはありませんで、とにかく誰がどういう目的でやっているかということを確認しようという思いがあったのは事実です。」と証言しています。
さらに、片山元副知事は、「3月27日の時点では、先ほども申し上げたように、この文書の作成意図が不正な目的であるということを、不正な目的に基づくものと思っておりました」として、公益通報という認識はなかったと証言されています。
この片山元副知事の認識は、知事ご自身も同じ考えですか。
(3)告発文書が公益通報に当たらないと判断する理由について
知事は百条委員会で、「公益通報に当たらないというか、外部通報としての保護の対象にならないということを後ほど8月7日にですかね、記者会見で言った記憶があります」と述べられています。また、「私自身が文書を読んだときに、具体的な供述や、それから信用性の高い証拠とか、そういったものが文書自体に書かれていないことが1点。それから、もう1点が、うわさ話を集めて作成したというふうに、元県民局長が供述していたということを報告受けましたので、結果的に、内部通報で保護される要件を満たさないと判断したと思います。」と述べられています。
改めて伺いますが、元西播磨県民局長の告発文書を知事が保護の対象とならないと判断された理由は何ですか。
(4)公益通報に当たらないとする3点の主張について
片山元副知事は、これまでの「不正な目的」に加えて、「法第11条第2項の(体制整備等)には、明文で、1号通報ですね、つまり内部通報だけに該当するという明文規定がございます。」と述べられています。つまり、片山元副知事の主張は、「真実相当性」がない、「不正な目的」がある、「公益通報者保護の体制整備等」については内部通報だけに該当し、外部通報には該当しないと、3点について主張されています。知事ご自身のご認識は如何ですか。片山元副知事と同じですか。
(5)告発文書に対する知事の対応について
しかし、公益通報制度の専門家であり当委員会で参考人としてお呼びした奥山俊宏教授、山口利昭弁護士、結城大輔弁護士の3人の解説や、そもそも3号(外部)通報については、内閣府指針、消費者庁逐条解説第2条定義の中で、「本項は、解雇その他不利益な取扱いからの保護の対象となる通報について、単なる『通報』ではなく『公益通報』として定義し、①役務提供先に使用され、事業に従事する労働者等から、②不正の目的でなく、③公益を害する事実である当該役務提供先等の犯罪行為やその他の法令違反行為についてなされる通報であるという趣旨を明らかにしています。
公益通報とは公益通報の通報先として、役務提供先等、権限を有する行政機関等及びその他の外部通報先が規定されている。また、浜田聡参議院議員の質問に対して内閣総理大臣臨時代理林芳正国務大臣が、ご指摘の「逐条 解説・公益通報者保護法」は、消費者庁参事官室が編集したものであるが、「同法第11条第2項は内部通報(1号通報)のみを対象としたものとの記載はない」と答弁されています。
また、消費者庁の公益通報ハンドブック改正法(令和4年7月施行)準拠版にも明確に示されています。この法第11条第1項及び2項の規定に基づき事業者がとるべき措置に関して定められた指針第4の2が外部通報にも該当しますが、不利益取扱いの防止や範囲外共有、通報者の探索を防ぐ体制整備が求められており、この体制整備には、真実相当性の要件は問われていません。また不正目的については、結城参考人によると、裁判例から事業者に対する反感などの目的が併存しているというだけでは、不正の目的であるとは言えないとされています。
また、人事当局からも不正の目的があったとも聞いていない。
知事は文書を入手した翌日に通報者の探索を指示したこと、また、3月26日に退職承認の取消決定をしたこと、翌日の会見で本人が認めていなかったにもかかわらず事実無根だと認めているような発言のほか「公務員 失格」と通報者を侮辱するような発言は、不利益な扱いと考え、体制整備の義務に違反していると考えます。
そもそも、不正の目的があるのか等、公益通報に該当するのか調査をする前にそのような対応をしたことは全くもって不適切であると考えます。
また、公益通報者保護法の趣旨からは、知事や組織幹部に関する事案については、独立性を確保することが望ましいにもかかわらず、知事自身が事実でないと決めて3月27日の会見で元西播磨県民局長の職を解き、通報者を公表したことは、通報された当事者による告発者潰しといえる不適切な対応であります。以上の指摘に対する知事ご自身の見解を伺います。
3 元西播磨県民局長の名誉回復と処分の取消について
これまで述べて参りましたように、県は、元西播磨県民局長の公益通報に対し、通報者の保護を行わずに、通報者の探索と違法性の強い調査を行い、不当な処分を行ったと私は考えています。
このことから、直ちに元西播磨県民局長の名誉回復と、処分の取り消しを求めますが、如何ですか。
4 県庁舎建設の方針変更について
知事は3年前に県財政の厳しさから、県庁舎建て替えを一旦凍結して4割出勤と在宅ワーク等を前提とした庁舎建設の方向を打ち出されました。
その時私たちは、民間企業の先行事例等から、また、一定業務の限られた民間と比較して、防災対応を筆頭に多種多方面にわたる行政事務では、4割出勤での事務遂行は不可能と言ってまいりました。
しかし、知事は我々の意見に耳を貸さず、モデルオフィスの実証実験を行いました。そして、現在コンパクトな庁舎建設とおっしゃっています。
まず、コンパクトな庁舎建設とはどういうものか教えてください。併せて、この3年間の取り組みが適切であったかどうか、お伺いします。
5 県民や職員との対話・議会との調整を通じた政策立案について
最初に申し上げましたが、「ワンチームで県政を支えたい。大切なのはコミュニケーション。中堅や若手職員との対話の場を作りたい。風通しの良い職場づくりを進めたい」。と知事はおっしゃっていますが、そのためには何をしなければならないか、これまで申し上げたこれらの疑惑の解消なしではありえないと考えます。
ここまで、5項目のことについて質問・意見を申し上げてきました。いずれにおいても知事は、自分の考えを最優先にして、職員をはじめ多くの我々の意見に耳を傾けずに、強権的な手法で行政運営を行ったところにすべての原因があったように私には写ります。
これまで「陽の目」の当たらなかった分野に目を向ける、知事の発想や着眼点の素晴らしいところも私は感じています。それを謙虚に、まず職員に問いかけ政策案をつくる。そして、議会や関係部署・団体と意見交換する。そのようなことが、なぜできなかったのか残念であります。
そこで、県政を前に進めていくために、どのように県民や職員との意見交換や議会との調整を行い、それを政策に結び付けていかれるのか、改めてお伺いいたします。
6 少子化対策、結婚・家庭を持つ環境・意識づくりについて
厚生労働省が1月に発表した人口動態統計の速報値によると、昨年1~11月に生まれた子どもの数は、前年同期比5.1%減の661,577人であったとのことであり、このままでいくと昨年の出生数は初めて70万人を割り込むことが予想されている。
また、本県の同期間の出生数は、29,345人と3万人に達しておらず、前年同期比では6.0%の減となっている。
こうした傾向の主な原因は、子育てに対する経済的不安感の高まりや、新型コロナウイルス感染症の流行化に伴う未婚化の進展などが原因と言われていますが、特に未婚率の上昇については、コロナ禍以前からも相当な高まりを示しており、国立社会保障・人口問題研究所の資料によると、2020年時点における本県の50歳未婚率は、女性で17.68%、男性では25.40%と近年大幅な上昇を示している。
少子化の原因である未婚化の主な理由としては、結婚をとりまく意識の変化や結婚後の経済的不安など様々な課題が想定されていますが、私は先を見通しにくい社会情勢の中にあって、特に若者が将来展望を描きにくい意識に陥っていることが大きな要因ではないかと考えています。
先日、元県議・元豊岡市長中貝宗治氏の講演を受けました。豊岡市の出生数の変化は、2000年896人が2023年には57%減の386人となっています。
有配偶女性数(20~39歳)100人当たりの出生数は、1985年13.5人、2020年16.5人とむしろ増加しています。有配偶女性数は、1985年を100とすると64%減となっています。
2015年と2020年の年齢別・純移動率を見ると、10代後半で豊岡市を離れ20代以降に豊岡市に帰ってくる若者回復率は、男性41.6%、女性28.5%と実に13.1%の乖離があります。結婚するには、圧倒的に女性が少なく男性余り現象となっています。そのことがさらに、人口減少・少子化となっています。
中貝氏は、豊岡に暮らす価値は、①若者に選ばれていない、②特に、若い女性に選ばれていない。その原因に、豊岡は男性中心社会で、ジェンダーレスが求められるとおっしゃっています。さらに、若者にとって突き抜けた「豊岡に暮らす価値(魅力)」の創造が必要とおっしゃっています。
現在、進学や就職を経た結婚・出産に対する価値観が多様化する中で、結婚や出産・子育てを前向きに捉え、自身の豊かなライフデザインを形成していくための教育や啓発に力を入れることが必要で、県としては、若者が求める結婚・妊娠・出産・子育てへの希望が叶えられる環境づくりを速やかに整えていくことが 肝要であります。
こうした適切な支援の実施に向け、県では、現行の「ひょうご子ども・子育て未来プラン」を改定しようとしているが、申し上げた課題に対して、このプランの策定を通じてどのように取り組もうとしているのかについてお伺いします。
また、少子化にブレーキをかけるために必要な様々な施策は、例えば福祉部門だけで達成できるわけではなく、教育や、仕事と子育ての両立、経済的支援、地域や家庭といった数々の施策に関わる多くの部署が連携しながら取り組むことが必須となることから、その実現に向けた全庁横断的な実施体制づくりも欠かせず、そのあり方に関する当局の所見も併せて伺う。