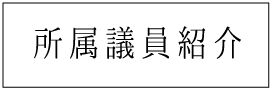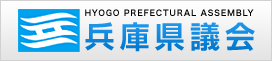理 事 北上 あきひと 議員(川西市及び川辺郡選出)
委 員 前田 ともき 議員(神戸市東灘区選出)
北上 あきひと 議員
財政状況 | 総務部・財務部・危機管理部 | 企画部・県民生活部・部外局 |
福祉部 | 保健医療部 | 公安委員会 | 農林水産部 | まちづくり部
前田 ともき 議員
総務部・財務部・危機管理部 | 企画部・県民生活部・部外局 | 福祉部 |
まちづくり部 | 教育委員会 | 総括審査
<北上 あきひと 議員>
●財政状況
1 地方財政計画の評価について
2 財政フレームについて
3 予算編成の在り方について
(1)予算シーリングについて
(2)予算編成における県内市町等との役割分担や連携について
4 宝くじの販売促進について
全文
1 地方財政計画の評価について (財政)
2025年度の地方財政計画の規模は97兆94億円、一般財源総額は67兆5414億円、交付団体ベースでは63兆7714億円であり、計画規模、一般財源総額ともに過去最高額を更新しました。歳入面では、全体的な賃上げ傾向や円安による好調な輸出産業等を背景とする国税や地方税の伸びによるものと考えます。
物価高は全般的な公共サービス経費を押し上げており、地財計画の歳出においても人事院勧告を踏まえた給与改定の反映、光熱水費や委託料の物価高対策、建築単価の引き上げ等、物価高に対応した経費増額を積極的に行っていると認識するところです。しかしながらこれら一連の経費計上によって、今後も予測される物価高や求められる対策経費の実情に十分対応可能なのかどうかは、見通せないところがあると懸念を抱くところです。
また、12月に発表された2025年度の税制改正大綱では所得税の給与所得控除および基礎控除合わせた最低保障額を103万円から123万円に引き上げることが明記されました。いわゆる「103万円の壁」の引き上げによる交付税財源の減収は2000億円と推計されていますが、現在は税収増によって還元している状況であり、今後の国会審議の推移によっては相当額の交付税減収分についての地財対策を講じることも議論になると推察します。しかし本来、地方交付税は地方固有の財源であって、税制改正よる影響は税収増の還元によって済まされるべきものではなく、地方交付税の法定率分の引き上げ等による恒久的な財源補填策を国に求める必要があると考えます。
地方財政計画の評価について、当局のご所見をお伺いします。
2 財政フレームについて (財政)
この度県が明らかにした財政フレームにおいては、税収の改善や経済成長率の上昇が見込まれること等から、2028年度までの収支不足額は一年前の試算よりも55億円改善し、160億円になる見込みであるものの、阪神淡路大震災から30年が経過してもなお震災関連県債の償還が続き、社会保障関係費の増加や長期金利の上昇等の影響もあり、2028年度以降も収支不足額が発生する見込みであるとしました。2025年度の見込みでは実質公債費比率の3か年平均が18%を超え、2026年度には県債発行に国の許可を要する「許可団体」になる見通しであります。県財政は大変に厳しい状況だと認識するところです。
実質破綻状態にある分収造林事業の債務整理では、2023年度補正予算と合わせて694億円の一般会計負担が生じます。地域整備事業においては、企業庁進度調整地の環境林取得に276億円が見込まれ、保有資産の整理(最大588億円)は先行きが不透明です。さらに病院事業会計は債務超過の状況が続いています。また、現時点では新庁舎整備にかかる総事業費が見込まれていない訳でありますが、この間の建築資材等の高騰の影響もあり1000億円以上の負担が生じることも指摘されています。このように、一般会計の負担も大きいことから、財政フレームへの影響も気になるところです。
県民の不安に応えるためにも、財政フレームを含め県財政についての分かり易い説明が求められると考えますが、県当局のご所見をお伺いします。
3 予算編成の在り方について
(1)予算シーリングについて (財政)
本県の毎年度予算編成おいては、施設維持費や運営費、政策的経費等の一般事業枠に属する経費についてシーリングを設定していると認識します。シーリングは予算抑制効果が認められ、財政の健全性を維持しつつ県民にとって必要な施策を展開するためには有用な策だと考えます。また、シーリング対象経費の予算査定については、要求内容の確認のみが基本となっており、査定事務の簡素化によって働き方改革に繋がっていることも理解するところです。一方、要求段階で予算額が決められるため、現場の課題に即した対応や社会経済環境の変化に合わせた事業に取り組めないといったことはないのか、また逆に不要な事業であっても基準の中であれば細かく査定が行われないため、シェアの固定化を招いてしまうなどの弊害はないのか、これらのことが危惧されるところであります。
予算シーリングの成果と課題について、当局のご所見をお伺いします。
(2)予算編成における県内市町等との役割分担や連携について (財政)
現下の厳しい財政状況のなかにあっては、事業の必要性や公共性が殊更に問われ、計画性や効率性が求められると考えます。加えて、無駄を省き事業効果を効率的に高めるために県内市町等との役割分担や連携を図る必要が増しているのではないでしょうか。
住民に関わる基礎的な業務は市町が担い、都道府県は広域にわたる事務や連絡調整、インフラ整備、各種許認可等を担うとものと認識します。市町単独では困難な規模や種類の業務においてこそ、県が役割を果たすものであり、財政当局におかれては、県の事業として相応しいのかどうかを峻別されたうえで、予算編成に努めて頂いていると考えるものです。
また、市町との連携を深め共同事業等を展開することによって県民の望みに応え、県民生活を支えることも重要な役割だと考えます。例えば、小中学校における校内サポートルームの支援員配置は、県と市町が課題を共有し前向きに取組んだことによって、効果的な施策が全県的に拡充されつつあるのではないでしょうか。新年度に予定される高校生等の自習室設置においても、計画段階からの市町等との丁寧な議論や調整は不可欠だと考えます。
予算編成においては県内市町等との役割分担の峻別や連携についてどのように整理されているのか、当局の基本的なお考えをお伺いします。
4 宝くじの販売促進について (財政)
県政の安定基盤保持のためには自主財源確保が重要であり、悪質滞納者への徴収対策、ネーミングライツや広告収入の確保、県債引受基盤の強化等の取組がなされているものと認識するところです。自主財源確保の取組策の一環である宝くじ販売促進については、本県では神戸市及びみずほ銀行と連携して若年層をターゲットにした広報活動を展開されております。宝くじの販売額の約4割が収益金として都道府県及び指定都市に配分をされ、新年度は約80億円の収入を見込まれているところです。
私は2022年度決算審査の際に「宝くじの売上げの一部が県財政に寄与することは承知するが、ギャンブルのゲートウェイとの指摘もある宝くじを、県が若者をターゲットに販売促進をすることには違和感を覚える」と指摘し、ギャンブル依存症対策の専門家による「ギャンブルを始める年齢が若ければ若いほど、依存症に陥りやすい。若者を取り込もうとするギャンブル業界の問題がある」との指摘は重く受け止めるべきだと訴えました。財務部長は「重要な自主財源としての販売促進と依存症対策の両立及び均衡ある発展を目指していきたい」と答弁されています。
国立病院機構久里浜医療センターが、2024年に有効回答数約9000人の大規模なギャンブル関連問題についての実態調査を行っています。調査によると、ギャンブル依存症が疑われる140人が過去一年に行った頻度が高いのは、パチンコ、パチスロ、宝くじの順でした。宝くじは身近なギャンブルとして浸透しており、特にキャリーオーバーで賞金が積み上がってくるタイプは、よりギャンブル性が高く危険だと指摘されています。現行においては、宝くじの購入経験者は50歳代・60歳代が特に高いとされており、オンラインカジノ等が深刻な社会問題となるなか、行政が敢えて宝くじで一獲千金を夢見る若者を増やす必要はないと考えます。自らの力を存分に発揮することによって夢を叶え、社会に貢献したり暮らしを豊かにしようと日々地道に努力する若者を支えることこそが県政の役割ではないでしょうか。
新年度における宝くじ販売促進策について、当局のご所見をお伺いします。
●総務部・財務部・危機管理部
1 災害時のドローンの活用における現状と課題について
2 個人情報保護について
(1)個人情報保護と守秘義務の履行を担保する取組について
(2)守秘義務違反容疑の刑事告訴について
全文
1 災害時のドローンの活用における現状と課題について
石川県能登半島地震の初動対応を検証してきた政府の関係省庁のチームは2024年6月に検証結果を明らかにしました。能登半島地震ではドローンによる被災状況の把握や孤立集落への物資輸送を実施した事例等が報告されています。輪島市においては、土砂が川の水をせき止める「土砂ダム」が発生した際に、ダム氾濫による二次災害の恐れから監視が必要でしたが、道路が寸断され目視が叶わないためドローンが活用されたり、また倒壊し立ち入りが危険な建物の内部調査等をドローンによって行われました。このような災害対応でのドローン活用は、これまでになかったことであり、政府は今後、時間帯や天候に左右されない高性能なドローンの開発を進める方針です。
本県においては、これまでにドローンによる物資輸送訓練や避難誘導訓練が行われていると認識するところです。昨年10月には、県広域防災センターで大阪府豊中市消防局の「災害対応ドローン総合技術訓練」が実施されたことが、消防の専門誌『Jレスキュー』で報道されています。記事によれば、2021年12月に発生した大阪市北区北新地のビル火災、2022年6月に千葉県野田市で発生した電車内での異臭騒ぎ、2024年の能登半島地震、これらの災害事例を参考に作成された3想定で実施されました。いずれも初動にドローンで情報収集することで、活動方針に大きな影響を与える情報が得られる災害だと指摘されており、豊中消防局関係者からの「消防がドローンで情報収集と人命検索をするという目的を設定しているならば、それに即した内容の訓練を行うべきだ」と考える。「有意義な訓練だと感じた」とのコメントが紹介されています。
知事提案説明では「防災‣減災対策の推進」が掲げられ、「能登半島地震を踏まえたひょうご災害対策検討会」の意見を踏まえて、防災対策を総合的に推進する旨が述べられました。新年度予算等に盛り込まれたトイレカーのモデル整備や耐震シェルターの設置支援等は県民の関心や期待が大きいと感じるところです。災害時のドローンの活用についても、関係機関や諸団体との連携を図りつつ取組を拡充する必要があるのではないでしょうか。ドローンを災害時に有効適切に活用するためのガイドライン作成、人材の育成や確保等、多くの課題があると考えます。
災害時のドローン活用における現状と課題について、当局のご所見をお伺いします。
2 個人情報保護について
(1)個人情報保護と守秘義務の履行を担保する取組について
県行政は業務の性質上、県民の所得や資産、交通事故や犯罪歴、病歴等の健康情報、子どもの成績や素行等、多種多様な個人情報を膨大に取り扱っています。だからこそ公務員には厳格な守秘義務が課せられており、地方公務員法第34条1項では「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする」とされ「職務上知り得た秘密」とは、職員が職務に関連して知り得た秘密であり、自らの担当する職務に関連するものの他、担当外の事項も含まれます。また第60条では法に違反し秘密を洩らした者は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と記されており、守秘義務に違反した場合には、懲戒処分と刑罰のいずれか、あるいはその両方を受ける可能性があります。個人情報の適正な取扱は、県民の県政への信頼の土台であり、恣意的な利用や漏洩は絶対に許されません。
県民の県政への信頼のもとに円滑な行政運営を行うためには、個人情報保護と守秘義務遵守の確実な履行が不可欠であり、それを担保するためにハード、ソフト両面にわたる対策が講じられていると認識するところですが、取組の現状と課題について県のご所見をお伺いします。
(2)守秘義務違反容疑の刑事告訴について
昨年7月、週刊誌において元西播磨県民局長の個人情報漏洩疑惑に関する問題が取り上げられました。そのことに端を発して、各種メディア等でも大きく報道がなされています。また百条委員会での聞き取り調査では、元総務部長から当該個人情報を「見せられた」との明確な証言が県議二人からあり、その証言内容は報道内容を凡そ裏付けるものだと認識するところです。多くの県民が県の取り扱う個人情報が恣意的な理由で漏洩したとのではないかと疑い、県の一連の対応に不信を抱いていると考えます。加えて、県民全体への奉仕者としての使命を自覚し、誠実に職務に精励する職員の士気にも影響を与えていることを憂慮するところです。事態は甚だ深刻であります。
先の本会議代表質問において我が会派の上野英一議員が当該事案について「速やかに刑事告訴しない理由について」質問を致しました。知事からは「現在調査を進めているところであり、今後の対応については調査結果を踏まえて検討する。」との答弁かあったところです。なぜ、第三者委員会による調査の結果を待つ必要があるのでしょうか。今なお真偽不明の個人情報は拡散を続けており、現状の県当局の姿勢は著しい人権侵害を不作為によって助長していると言われても仕方ないのではないでしょうか。本県が取り扱う個人情報が漏洩した蓋然性は極めて高く、県において詳細な事象の把握に至っていなかったとしても、速やかに刑事告訴をすることが県民の個人情報を取り扱う行政機関としての責任ある対応だと考えます。
当該守秘義務違反容疑の可及的速やかな刑事告訴を求めますが、県のご所見をお伺いします。
●企画部・県民生活部・部外局
1 「パートナーシップ制度」について
2 県内企業におけるLGBTQ+当事者の活躍を促進する取組を積極的に進めるための制度について
全文
1「パートナーシップ制度」について
本県「パートナーシップ制度」は昨年4月1日に運用が開始されました。その初日早々には1組目のカップルの届け出がなされ、本年2月末日現在既に72組に受理証明書が交付されています。本県ホームページには、パートナーシップ制度届出者からのメッセージが掲載されていますが、例えば「安心材料が増えました。もっと、ずっと、笑顔でいましょう!」とか「私達を認めて頂きありがとうございました。これからも笑顔になる人が増えますように」また「老後の人生明るくなりました。パートナーシップに感謝のみ」等のメッセージを拝見すると、この制度によって県民お一人お一人の安心感に寄与したり人権が救済される等、心豊かな暮らしに繋がっていることを実感するところです。当該制度への県民の理解が一層深まることによって、誰もが人間としての誇りを持って安心して暮らせる社会環境が形成されることを期待します。
当該制度運用開始にあたっては、県内市町との連携や制度の相互利用、他都道府県との調整、制度への不安を抱く県民への周知啓発等が課題となっていたと認識するところですが、運用の現状と課題、今後の取組について、当局のご所見をお伺いします。
2県内企業におけるLGBTQ+当事者の活躍を促進する取組を積極的に進めるための制度について
2022年度決算審査において、私は「LGBTQ等セクシャルマイノリティが自分らしく働く職場整備について」質問し「全ての人が勤労者としての権利が守られ、自分らしく働くことのできる職場が保障されなければならない」と訴えました。労政福祉課長からは「LGBTQ等セクシャルマイノリティの当事者を含めた多様な人材が活躍できる職場環境を実現していくということは、ダイバーシティ&インクルージョンを推進する上での課題でもある」「働く人一人ひとりが自分らしく働ける職場づくりを推進していきたいと考えている」との前向きな答弁があったと記憶しています。
求人検索エンジンを提供するインディードジャパンが当事者1,000人に実施した意識調査では、職場で生きづらさを感じると回答したLGBTQ+当事者は39.1%であり、非当事者26.8%の約1.5倍でした。企業の人事担当者500人への調査では、セクシャルマイノリティの従業員への支援に取り組む企業は、大企業39%、中小企業18%、全体で24%でした。更なる取組みが求められていると考えます。
本県には県内企業の女性活躍を促進するための制度として、女性活躍や多様な働き方等に積極的に取り組む企業等を認定し、認定企業には入札参加資格においての加点や兵庫県信用保証協会の保証料率の割引等のメリットを付与する「ミモザ企業」認定制度がありますが、LGBTQ+当事者の活躍を促進する取組を積極的に進めるための何らかの制度も必要ではないでしょうか。先述の意識調査によると、企業によるLGBTQ+当事者の従業員を支援する取組は、結果的に誰もが安心して生き生き働ける職場環境づくりに繋がっていることが明らかです。例えば、平均勤続年数が長い、お互いを認め合う風土がある、上司に相談しやすい、従業員の心理的安全性が高い、社外からの企業イメージが良い等の調査項目においては、取組ありの企業が無しの企業に比べて20%以上高い回答率になっています。県内企業におけるLGBTQ+当事者の活躍を促進する取組を積極的に進めるための制度について、当局のご所見をお伺いします。
●福祉部
1 高校生を含む若者のギャンブル依存症対策について
2 障がい者の「親なきあと」問題について
3 介護現場における職員の処遇改善と確保増員について
全文
1 高校生を含む若者のギャンブル依存症対策について(障害福祉課)
オンラインカジノ利用者らの摘発者数は2024年、過去最高に上りました。警察庁によると、24年の利用者の摘発は279人、23年の107人から2.6倍です。しかもこの数字も「氷山の一角」だと言われており、報道等によれば日本の利用者は300万人とも350万人とも推計されています。専門家は「違法だと認識せず、ゲーム感覚で手を出す場合が多い」「一度利用すると、依存症に陥る危険性が高い」と指摘しています。ギャンブル依存症家族会の関係者は「合法である公営競技の競馬や競艇もオンラインが主流となっており、宝くじを含め、SNSにはギャンブル依存症に繋がりかねない情報が溢れている。オンラインギャンブルの広がりで、特に若者の依存症が増えている」と危惧されていました。
また、全国ギャンブル依存症家族の会による緊急アンケートによると、「当事者に犯罪行為があった」との回答が、回答者681人中230人と3割を超えていました。その内、闇バイトは30人です。ギャンブル依存症問題を考える会の田中紀子代表は「私がギャンブル依存症に関わり始めて20年ですが、これば由々しき事態です。依存が急速に進行し、3人に1人があっという間に犯罪に結びつく。何とかして日本の若者たちを守らなければなりません」と語っておられます。
私の事務所に来られた家族会の方は「息子は高校三年生で部活動を引退し受験も終わった時に、心に隙間が出来たのか、スマホでギャンブルを始めたようです。無事に志望の入学し喜んでいたのですが、しばらくしてギャンブルで大きな借金を作ってしまっていたことが分かりました。結局、大学は退学しました。高校生にギャンブル依存症の啓発を是非行ってください」とお話しされました。本県では2021年度に作成した「ギャンブル等依存症対策推進計画」に基づいて対策を展開してこられました。その「第2期計画」策定時に開催された協議会においては、新たな課題として、公営競技等のインターネット投票やオンラインカジノの急速な拡大とそれに伴う依存症発症の短期化、低年齢化についての指摘があったと認識するところです。
ギャンブル依存症対策については、高校生を含む若者への働きかけが特に求められていると考えますが、その取組の現状と課題について、当局のご所見をお伺いします。
2 障がい者の「親なきあと」問題について(障害福祉課)
「第7期兵庫県障害福祉実施計画」においては、その目標を「一人ひとりが尊重され、互いへの思いやりとつながりがある中で、住みたい地域・場所で、ともに暮らしていける社会」と定めています。本県の「障害者の暮らしに関する課題検討報告書」によると、「将来暮らしたい場所」として、現在住んでいる住居の形態を問わず「今住んでいるところに引き続き住みたい」と希望する者の割合が高く、次いでグループホーム、障害者施設の順になっており、他団体の調査結果においても凡そ同様の傾向だと認識するところです。障がい者本人が住み慣れた住居で生活を希望したとしても、同居する親の高齢化に伴う介護力の低下や親の死亡によって、在宅生活が叶わないことは多分に想定されます。同居する親がいなくなった後においても、本人の意思が尊ばれ健康で文化的な暮らしが叶うのかどうか。いわゆる「親なきあと」問題です。親なき後に残された子どもに対する心配は、子を持つ親にとって共通の心情でありますが、障がいのある方のご家族にとっては、一層大きい心配であると考えます。
「親なきあと」問題については、その親が健在の間に見通しを立てつつ、準備を進めることが必要であり、新年度においては引き続き「親なきあと」等を見据え、在宅障がい者や保護者の希望する暮らしの実現に向けた説明会の開催がなされるものと存じますが、「希望する暮らし」を実現するにあたっては、在宅支援サービスやグループホームの拡充が必須であり、取組の更なる推進が求められるのではないでしょうか。また、例えば県内市町ではニュータウン等の戸建て住宅地の地区計画において、グループホームが共同住宅や寄宿舎として扱われることから、結果的に制限される事例を聞き及ぶところではありますが、広く県民の理解のもとに必要な緩和が図られるべきだと考えることから、福祉部として関係部局との連携のもとに適切な助言指導を行うことを求めるものです。
障がい者の「親なきあと」問題の解決に向けた取組における現状と課題について、当局のご所見をお伺いします。
3 介護現場における職員の処遇改善と確保増員について(高齢政策課)
団塊世代を含め国民の5人に1人が75歳以上の後期高齢者となる「2025年問題」は、介護の現場においてもその影響が大きく及ぶと予想されているところです。厚労省の資料によると、2025年には75歳以上の高齢者が2,000万人(人口の18.1%)に達します。兵庫県における75歳以上人口は973,630人(18.3%)と推計されています。介護保険サービスの需要は今後急増すると見込まれ、2040年度には全国で約57万人の介護職員が不足すると推計されています。担い手不足への対応は極めて重要な課題です。
訪問介護においては、昨春の介護報酬改定で基本報酬が引き下げられました。国はヘルパーの処遇改善に向けた加算率を手厚く設定したことを強調していましたが、介護現場からは「やりがいのある仕事だが、給与は上がらずボーナスもなく家計はしんどい。いつまで続けられるのか分からない」「仕事に見合った処遇にしないと、若い人が介護業界には来なくなるのではないか」との声が数多寄せられているところです。国や自治体による、処遇改善に向けた更なる施策展開が求められていると考えます。
また、厚労省の国民生活基礎調査によると、2022年時点で、介護の必要な高齢者のうち、同居の高齢者に介護されているいわゆる「老老介護」の割合は増加傾向にあり、2022年においては63.5%でした。警察庁の2023年の統計によると「介護・看護疲れ」を理由にした殺人事件(含未遂)は23件で、その被疑者のうち男性は17件でした。「介護・看護疲れ」を理由とした自殺者は348人で、60歳以上が56%で、全体の58%が男性でした。専門家は「真面目で配偶者思いの人ほど、一人で抱えやすい。特に男性の方が悩みを周りに打ち明けられない場合が多い」と指摘しています。支援を必要とする人に適切なサービスを繋げるケアマネジャー等の役割は大きく、その確保増員も喫緊の課題ではないでしょうか。
新年度にあっては「介護人材の確保及び資質の向上」に関する施策を種々推進されることと存じます。特に介護現場における職員の処遇を改善し、職員の確保増員を図ることが重要だと考えますが、県当局のご所見をお伺いします。
●保健医療部
1 被爆者への支援と被爆者の想いを継承する取組について
2 ハンセン病の元患者や家族への支援とハンセン病問題への理解促進について
全文
1 被爆者への支援と被爆者の想いを継承する取組について(疾病対策課)
昨年10月、70年近くにわたり被爆者の立場から核兵器廃絶を訴えてきた日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)がノーベル平和賞を受賞しました。ノーベル平和賞の選考委員会の声明には「日本被団協は“ヒバクシャ”として知られる広島と長崎の被爆者たちによる草の根の運動で、核兵器のない世界を実現するために努力し、核兵器が二度と使われてはならないと証言を行ってきた」「被爆者は筆舌に尽くし難いことを言い表し、核兵器によって引き起こされた計り知れない痛みと苦しみへの理解に貢献している」と記され、被団協と被爆者への心からの敬意を表しています。加えて「いつの日か、被爆者が存在しなくなる時が来るだろう。日本の若い世代は被爆者たちの経験とメッセージを継承している。彼らは世界中の人たちを鼓舞し、伝え続けている」と被爆者の想いを受け継ぐ若者の活動の意義を強調したことが大変に印象的でした。昨年6月に広島、長崎、兵庫の「高校生平和大使」がノルウェー・オスロのノーベル平和賞委員会や非政府組織(NGO)等を訪問し、被爆者の想いを伝え核兵器の非人道性をアピールした影響は大きかったと考えます。
「高校生平和大使」は1998年に長崎県でスタートした高校生による平和運動です。「一人ひとりの力は微力だが、無力ではない」をスローガンに、核兵器廃絶と平和な世界の実現を求めて様々な活動を行い、毎年夏のジュネーブ軍縮会議にあわせて代表を派遣しています。兵庫の高校生も「平和大使」に参加しており、昨年夏には県内の高校2年生がジュネーブに赴きました。これらの地道な取組が、核兵器のない平和な未来を実現するための大きな力であることは間違いありません。
本年は戦後80年の節目の年であり、戦争の惨禍と核兵器の非人道性を改めて心に刻み、非核平和の世界を築く歩みを前進させなくてはなりません。県議会においては、2017年12月に「世界の恒久平和と核兵器の根絶を希求する兵庫県宣言」が全会派一致で採択されていますが、恒久平和と核兵器の廃絶は被爆者の想いであり、同時に県民の総意でもあります。被爆者をはじめ県民の願いに応えるために、施策の展開をより一層図るべきではないでしょうか。当局におかれては、医療特別手当等の支給業務をはじめ被爆者等に対する支援を長年にわたり続けておられるとともに兵庫県被団協への補助を通じて原爆体験記憶継承事業を支援されてきたと認識するところです。それら施策の現状と今後の課題について、当局のご所見をお伺いします。
2 ハンセン病の元患者や家族への支援とハンセン病問題への理解促進について(疾病対策課)
ハンセン病はかつて「らい病」と呼ばれ、法律によってその患者は社会から隔離されました。1929年から全国的に始まった「無らい県運動」では、各県が競ってハンセン病患者を見つけだし、強制的に療養所に入所させられたのです。そもそもらい菌は非常に感染力が弱く感染しにくにも関わらず、これら隔離政策により、ハンセン病は伝染力が強いという間違った考えが広まり、偏見を大きくしたと言われます。戦後も状況は変わらず、患者とその家族は結婚や就職を拒まれる等の差別を受け、またその差別への恐怖が故に適切な医療を受けられない等、辛苦の歴史を刻んで来られました。1996年に「らい予防法」は廃止をされ、2001年に新たに補償を行う法律が制定されました。2002年には、療養所退所後の福祉増進を目的とした「国立ハンセン病療養所等退所者給与金事業」が開始され、同時に名誉回復のための取組が推進されていると認識するところです。入所者は既に高齢で、後遺症による重い身体障がいのある方もおられます。また残念ながら差別や偏見がなくなっていないことから、安心して療養所から退所することが出来ない現状があると聞き及びます。
兵庫県では、ハンセン病問題の解決に向け、里帰り事業や、療養所の訪問、相談体制の充実など療養所入所者の皆様への多彩な生活支援に取り組んで来られました。さらに、ハンセン病への偏見・差別を解消するための啓発事業も展開されています。引き続き、元患者に寄り添った誠実な対応を願うものです。またコロナ禍においても人権侵害が惹起しましたが、ハンセン病に係る歴史と課題を学ぶことは、元患者やその家族の人権確立に寄与するとともに、私たちの社会において新たな差別を生み出さない力にもなると考えます。ハンセン病の元患者や家族への支援とハンセン病問題への理解促進における現状と課題について、当局のご所見をお伺いします。
●公安委員会
1 交通事故多発交差点における交通事故防止対策について
2 鉄道施設における安全・安心の確保について
(1)鉄道施設における受験シーズン中の痴漢対策について
(2)鉄道施設における無差別殺傷事件や駅員等に対する暴力事案への対応について
3 道路標示の補修について
全文
1 交通事故多発交差点における交通事故防止対策について
2024年中の兵庫県内における交通事故の発生を見ると、交通事故で亡くなられた方は109人、怪我をされた方は約18,000人という結果でした。
そのような中、先般、県警察から、2023年中における兵庫県内の交通事故多発交差点について発表がなされたところであり、川西市内の「小花1丁目交差点」が、県内で最も多くの交通事故が発生した交差点であることが明らかになりました。
小花1丁目交差点では、2023年中、13件の人身交通事故が発生しており、その内、主な事故類型については、右折車両対直進車両による事故や、追突事故とのことであります。
私は地元ですから、この小花1丁目交差点をよく利用している訳ですが、当該交差点は、付近に駅や商業施設があるため、人待ち駐車や施設利用目的と思われる車両の駐車が目立ちます。また昼夜を問わず、バス停やその付近にまで多くの車両が停車をしており、バス利用者の安全な乗降を阻んだり、車道上の円滑な交通の流れを阻害している状態を頻繁に見るところです。
今回、この小花1丁目交差点が交通事故多発交差点となった訳ですが、私は、交通事故が発生する原因は、前をよく見ていなかったとか、安全を確認していなかったといった運転者のミスによるものばかりではなく、この小花1丁目交差点のように、駐車車両等が交通の流れを悪化させることで生じる交通渋滞など、交通環境の悪化も、交差点における交通事故が多発する要因の一つとなっているのではないかと考えています。
県警察では、交通事故を未然に防止するため、その交通事故が発生した 原因について調査を行い、その上で、交通規制の見直しや交通取締りなどの対策を講じておられると承知していますが、小花1丁目交差点を含め、県警察として把握している交通事故が多発する交差点については、どのような 交通事故防止の対策を講じていくのかお伺いします。
2 鉄道施設における安全・安心の確保について
(1)鉄道施設における受験シーズン中の痴漢対策について
列車内や駅構内で敢行されることが多い痴漢行為は、被害者の心身に 深刻な影響を及ぼす重大な性犯罪です。
昨今、SNS上で、受験会場に遅刻できないため被害を訴える暇のない受験生を狙った痴漢行為をあおる投稿がなされていると承知しているところですが、あまりに卑劣であり強い怒りを覚えます。
県警では受験シーズンの痴漢対策をどのように講じ、県民や鉄道事業者に対してはどのような働きかけを行っているのかお伺いします。
(2)鉄道施設における無差別殺傷事件や駅員等に対する暴力事案への対応について
昨年12月、神戸市営地下鉄三宮駅において女性が刃物により斬りつけられる殺人未遂事件がありました。また、駅員や乗客に対する暴力や 暴言についても日々発生していると承知しているところです。
これら事案は鉄道の円滑な運行を阻害し、鉄道利用者を不安に陥れるもので、列車内等での無差別殺傷事件や駅員等に対する暴力事案の未然防止、事案発生した場合の対応についてお伺いします。
(再質問)
駅員に対するカスタマーハラスメントについて
駅窓口に長時間居座ったり、連日窓口に訪れて理不尽な要求や不平不満を言う者がいて、駅員の業務の妨げになっているなど、駅員に対するカスタマーハラスメントが急増しているという話を聞きます。
カスタマーハラスメントについては、近年大きな問題となっており、 行き過ぎたマナー違反やハラスメント行為は既存の法令に抵触することがあると思いますが、当局のご所見をお伺いします。
3 道路標示の補修について
公安委員会事業としての、横断歩道をはじめとする道路標示については、交通事故が発生しやすい場所にこそ必要であり、そうした道路は、一般的に交通量が多いことから、自ずと摩耗で塗装がはげやすいという特徴があると認識します。
道路標示は、公安委員会が交通規制を実施するにあたり、運転者に具体的な意思を表示する手段であり、摩耗等によって視認性が下がれば、交通事故や交通違反の原因ともなり得るため、適正な管理が必要であると考えます。
横断歩道については、昨年初頭、交通死亡事故が多発し、その中でも車両と歩行者の事故が多発傾向にあったことから、県の「横断歩道等安全対策 プロジェクト」の一環として、2023年度補正予算で、県内全域において摩耗が激しい横断歩道約10,000本の緊急補修を行ったと聞いており、今後一定の事故防止効果が現れるものと考えます。
しかし、道路標示は横断歩道だけではなく、ドライバーに横断歩道の存在を事前に知らせるためのダイヤマークや、車両の停止位置を明確に示す停止線、対向車線にはみ出しての通行を禁止する黄色のセンターラインなど、 その他の道路標示も薄くなっている場所が県内全域にあることから、交通 事故を防止していくためには、補修が必要不可欠ではないでしょうか。
また、常に劣化していくものであることから、摩耗しやすい場所の把握に努めるなど、今後も引き続き適正に管理する必要があると思いますが、今後の取組についてお伺いします。
●農林水産部
1 治山事業について
(1)治山事業等の広報啓発について
(2)六甲治山事務所管内における治山事業について
2 里山の保全・再生について
全文
1 治山事業について
(1)治山事業等の広報啓発について
いつ発生するか分からない自然災害から、県民の生命財産を守るための事前対策は極めて重要であり、県の果たす役割は大きいと考える。庁内 各部においては、防災・減災を目的とした各種対策事業を推進していると認識しており、農林水産部では、激甚化・頻発化する山地災害に対応するための「第4次山地防災・土砂災害対策計画」に基づく事業や、漁港の耐震化、津波・高潮防災対策の推進、災害に強い森づくり、ため池防災工事等に取り組んでおり、円滑な進捗を期待する。
私の地元である猪名川町では、町立楊津小学校の裏山が、2018年7月の集中豪雨により崩壊し、流下した土砂により体育館の一部が破損する被害が出た。兵庫県神戸県民センター六甲治山事務所において、翌年から治山事業による復旧工事が行われてきましたが、2024年9月に約5年間に わたる全体工事が完了。昨年8月には、県議会農政環境常任委員会による現地調査が行われ、私も地元議員として出席した。近隣の住民からは 「学校の安全が確保できて、子どもも大人も喜んでいます。学校は避難所にもなりますが、これで安心です」等の意見を聞くところであり、嬉しく思うところである。
六甲治山事務所と治山課においては、楊津小学校の3~5年生の子どもたちを対象に、裏山復旧工事でどのような事が行われてきたのかを、工事受注者の協力や、実験装置を用いながら知ってもらう、課外授業が実施 された。
学校の教職員や地域の皆さんから、「分かり易く大変有意義だった」 「子どもたちも楽しく学べた」等の声が寄せられている。子どもたちに 森林の果たす役割や治山事業の目的、復旧工事の工法等がしっかりと 伝わったものと考える。
当該課外授業のように、治山事業をはじめとする災害から県民の生命 財産を守るための各種事業に関して、その内容や意義を広く伝えていく ことは、防災意識の高揚、環境保全への理解促進等に寄与するものであり、ひいては森林土木技術人材等の育成確保にもつながるものと考える。
子どもたちを含む県民への治山事業等の広報啓発について、当局の所見を伺う。
(2)六甲治山事務所管内における治山事業について
六甲治山事務所においては、管内の市町との連携を図りながら各種工事を推進し、安心安全な地域づくりに尽力頂いているところである。しかしながら、例えば山地災害危険地区対策の進捗率を見ると、私の地元である川西市と猪名川町は同率の11.4%であり、この進捗率は管内ワースト1 である。進捗状況は各々の箇所の事情による影響も大きく、当局においては鋭意取組を進めて頂いているところであり、そのことには心から敬意と感謝を表するものである。
今後の更なる進展を大いに期待するが、六甲治山事務所管内における 治山事業の現状と課題について、当局の所見を伺う。
2 里山の保全・再生について
先の質問で取り上げた猪名川町立楊津小学校の校区においては、田舎 暮らしを希望する子育て世帯の新規移住が見受けられる。その内の幾世帯 かにおいては、地権者だけではなかなか手入れの行き届かない森林の維持 管理を手伝っており、その作業は無償であるものの、例えば伐採した木の 一部を無料で譲り受け、薪ストーブの燃料としていると聞き及ぶ。
里山の豊かな生態系は、人が手を加えることで維持されてきた。しかし、人口減少や高齢化に伴い、人の手が行き届かず、豊かな生物多様性や保水力等の防災機能が著しく低下することが懸念されている。当該地区の取組は、里山放置林の問題を解決し、里山の保全・再生につながる好事例だと感じるところである。
兵庫県の県土面積に占める森林の割合は、令和6年3月末時点で67%、 約7割を占めており、当局におかれては特に集落周辺の里山林等において、生物多様性の保全や、防災機能の向上を重点にした森林整備を進められて いると認識するところである。
コロナ禍を経て都市部集中型から地方分散型社会への動きが見られるなか、身近な里山林を保全・再生する取組の今後について、当局の所見を伺う。
●まちづくり部
1 オールドニュータウン再生に向けた取組について
2 県立都市公園利用者への熱中症対策について
全文
1 オールドニュータウン再生に向けた取組について(住宅政策課)
川西市、猪名川町には、日生ニュータウンをはじめとする、オールドニュータウンが数多く存在します。高度経済成長期の都市部への人口流入に対応して郊外に開発されたニュータウンは、約半世紀に及ぶ歳月を経て、急速な高齢化、年少人口の減少、空き家の増加、各種施設の老朽化、日常生活を支える医療、交通、小売業の減衰等が課題となっており、住民や市町行政、事業者等が連携し、若年層世帯の流入策や商業施設活性化策等を講じて、持続可能なまちづくりに取組んでいるところでありますが、県の果たす役割も大きいと考えます。
本県では、ニュータウン再生のための具体的な取組事例等を示した「兵庫県ニュータウン再生ガイドライン」を作成したり、オールドニュータウン商業施設等空き区画活用支援事業によって新規出店を促す等、種々の支援策を講じていると認識するものです。更に、阪神間における「子育て住宅促進区域」の指定と重点支援や県外からの阪神間への住み替え支援については、ニュータウンでの活用を大いに期待をするところでありますが、これら施策の取組実績や新年度以降の展開について、当局のご所見をお伺いします。
2 県立都市公園利用者への熱中症対策について(公園緑地課)
県立都市公園では、昨年の夏に子供の遊び場環境の充実に係るアンケートを行い、要望の多かった夏場の熱中症対策として、日除けやベンチを今後整備していくと聞いています。
近年の夏場の高温状況を鑑みると、熱中症対策は、子供の遊び場だけではなく、公園全体に必要と考えます。例えば、私の地元の西猪名公園のテニスコートでも日陰がなく、夏場の炎天下のなか利用者がプレーしています。特に、夏場炎天下でスポーツを行う利用者に対しては、休憩時の日陰対策は優先すべき事項と思いますが、当局のご所見をお伺いします。
<前田 ともき 議員>
●総務部・財務部・危機管理部
1 県民だよりひょうごの発行費半減とネット強化
2 県庁舎再整備~事業費の削減策~
(1)長田楠日尾線の廃止による事業収支と開発自由度の増加
(2)阪神線魚崎高架下への分庁舎等の移転
3 公営掲示場の3割減で2.5億円の費用削減
4 ネット公営掲示板の開設とバナー・SNS広告の活用
5 フェニックス共済の設計・運営上の課題
(1)保険料の改定がされてこなかった理由
(2)保険料の改善案~契約期間の短縮と築年数別保険料~
(3)基金運用の改善案~兵庫県債への偏重と低利回り~
全文
1 県民だよりひょうごの発行費半減とネット強化
県民だよりひょうごは2.7億円もの予算が計上。記事を拝見すると、フェアトレード紅茶の開発、ひょうごジビエコンテスト、コント劇大会、黒豆ヴィーガンバターなど税金で周知すべきコンテンツなのか疑問である。
エンタメ、親しみやすい要素や紙面づくりは大切だが、尖った情報はネット・SNSに親和性があり、コストもかからないが刺されば拡散が期待できるので、ネット移行すべき。
既に民間の紙媒体は新聞を含めて廃刊が続いている。愛読していた日経産業やヴェリタスもネットに移行した。
添付資料のとおり、媒体別広告費は20年前の2005年に新聞15.2%、ネット5.5%とリアル中心の比率だったのが、2023年には新聞4.8%、ネット45.6%と激変している。
広告主は費用対効果が高い媒体選定を紙からオンライン化を進める中、 前例踏襲で県民だよりひょうごに要する経費を毎月2,000万円以上の税金を 使って配布していく必然性は今やない。毎月発行から数か月に一度、ページ数も削減し、本当に行政として届けたい情報のみに限定し発行費用を大幅に削減させる。
エッジの効いた要素はネットでコストを抑えて発信する体制に変更すべきと考えるが、どうか。
2 県庁舎再整備~事業費の削減策~
上場企業のIR資料を見ていると、人的資本経営とオフィス環境の重要性を意識する記載が目につく。GAFAMもオフィス回帰し、やはり人も動物。面と 向かって会う機会を作り、帰属感・雑談を通じて生まれるアイデアなどの 生産性が上らない。オフィスの質についても、温度、湿度、照度などで生産性や集中力に影響があることを指摘してきた。
県庁舎再整備の費用を落としたい思いは同じなので、以前申し上げた議場廃止や会議室などの行政共同化などに加えて2点提案する。
(1)長田楠日尾線の廃止による事業収支と開発自由度の増加
県庁すぐ南を横切る神戸市道長田楠日尾線。自動車の通行量は極僅かで、代替道路も南北にあり不要な道路。県庁南側部分だけで、ざっくり1,000坪あり市場価格より低い公示地価327万円でも30億円超の資産価値。
全部マンションとすると70㎡で280戸、7,000万円としても約200億円の売却、総工費120億円とみても80億円引く土地代で数十億円の収益になるのでは。加えて、今後は固定資産税が入る。
経済価値を最大化した場合の例を挙げたが、廃止すれば、形のきれいな大きな開発用地となり活用の選択肢増加や売却収益で事業費削減につながる。
県は神戸市のオフィス誘致、タワマン否定の方針でマンション組み入れは否定的のようだが、あくまでも現神戸市長の意向にすぎず、気にする 必要はない。
また、解体・建築時には建築資材置き場として工期・費用縮減に貢献。増加した延べ面積の一部を収益性以外の施設も組み入れることで地域貢献性、元町活性化要素も追加できる。
今後の県庁舎再整備の議論が本格化する前に神戸市道長田楠日尾線の 廃止と、県が購入し、大前提となる利活用可能な土地の拡張を図るべきと考えるが、どうか。
(2)阪神線魚崎高架下への分庁舎等の移転
阪神電車の高架化によって、東灘区の魚崎から深江駅あたりまで大規模な空き地が誕生したが、ほとんど活用されていない。今回の提案は兵庫県がこの土地を長期借上げ、分庁舎や県民会館ギャラリーを移転すること。
元町庁舎近辺の公示地価が坪327万円に対して、魚崎駅周辺は80万円と1/4程度の土地値。加えて高架下は長期・大規模面積を借り上げる店子を 見つけるのは難しく、単純な土地値比より更に割安に借りることが可能 だろう。
更に、木造は鉄骨鉄筋コンクリート造より建築コストが半分以下。県産木材の活用に加え、施工も早く、建築には地元企業も活用でき、様々な点でメリットが多いのではないか。数十年後の職員数の減少に対応する オフィス面積調整弁にもなる。
高架下を行政が賃貸し、行政サービスを提供している事例は増加して いる。国立市と国分寺市が広域連携でJR国立駅高架下に住民サービス拠点を設置。京都市もライブラリー、カフェ、市民活動室などを備える行政 サービス施設を高架下に設置し、利活用と地域活性化をしている。
事業費削減のためには、割高賃料の元町に拘泥することなく、割安な エリア、高架下への移転も行うべきと考えるが、どうか。
3 公営掲示場の3割減で2.5億円の費用削減
知事選挙では投票率が41.10%から55.65%まで14.55%急上昇した。これまで投票率向上へ様々な取り組みがなされてきたが効果はなく、争点や関心があれば、県民は投票にいくというあたりまえの結果。そして、従来から 感じていた公営掲示板の費用対効果に疑問を強めた。
公営掲示板は直近の知事選挙では13,033箇所と膨大な箇所。掲示板の 設置・撤去や各候補者のポスター貼り付け作業。その割に、投票の参考に なるか、啓発につながるか、疑問。
また、狭いエリアに集中して何か所も設置されているのはざら。税金と 人的資源の無駄。過剰な掲示板数による高額な選挙費用は費用対効果に懸念。
公営掲示板の費用は直近の知事選挙が約4.4億円で、今回は候補数増対策により掲示板を一部増設し、費用が更にかかった。加えて、候補者へのポスター公費負担は請求額で394万円。
仮に公営掲示板の数を3割減らせば、掲示板とポスター公費負担の削減分だけで知事・衆参両院・統一地方選挙の1サイクルで、ざっと2.5億円の 税金が削減できる。
法定数は一応定められているものの、地域の実情に応じて「効果が見込めない場所」の掲示板を省くなど、設置数を見直す運用が行われている。 例えば茨城県常陸大宮市は、掲示板の設置箇所・数を全市的に見直し、274 か所から199か所へと約75か所27%削減した。
兵庫県は法定数13,231に対し設置数13,033と削減が足りない。
掲示板に対する過剰評価を見直し、無駄な支出削減のため3割カットを 目指すべきと考えるが、どうか。
4 ネット公営掲示板の開設とバナー・SNS広告の活用
今回の県知事選挙はネットが良くも悪くも大きな影響を与えた。今後は 選挙管理委員会としてもリアルの公営掲示板や選挙公報の折り込みだけで なく、ネットへの配分増が必要だ。
公営掲示板の削減でカットした予算の一部で、ネット上の公営掲示板・ 選挙公報の運営やプッシュ型でバナー・SNS広告の活用を提案したい。
選挙管理委員会も紙の選挙公報や掲示板偏重からネットへシフトすべき だが、ネット関連の費用は僅か1,500万円である。「最小経費で最大の効果」の観点からも最適化が必要。
SNS型広告でプッシュ型認知をとり、オンラインでポスターと選挙公報を 掲示するサイトを運営する。候補者の増減にも対応でき、掲示板の木材廃棄や人的資源の無駄削減にもなる。そして、仕組みは他自治体にも有償提供 して、投資資金を回収する。
リアル偏重から脱却し、ネット比重を増やすことで、選挙啓発の効率性と選挙運動の無駄削減、選挙費用の削減につなげるべきと考えるが、どうか。
5 フェニックス共済の設計・運営上の課題
損保業界は、自然災害リスクの増大により収支が悪化している。平時は 自動車保険などの黒字で火災保険の赤字を補い、トータルで引受利益を確保する状況。金融庁のレポートによれば、2021年度の損保各社の保険引受利益率は+3.9%だが、火災保険分野に限ると-15.0%。火災保険料率の引き上げ (参考純率の改定)や長期契約の短縮などで収支改善を図っている。
火災保険の算定根拠となる損害保険料率算出機構が出す参考純率は、ここ10数年で全国平均2割程度の引き上げ。一方で兵庫県地域は、地震リスクの見直しで基準料率が2014年7月16,500円から2022年10月改定11,200円と大幅に値下がりしている。
しかし、グローバルな自然災害の増加傾向等の影響により再保険市場は ハード化。金利上昇、インフレ等の影響により、2023 年には再保険契約更改では、米国の自然災害で40%前後の大幅な再保険料の引き上げが行われ、 日本は約20%の引き上げ。フェニックス共済は再保険していないが、類似の 対応も必要だ。
(1)保険料の改定がされてこなかった理由
私は2017年からアクチュアリー保険数理人をいれて、適切な保険料を 設定すべきだと申し上げてきた。類似の保険業法では、保険会社の取締役会は保険数理人を選任させる義務規定がある。フェニックスも同じビジ ネスモデルであり収支・リスク管理上必要。
民間が柔軟に保険料を改定する中で、フェニックス共済は創設以来一定である。同種保険のSBIリスタは新耐震限定、600万円給付で年間2.1万円に対して5,000円。
なぜ保険数理人による適切な保険料の算出やリスク管理を行わないのか。なぜ保険料率を改定してこなかったのか伺う。
(2)保険料の改善案~契約期間の短縮と築年数別保険料~
民間損保が10年で2割以上の保険料値上げや5年超の保険を停止する など、値上げを図ってきた中でフェニックスは5年・10年の長期割引を 継続するだけでなく、QUOカード販促など真逆の施策を行ってきた。
契約更新のたびに最新のリスク環境に即した料率に修正できるように すべきであり、本来は単年度契約を原則とすべきだが、一方で単体5,000円程度の保険を1年更新とすることへの事務費用割合の増加は考慮する 必要がある。
また、建物損失リスクは築年数によって異なるため、保険料も築年数で設定するのが妥当だが、フェニックス共済はまったく同一。更に、築年数を把握すらしていないので、震度に対する全壊・半壊の割合が想定できず、そもそも支払いリスク算定が困難である。
ソニー損保では、2022年10月改定以降、建物の築年数区分を「築5年 未満」から「築25年以上」の6区分で料率を設定し、1980年以前の建築は新規加入不可とした。
セゾン損保も35年超で新規不可とするなど、築古物件の火災保険への 新規加入が厳しくなっている。東京海上日動に至っては築年数1年ごと。
例えば、保険期間は3年、長期係数(2.85)は不適用、つまりは長期 割引なしで事務コストと引き受けリスクを減少させると共に、築年数別の保険料を設定すべきと考えるが、どうか。
(3)基金運用の改善案~兵庫県債への偏重と低利回り~
前払いの保険料、いわゆるフロートを運用して利回りを獲得するのは 保険ビジネスの根幹であり、これまで運用の改善を求めてきた。しかし、現状でも積立金総額134億円に対して、ほぼ債権で運用しており利回りは僅か0.38%。
さらに問題なのは、その債権が兵庫県発行で大半を占めていることだ。
再保険せず、兵庫県のみを対象にし、支払い上限もない高リスクな状況に加えて、支払い原資の運用先も兵庫県。巨大地震で兵庫県がフェニックス共済の肩代わりをする場合、兵庫県は利払いができるのか。
債権売却で現金化する必要性に迫られた場合、市場性が低く、発行体のリスクが上昇し、ジャンク化した兵庫県債は機関投資家はルール上買えず、安値で投げ売りせざるを得ないリスクもあるのでは。
債権、公社債、満期保有が前提。会計上損失にならないからリスクが 低いのではない。保証も運用も全て兵庫県内で完結しており、地域偏在・発行体の信用・市場性・インフレリスクなど多面的なリスク管理がなっていない。公社債以外のリターンが期待できるアセットクラスも組み入れるべきではないのか。
また、公社債なら最低でも兵庫県の地震と関係のない地域の公社債で 運用すべきではないのか。資金運用委員会のメンバーは運用経験のない 人間が大半であり、刷新を求めるが、どうか。
●企画部・県民生活部・部外局
1 脱計画行政~廃止、統合、頻度の減少と共同策定~
2 ミモザ企業の緩すぎる認定基準
3 コンパクトな県民会館~4割増床から減床へ転換~
全文
1 脱計画行政~廃止、統合、頻度の減少と共同策定~
2021年末で地方自治体に計画策定を課す法令上の規定は514条項にのぼり、この10年で約1.5倍に増えている。
広島県の調査では業務量が10計画に対して、専任3名、幹部会議113回、有識者会議49回、1,000ページ+会議資料1.4万ページと膨大。計画策定で仕事をやっている感は出るが、一番重要な事業の実行力に手が回らない。 成果が上がらない。
地方分権改革有識者会議でも議論されているが一向に改善されない。必要性が低下した計画等の廃止や、密接な関連性を有する諸計画との統合が十分になされていないこともあり、計画等の数が増加し、乱立してきている状況だ。
県議13年。計画・指針など拝見してきたが、本当にこの計画が必要なのかと疑問が多々あった。計画期間も老人福祉、介護保険、障害福祉計画などの計画は3年で、現状や対策が大きく変わるわけでもなく、5年や7年で策定 頻度を削減させればいいのでは。
どうしても策定せざるを得ない場合、計画等を極力簡素化・集約化すべきだ。必要性が低下した計画の廃止の意思決定はどうなっているのか。
地方創生総合戦略は第2期以降、自治体によっては統合して一体的に策定が可能。福祉分野では高齢者・障害者・児童の各計画を包括する「地域共生社会計画」のような統合計画に再編することも一案だ。更には、共同策定はガイドラインや手引きで約16%可能とされているが一向に進まない。共同 策定の課題は何か。
法的な義務付けなど、やむを得ない策定理由がある場合を除き、計画策定は原則しない方針を打ち出すべき。
また、計画期間の延長・改訂頻度の抑制で業務軽減をすべきと考えるが、どうか。
2 ミモザ企業の緩すぎる認定基準
ミモザ企業に認定されると、入札参加資格においての加点対象や信用保証協会の保証料率の割引。奨学金返済支援制度がミモザ企業は17年、フレッ シュミモザ企業は10年と、延長される要件の1つ。17年は企業負担と合わせて300万円程になるので、ミモザ企業の認定を受ける価値が向上した。
行政も議員もミモザ企業認定数の拡大にばかり意識が集中。しかし、認定のための自己評価シートを見ると、随分とふわふわしている。
テレワークやフレックスタイムなど、今やどこでもやっている制度。 ミモザ認定7割14項目達成だが、女性活躍で定量かつ認定にふさわしいと 判断できるのは項目7・8・9・11・12程度ではないのか。レベルが低く ないか。
認定後の悪化に対しては降格がないまま、一度認定を受けさえすれば恩恵を受け続けることはおかしくないでしょうか。業績悪化や代表・株主変更 などによる認定後の改悪リスクを防ぐための調査は行っているのか。
ミモザ企業の認定基準の引き上げと認定後の改悪対応について伺う。
3 コンパクトな県民会館~4割増床から減床へ転換~
1,000億円県庁を撤回し、コンパクトな県庁舎。我々も議場廃止や議会会議室のフリースペース化などを提案しており、同意する。現在、県庁舎ばかりに焦点が当たっているが、令和6年8月の県庁舎のあり方検討会資料に 基づき、令和5年時点の建築物価で計算すると1,000億円のうちの2割は 県民会館部分で約200億円、約4割も増床する計画だった。
コンパクトな県民会館も必要ではないのか。議事録を見る限り、委員は 利用者ばかりであり、当然議論はよりよく、より広くといった要望しか出ない。新設の神戸市施設や民間など、近隣代替施設も含めた需給の最適化が必要であり、増床ありきはおかしい。
会議室の稼働率は61.9%で16.4万人の利用があったが、これらの一定は 県庁・議会のフリースペースの貸し出しで対応が可能。また、県民会館の ギャラリーは令和5年で4つの総面積が約650㎡だが、利用率は 45.1%。 本当にこの規模で、この用途で、この立地に必要かは再検討が必要だ。
安価で貸し出しするギャラリーや会議室は、交通アクセスの犠牲はやむを得ないと考える。ミュージアムロード近辺への移設で県立美術館を中心と した芸術エリアの魅力向上や、高架下など、現地を前提とすべきではない。
コンパクトな県庁舎と同じく、コンパクトな県民会館についてはどのように考えるか。
●福祉部
1 介護・医療保険の不正請求対策と公益通報報奨制度の創設
(1)介護・医療保険の不正請求対策
(2)公益通報報奨制度の創設
全文
1 介護・医療保険の不正請求対策と公益通報報奨制度の創設
(1)介護・医療保険の不正請求対策
以前、税金で喰ってるのは政治家や行政職員だけじゃないぞ。公務員に向けられる厳しさの一部でも公的サービス、補助金を受けた個人・法人に反映させた制度設計、運用をしませんかという問題提起をした。
手取り増に向けて、社会保険料負担の軽減が注目を浴びている。社会 保険料の使途は医療費や介護費が膨大にあり、税金みたいなものの不正は許されず、断固とした処分が必要だ。
例えば、上場企業でホスピスを運営するサンウェルズ社が税金みたいなものである診療報酬の確定だけで約28億円を不正請求したと報じられて いる。
報告書によると、数秒から数分間の訪問しかしていないのに、約30分間の訪問と偽って診療報酬を請求。看護師1名で訪問したにもかかわらず、2名で訪問したと偽って複数人加算を請求する全42施設中41施設で 何らかの不正請求があった。
1年前から報道されているが、同社及び同種の例えば施設と訪問看護が同一のグループ会社は不正請求の可能性が高いと考えるが、調査は行ったのか。近畿厚生局と連携した合同指導・監査は適正にされているので しょうか。
不正請求の回収は国民健康保険法の改正により県による回収が可能と なりました。指導・監査権限を持つ県が一括で、広域的に・効率的に行うべきではないかと考える。
悪質な不正請求の場合は、原則、診療報酬及び介護報酬全額の返還、 加算金、指定取消等、詐欺罪で刑事告訴を徹底すべきだが、どうか。 これら不正請求対策について伺う。
(2)公益通報報奨制度の創設
記録と実態の違いを書類だけで外部が調査するのは限界がある。サン ウェルズ社では、社内の従業員や関係者から複数回にわたる内部通報が 行われていた。入居者から訪問看護の実態に関する意見書が提出され、 さらに看護師や他の職員からも不正を疑う内部通報が寄せられていていたが、取締役会は対応をしなかった。
おそらくは外部通報によって、共同通信が調査し、2024年9月に不正 請求疑惑を報じたが、同社は「事実無根」であると反論し、法的措置も 検討すると表明。どこかで見た光景ですね。
不正請求の端緒は、多くの場合は内部からの公益通報と聞く。一方で、内部通報者に対する探索や報復リスクは依然として存在し、委縮する。 経済的なインセンティブが必要であり、税金みたいなものの不正抑止、 調査する行政コストの削減にもつながる効率の良い投資だ。
そこで、兵庫県が診療報酬や介護報酬の不正請求について公益通報報奨制度を創設すべきと考えるが、どうか。
●まちづくり部
1 青木県営住宅PFIの課題~入札要件の妥当性~
(1)1社入札にとどまった要因
(2)1社代表、JV構成の最適化
(3)事業資金の合理化~前払い金拒否と活用地の引き渡し時期~
(4)売却価格25.5万円/㎡は市場価格より安価ではないか
(5)高規格・好立地な公営住宅は公平か
全文
1 青木県営住宅PFIの課題~入札要件の妥当性~
(1)1社入札にとどまった要因
サウンディング当初は大手を中心に建築5社、不動産3社などが意向を表明するも、結果は柄谷工務店1社入札。予定価格と同じ72億円となった。競争原理が働かず、事業費の妥当性や提案の比較ができない結果となった。問題は入札要件だと考える。
まず、入札書の公表から受付までたったの3か月。既存住宅を壊す、移転支援、県営住宅を建てる、利活用地のプランを設計から原価計算までやって3か月。まちづくり部は、この業務を3か月でできるのか。1社入札になった大きな要因だ。
また、短期見積もりによって企業にとっては保守的、県にとっては割高な金額になる要素をはらんでいたのではないか。1社しか対応できないように誘導されていたのではないかとすら思えてくる。
今回のPFIが1社入札にとどまった要因の分析と、入札書の公表から3か月と極めて短期間に設定した根拠、その影響を教えてください。
(2)1社代表、JV構成の最適化
入札説明書や実施方針などに対する企業側の質疑から課題が見えてくる。入札説明書には、代表単体企業は構成企業の債務すべてについて責任を 負うとある。総事業費72億円と1社で負担するには金額が大きく、時として大規模開発は工期遅延などで請負金額以上の金額にもなりうる。
企業側からすると債務負担の軽減、県側も単独代表に財務・事業遂行で依存するリスクをヘッジする上でも、なぜ共同代表を可能としなかったのか疑問が残る。
また、建築企業に関しては、企業側から工事費用の削減や参入障壁が上がることを理由に単独参加を求める要望があったにもかかわらず、JV2者か3者としています。事業リスクの大きい入札代表は単独としな がらも、よりリスク・事業の小さい建築企業は単独や分担施工を認めなかった合理性、根拠、その影響分析を教えてください。
(3)事業資金の合理化~前払い拒否と活用地の引き渡し時期~
実施方針に対する企業の質問では、通常の県発注工事と同様に事業費の前払い金を求める内容があり、メリットとして資金調達費用の縮減や応募者増加、応札額の低下、事業VFM向上を挙げ、私も納得します。
しかし、県はPFI民間資金の活用を理由に拒絶。一般に、資金調達コストは民間事業者より県の方が割安であり、PFIの趣旨は資金調達の多様化より、コスト削減と効率性向上、民間の創意工夫です。3年程度の事業期間では資金調達上の行政メリットはそれほどありません。なぜ、前払い金を認めなかったのか。多額の立替金の存在が入札障壁を高めたといえる。その判断が本PFIに与えた影響をどう考えるのか。
次に、活用地の引き渡し時期。県は事業用地内における全ての県営住宅整備業務が完了した後に一括して契約事業者に引渡す、としている。
インフレ時代を見据えた本会議質問でも指摘したが、値段は今が最安値。土地を寝かすのはもったいない、資材も毎年値上がりするので収益が悪化する。事業者が可能な限り前倒しを求めるのはもっともであり、県の固定資産税収入も遅れる。県の対応は合理性を欠くが、なぜこのような対応をしたのか、引き渡しの前倒しについても伺う。
(4)売却価格25.5万円/㎡は市場価格より安価ではないか
一方、事業者有利の面もある。活用地は不動産鑑定評価を最低価格とし、坪84万円、21.7億円で売却する予定。
青木・深江駅から徒歩6分程度の成形地で道路付けもいい土地が、この値段はありえない。最低でも1.5倍はすると思う。本物件から徒歩圏で、より駅に近い物件が廃屋撤去費用別で坪164万だった。
不動産鑑定=正しい価格ではない。REITはスポンサー企業との利益相反が問題となっている。外形上、第三者の不動産鑑定士に評価させ、適正価格とうたうが、鑑定士へのプレッシャーや複数の鑑定士に非公式に試算をさせ、希望価格を満たす数字を出した鑑定士に正式鑑定をするなどの 問題がある。
大阪IRでは市の誘導で不当に安い評価額を算定したとして、鑑定評価を行った不動産鑑定士の懲戒処分を大阪府不動産鑑定士協会に請求したという事案もあり、本物件の不動産鑑定会社もその対象である。
同物件の鑑定報告書では開発法の適用で想定分譲マンションの販売単価を坪200万円、平均専有面積69.4㎡、平均4,201万円としている。2022年の近隣エリアのマンションは坪260万円の販売実績。2024年は東灘区なら平均ではあるが坪386万円だった。
販売が令和12年頃の土地引き渡しから14か月以降後となると6年後の販売。インフレを加味すると坪200万円の想定は不可解なほどに割安だ。
また、取引事例比較法では、格差率で規模が大きいことを理由に評価額を10%マイナスとした。兵庫県下では100戸〜300戸のマンションは頻繁に販売されており、177戸程度のマンションは10%マイナスしないと参入企業が減るほど大規模ではない。ここ数年のこのエリアの供給マンションは20~30戸であり、むしろ希少性すらあるのではないか。
更には、埋蔵文化財包蔵地で4%、8,000万円分も価格が割り引かれる のであれば、県が立ち合い調査や試掘調査を事前に行い、教育委員会への届け出も前倒しで認めるなど、減価補正を避ける手立てはあるのではないか。
市場価格より大幅に安く売却するのはなぜか。活用地、つまり県民財産のより高い金額で適正に売却するための改善案を伺う。
(5)高規格・好立地な公営住宅は公平か
従来から税金を使って住む公営住宅は好立地、高規格は抑制的である べきだと申し上げてきた。民間分譲マンションは建築費高騰の価格転嫁を抑えるため、スペックダウンで対応している。高くて、狭くて、チープな内装や規格。結果、新築マンション離れともきく。
さて、サウンディングの意見では、「建物仕様を縛りすぎず、民間のノウハウを活かした工法等が採用できるようにしてほしい」と、もっともな意見があった。
しかし、要求水準への民間意見では、「廊下85cm以上の広すぎる幅員、洗面・脱衣の有効幅など、高価格の分譲マンションと比べても過大で割高な建築費につながる」との指摘に対し、県は拒絶。なぜ、税金で住んでいる人が豪華なマンションなのか。
販売価格を抑えるために分譲マンションは面積を狭めて販売している。東京カンテイ調査では、2016年に青木駅1キロ四方内の新築マンションは平均80㎡だったのが、2022年には62.5㎡と大幅に狭くなった。
なぜ、青木県営住宅のOタイプ(3LDK(大))はゆったり70㎡なのか。また、同じエリアで、立地はやや劣るブランズ東灘青木は73㎡で5,370万円の価格。自腹で住む県民は金利1.3%、35年ローンなら月16万円+固定資産税の支払いの一方、税金で住む人は家賃が4.9万円から12.9万円。
なぜ過剰な高規格、広すぎる面積を設定したのか。結果として、高額な事業費に至ったことをどう捉えているのか。
また、自腹で住んでいる納税者の公平・納得感について、どう考えているのか伺う。
●教育委員会
1 高校プールの廃止
2 制服費用の削減と全県共通制服の導入
(1)教育委員会による現状の把握について
(2)全県共通制服で制服費用の削減と新たな選択肢
全文
1 高校プールの廃止
高校施設の充実は図るべきだが、時代と共に不要となりつつある施設は廃止すべきだ。水難事故防止のために、子供たちに水泳を教える必要性は小中学校ではあれども、高校段階ではもはや不要。
県立高校のプール設置率は89.9%(116校/129校)。猛暑による熱中症リスクの高まり(暑さ指数WBGTが基準を超える日は授業中止)や突然の豪雨など天候要因もあり、夏季でもプールが使えない日が増えていることも利用率低下に拍車をかける。
プール1基の建て替えには約2億円、水光熱費や小規模改修、薬品等でプールの維持費は年間200万円という試算もある。プールの管理・運営の多くは、現場の教職員がプール清掃から毎日の水質検査、薬剤投入、安全監視まで多岐にわたるが、プール水を誤って流出させると賠償責任を負わされる。
低稼働率に高コスト、広大な面積を喰うプール。県立高校で設置後30年以上経過する高校は多数あり、劣化による改修費用の増加や長期の生徒数減少、更なる統廃合を見据えて判断する必要がある。
廃止したプール跡地は、今の時代に求められている新しい機能か民間へのリースなどで土地の資産価値向上にもつながると考える。
海外の事例も見たが、小学校で水泳を必修とする国が多いが、自校プールは稀で、ほとんどが外部施設の利用。
高校のプールは廃止を原則とし、どうしても必要なら小中学校も含めた近隣学校の借用や民間プール施設への委託をすべきと考えるが、どうか。
2 制服費用の削減と全県共通制服の導入
(1)教育委員会による現状の把握について
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの調査では、中高の保護者の約8割が「制服代が特に負担」を感じている。制服は学校ごとに決められるが、特注で発注量が少なく、原価がかさみやすい構造上の問題点がある。
公正取引委員会によると、制服の購入費用は約10年で平均5,000円も上昇し、地域間で倍以上開くなど価格差が大きい。要因として、指定販売店同士が制服の販売価格を協調するカルテルなど、制服価格の高止まりを招く要因だ。
事前のヒアリングで県立高校の制服単価について聞いたところ、学校長判断であり教育委員会は知らないとのこと。子育て世帯に負担、公取委から指摘されているのにそれでいいのか。文科省通知では制服の経済的負担が過重にならぬよう留意すること。学校の取組内容を把握するよう通知が出ているが、どのように対応したのか。
指定製造・販売店のカルテルや随意契約の問題、制服や体操服などの価格や学校間の違いも含めて、まずは教育委員会として調査すべきではないのか。
(2)全県共通制服で制服費用の削減と新たな選択肢
次に、制服費用削減について、全県で統一制服の導入や準制服、体操服などを県立高校で導入すべきだ。
生徒達には制服デザイン選択の自由や、性的マイノリティ対応、大量製造による制服費用の削減、20%台にとどまる女子スラックス採用率対策になる。更に安価な中古の制服バンクが規模の経済でしっかり機能するし、転校時の買い替え負担もなくなる。少子化により各学校の発注量は減少しかなく、小規模校単独はさらに苦しい。値上げは構造的。神戸市は市内共通の神戸標準制服をスタートさせた。
加えて、ざっくり紺のジャケット、白シャツを指定する準制服の導入も求める。さいたま市はユニクロを指定。ユニクロ制服は約1万2,000円と従来制服5万円に対して大幅に安い。安価なので成長に合わせて服を買い替えることができる。公取委の計量分析でも仕様の共通化や学校が販売価格の決定に関与することが重要と指摘。
授業料の削減に注目が集中しているが、これら制服・ジャージなどの費用負担も大きい。私の提案は、負担減と選択肢増に税金を使うのではなく、知恵を使うことで対応できる。
全県共通の制服や体操着の導入や準制服を全県で導入すべきと考えるが、見解を伺う。
●総括審査
1 県民割引と外国人料金の設定
2 嫌われる勇気とやめる勇気
3 手取りを増やせ~県版年収・対象の壁を撤去せよ~
4 金利上昇・インフレ下の資産管理~PF最適化と運用の高度化~
5 県立病院の経営改革
(1) 選定療養費のあり方~値上げと県民割の導入~
(2) 軽症者による救急車利用の有料化
(3) 保険適用外の点数増と消費税の徴収
(4) 自由診療への参入・収益部門の確保
6 県立高校入試の多様化
(1) 調査書不要の選抜枠
(2) 日本語指導を必要とする生徒枠
7 他国からの政治・世論介入~ディスインフォメーションへの備え~
全文
1 県民割引と外国人料金の設定
前回一斉改定からの物価上昇を考慮し、各部局から10%ほどの使用料の値上げが上程されている。がしかし、公営サービスは利用収入だけでは初期・ランニング費用を賄うことはできず、県民の税金を投入している。そもそもが低すぎるのであり、大幅に値上げをしたうえで、県民割で料金を調整すべき。
これまで私は、粒子線治療では外国人向けに料金を大幅値上げせよ、グランドニッコー淡路では逆に県民直前割で還元せよ、ピッコロシアターの大ホール22,000円は安すぎるなど申し上げてきた。
国民と外国人で料金を分ける事例は多くあり、例えば、トプカプ宮殿は国民1,200円に対し、外国人は7,000円。アンコールワットは国民無料で外国人は5,400円。日本の文化財入場料は平均 593 円に対し、世界平均は 1,891 円と安すぎる。
市民病院も市民とそれ以外で個室料を分ける事例は多い。現在の利用料は原価を割る水準であり、県外の人はその分を負担すべきだ。
様々な利用料・行政サービス料は、定価を大幅に引き上げた上で現行料金程度までの県民割を導入し、県民と県外・外国人で分ける必要があると考えるが、どうか。
2 嫌われる勇気とやめる勇気
2020年2月、私は本会議で井戸知事に嫌われる勇気を問いました。要旨は、日本は成長から成熟の時代。あれもこれもから、あれかこれか。事業や箱を廃止すると反対。あっちに遠慮、こっちに配慮が強いられる政治家。多選知事の最後の役割、それは嫌われ役、泥をかぶること。議会や県民に嫌われても反対されてもやりたいことは、という問いかけ。
初当選の齋藤知事には「1期目から、嫌われる勇気を発揮していただき、ゼロベースでどんどん改革を進めていただきたいと、エールを送る」と申しました。今回はやめる勇気を問う。
予算委員会では、様々なやめるべき事業を提案してきた。県民だよりひょうごの毎月発行をやめるで年1.3億円の支出削減、公営掲示場を3割やめるで1サイクル2.5億円の削減、高校プールをやめるで232億円の更新費用減、長田楠日尾線をやめるで数十億の収入、無駄な計画行政をやめるで仕事の負担減、フェニックス共済をやめるでテールリスク減、高規格・ 好立地な県営住宅をやめるで前田の支持率減など、有権者には嫌われる施策も多々。改革派知事をうたうなら、これら事業をやめる勇気を持つべきだ。
再選後、知事は議会との対話を図る、政策を前に進めるとよくおっしゃる。その、一番わかりやすい対話の形は今回の本会議や予算委員会での各議員の政策を反映した予算修正案を知事案で提出することではないか。知事のやめる勇気を問う。
3 手取りを増やせ~県版年収・対象の壁を撤去せよ~
年収の壁が国民的な関心を呼んでいる。他人事ではなく、県レベルでも存在する。
2020年本会議で所得制限の最適化を提起した。不妊治療や妊孕性温存の所得制限が400万円でありながら、持ち家耐震改修の所得制限は1,200万円というちぐはぐさ。その後、愚かな所得制限はなくなった。
2021年本会議では、ひょうご保育料軽減や不妊治療ペア検査助成などの所得制限の全廃を提言。
2023年予算委員会では、県営住宅の所得・入居要件。添付のとおり、夫婦で合算80歳までなら年収503万円以下で入居できるのに、お金のかかる多子531万円、子育て大変な父子・母子436万円だった。翌年是正されたが、生活の実態にあった年収の設定では全くなかった。
全県的な年収の壁の最適化を問題提起した以降もこのように個別に指摘しないと変わらない。多くはタコつぼで起案、国の同種の政策に合わせるなど、県民目線からは乖離した設定だ。
今でも、家賃や債務保証料低廉化への支援は政令月収が15.8万円以下、多子25.9万円以下というのは今の物価で合理的ですか。
添付資料のとおり、私立専修学校の授業料支援では、県は年収300万円未満に2/3支給に対し、年収380万円未満は1/3支給と大きな壁。更に県立大学は所得制限無しで金持ちはタダ。大きな壁。
対象の壁もある。新婚・子育て世帯向けの優先入居は18歳未満が対象。短大や専門含む高等教育機関への進学率は87.3%と養育費用がかかる現代、20歳まで拡大すべきではないか。
奨学金返済支援は県・教職員や警察などの公務員も対象にしてはどうですか、東京都ですら半額支援を開始。
かつて私立高校の授業料補助は大阪や岡山など隣接県のみが対象で、奈良や滋賀への通学は対象外となっていた。私の提案で翌年拡大されたが、今度は不妊治療で隣接府県に縛る対象の壁。我々は関西広域連合まで対象拡大を求めています。
年収の壁は他人事、国マターではありません。兵庫県にも年収の壁、そして対象の壁があり、少数かもしれないが制度の狭間で苦しむ人々に光を当てるため、壁の撤去を求めるが、どうか。
4 金利上昇・インフレ下の資産管理~PF最適化と運用の高度化~
2023年本会議ではインフレ時代の資産運用について問題提起した。その中で、現預金偏重はだめ。一括運用を外郭団体も含めて行うべき。資金管理委員会は実務プロを採用し、資金運用方針はアセットクラスを緩和すべき という提案を行った。その後わずか1年半で物価上昇が3%、10年物国債は0.7→1.57%と16年ぶりの水準をつけた。
市場金利が上昇すると、既存債券の評価額は下落する。2022年に米国金利が急上昇した際はBloomberg地方債指数は年初来-12%下落。日銀は債券の評価損を13兆円計上したが、株式評価益33兆円でPFが機能した。
評価損は表面化しないが、仮に債券以外のアセットクラスを組み入れしていた場合はどうだ。債券買い替えも行うべきではないのか。どのように柔軟かつ、効率的な運用を行ったのか、お伺いします。
また、外郭団体も含めた複数の基金を個別運用ではなく、一体的に運用すべきと提案した。フェニックス共済は、134億円の積み立て資産に対して、運用益は5,145万円、運用利回りは僅か0.38%。更に、兵庫地域の地震保証をしながら、その資金の運用先が兵庫県債一辺倒はリスク管理がなっていない。関連公社等の資金運用に関して指導・助言はどのように行ってきたのか、お伺いします。
また、指針の運用対象の緩和。私の質問後に開催された、資金管理委員会では「金利のある世界になった今、指針の運用対象を緩和して、収益性を高めてもいいのでは」やフェニックス共済の運用議事録でも「県が購入実績を示さないと外郭団体では対応できない」とある。
かつて、朝来市や名寄市が外債や仕組み債で大失敗した事例は承知しているが、運用指針や透明性の向上、ガバナンス強化で対策すればいい。更には、実務者不足と指摘した委員のメンバーも従来から変わっていない。例えば、人材派遣型ふるさと納税で第一生命からマルチアセットクラスの ポートフォリオマネージャー派遣や国東市財務管理専門委員の益戸氏を委員とし、調達・運用・ガバナンスの改善を進めるべきと考えるが、どうか。
5 県立病院の経営改革
公立病院は政策医療もやってるし赤字で当たり前。という価値観で収益を上げるべきところ、支出を抑えるべきところで判断が弱くなっていないか。10億円の赤字に苦しむ粒子線センターには黒字時代から価格設定や集患戦略に警鐘を鳴らし、撤退を申し上げてきた。
県立病院の累積欠損金は496億円。収支改善に向けて4点の問題提起を行う。
(1)選定療養費のあり方~値上げと県民割の導入~
公定価格から離れて、病院独自に値段設定ができるのが選定療養費。紹介状なしで大病院を受診する初診時、緊急性がない患者の夜間・休日受診には時間外など設定できる。
2022年には、「紹介受診重点医療機関」も選定療養費の義務対象になった。法定の最低が7,000円であり、県立病院も一律最低料金。日本赤十字社医療センターは11,000円で、慶応義塾大学病院は9,900円。収支改善と役割明確化のためにも、県立病院はもっと値上げをすべきだ。
健康福祉常任委員会では県民割引を創設したうえで、差額ベッド代をもっと上げるべきと申し上げた。極端な例では、東京慈恵会病院の個室最高額は1日14万円、NTT関東病院で12.6万円、神戸市立病院では市民と市民以外で料金を分けている。県民の税金を投入して赤字を補填する。なぜ県外・外国人と同じ料金を払わなければならないのか、納得がいかない。
選定療養費の値上げと差額ベッド代は県民割の導入を求めるが、どうか。
(2)軽症者による救急車利用の有料化
軽症者による安易な救急車の利用で、医療資源、税金が浪費されている。救急出動件数は700万回を突破し、その半数が救急車不要な軽症者とされている。東京消防庁の救急事業費285億円を、年間の出動回数63万回で割ると1回45,000円の費用。受け入れ病院の費用、当直対応の負担は別になる。海外では5万円前後取られる国が多い。
県立病院の救急車搬送数は令和5年で34,317件で、4.5万円とすると15.4億円。その半分の7億円以上の血税や医療資源が浪費されている。
さらに、救急車の現場到着時間は、20年前の6.3分から2022年は10.3分と大幅に延びた。真に必要な重症患者への対応が遅れ、救える命が救えない状況にもなる。#7119もあるが、「血圧図って欲しい」「タクシー代わりに」みたいな人には抑止にならない。
そこで、救急車を利用しても、軽症で外来受診が終わった患者に対して選定療養費を徴収する事例がでてきた。
松阪市は2024年から「初診時選定療養費」を準用した仕組みで7,700円。有料化後1か月で救急出動件数が約22%減少するなど、コンビニ受診の削減に成功。自治体主導は全国初で、都道府県初は茨城県が続きます。仮に1.7万回の軽症患者に有料化で利用が3割減、1万円の選定療養費なら、1.2億円の増収と現場負担の減少、市町消防部門で2.3億円分の負担減という試算になる。
そこで、全ての県立病院で軽症者に対する救急車の有料化を図るべきだ。
(3)保険適用外の点数増と消費税の徴収
公的医療保険は「1点=10円」の全国一律。しかし、保険外では、自由に単価を決めることができます。
例えば、事故で使う自賠責や保険未加入者、外国人が使うときは10円ではなく、20円以上取る病院もある。更に、保険では徴収できない消費税も徴収可能で、控除対象外消費税問題は自由診療では解消可能だ。
県立病院は無保険者、外国人を1点12円、自賠責保険20円で算定し、消費税は徴収せず。非常に安い原価割れ料金だ。例えば、筑波大学附属や国立がん研究センター病院は、保険未加入者30円、消費税も加算している。県の2.75倍の価格。県民の税金で赤字補填されている県立病院が義務化された保険に加入しないフリーライダーや外国人に甘くないか。ニュー ヨークで虫垂炎で日本人が1日入院すると112万円取られます。県立病院は平均で約11万円。3倍取ってもまだ安い。外国人の受診数はまだ少なくとも、在留外国人の数は昨年対比5%増の358万人で今後もこのトレンドは続くため、体制整備が必要だ。
未保険者や外国人、自賠責保険などは30円、消費税を徴収も行うなど、診療報酬増収に向けた取組を伺う。
(4)自由診療への参入・収益部門の確保
保険外の自由診療は広告宣伝費がいらず、既存の医療資源・設備、集患力を転用できるので、収益性向上が期待でき強化すべきだ。県立こども病院で、赤ちゃんの頭外来なども行われているが、民間提供が少ない先導型だけでなく収益型も強化すべき。
広畑病院の視察時には、民間時代に収益部門だった人間ドックや透析などが県立移行に伴い、廃止されられたとのこと。このような判断では赤字体質は治らない。
以前も、医療サービス以外に収益部門を持つべきだ。ホスピスはどうかと問題提起した。介護施設への患者紹介も収益性・業界是正・患者ニーズから期待が持てる。1人当たりの紹介料の平均金額は21.5万円、患者も自ら最適な施設を見つけることは難しい。横行する紹介ビジネスを適正な紹介料金で抑止し、病院・患者・看護施設・納税者の4者両得。
例えば、国立埼玉病院では保険で利用しているレーザー機器、重症、難治性の皮膚疾患治療を活用して、ピコスポット、シワなど自由診療の美容治療に参入。慶応義塾は加えて、がんゲノム外来やニューロモデレーションなども行っている。PETやMRIなど既存施設を活用した全身がん検診なども検討願いたい。
この話をすると行政は民業圧迫を気にするが、高年収の開業医・美容外科の豪奢な生活に対して、政策医療で赤字に苦しむ公立病院がなぜ配慮せねばならないのか。
これらを踏まえ、利益が期待できる自由診療・収益部門を強化すべきと考えるが、どうか。
6 県立高校入試の多様化
私立高校の無償化と通信制への進学率上昇により、県立高校は生徒獲得への危機感を持ち、改革を進める必要がある。先に無償化した大阪では私立人気が高まり、過去最低倍率に衝撃が走りました。
兵庫県公立高校受検者数は平成26年度でのべ約4.2万人が、10年後の令和6年度では、のべ約3.6万人と約14%減少した。更なる発展的統合が必要だが、入試の多様化による県立高校の競争力向上も提案する。
兵庫県は愛知県と並び、数少ない複数併願可能な都道府県であることは 評価する。一方で、迎山議員が指摘したように、内申書の割合が他の都道府県より高く、公平性や生徒に対する過度の抑圧など課題があり、内申書の配分は是正すべきだ。
(1)調査書不要の選抜枠
推薦入試など学力検査によらない入学者選抜があるのならば、調査書によらない選抜もあっていいはずだ。
山梨県では、今年からすべての県立高校で調査書不要の入試枠を設定している。不登校やヤングケアラー、病気などを含め長期欠席者の多くは通信制や私立などを志望する一方、調査書を重視する公立全日制の志望は少なく、フリースクールなどの関係者から「学力中心の選考」を求める声が挙がっていたとのことで、2026年度から島根も続く。
兵庫県の入試方式では生徒ニーズに対応しておらず、受検者を獲得できないのではないか。
小中学校で不登校の児童・生徒は、2022年度には29万9,048人と過去最多を突破。通信に在籍する生徒は、公私併せて2005年に18.3万人から2024年に前年比9.5%増の29万人と増加し、公立普通科の需要を喰っている。不登校や特性を持つ子供たちを評価するためにも、調査書不要の特別枠選抜を設けるべきだ。
無償化で私立との競争も激しくなる中で、全県立高校への調査書不要の選抜枠導入を求めるが、どうか。
(2)日本語指導を必要とする生徒枠
文部科学省は2024年度以降の公立高校の入試において、外国籍を対象とした特別枠の設定や、試験問題にルビなどの配慮を通知した。
日本語指導が必要な外国籍の児童生徒は、2021年の調査で全国4.7万人と10年ほどで1.8倍に増加。加えて、日本国籍でも親の仕事で外国歴が長く、日常会話はできるが入試に関係するような学習用語を理解できない生徒も増加。
東京都教育委員会は日本国籍も対象とし、入国後の在日期間が6年以内は「ルビ振り」、3年以内は「ルビ振り・辞書持込み・時間延長」と柔軟に対応。兵庫県は定員18名に対し、志望者29名と1.6倍。2年前に質問した時は、募集定員を満たさないことが多いと答弁された。
今後は定員数の拡大と共に、外国籍だけでなく、日本国籍も対象とし、入国後の在日期間も3年以内から拡大すべきである。
生徒目線・公立高校の受検者獲得の両面から、定員増や対象拡大を図るべきと考えるが、どうか。
7 他国からの政治・世論介入~ディスインフォメーションへの備え~
悪意を持ち、真偽を織り交ぜて世論を誘導し、社会に害をなす情報のディスインフォメーション。現代では、SNSで増幅され、非常に急速かつ広範囲に拡散し、その脅威が増している。
2馬力選挙が問題となっているが、私が更に懸念するのは、他国による政治家・選挙、世論への介入だ。個人ではなく、国。資金量や人的リソースは10万馬力。情報操作によって外国勢力が民主主義に干渉し、広範な影響工作、社会の信頼や統合の毀損を企図する事例が頻発している。
アメリカ大統領選挙ではロシア政府が大規模な干渉を行ったとされ、数千の偽アカウントやボットを動員し、FacebookやTwitter上で政治的分断を煽る投稿や政治広告を大量配信しました。
沖縄県知事選では、知事を貶めたり、反基地に関する動画サイトが作成され、中国・ロシアによる可能性もあるとの指摘。
現代の戦争は物理的な武器のみならず、サイバー攻撃や情報工作など複数の手段を組み合わせるハイブリッド戦が主流。
私は以前、台湾有事を見据えた警察資機材の強化やSATを提言したが、ミサイル一発より政治・世論介入の方がはるかに容易で安価。サイバー安全保障の対応能力向上に向けた有識者会議では、「国家主体のサイバー攻撃や 他国の選挙干渉、偽情報拡散などハイブリッド戦が平時から展開されている」とし、相対的に露見するリスクが低く、攻撃者側が優位にあるサイバー攻撃の脅威は急速に高まっているとした。
プラットフォーマー規制や外国勢力の介入に事後制裁など各国で取り組んでいるが、シンガポールで採用されている虚偽情報規制も参考となる。
加えて、シンガポールは、国会議員など政治的重要人物が、外国から影響を受ける可能性があると考えられる寄付や、ボランティアやメンバーとして関わった人々の所属等について公表を求められた場合、開示する義務を負う。
政治的グルーミング、資金提供や代理勢力の支援も懸念です。
日本は国家安全保障戦略において、「外国による偽情報等に関する情報の集約・分析、対外発信の強化、政府外の機関との連携の強化等のための新たな体制を政府内に整備する。」に留まる。
兵庫県内において、これまで外国政府が絡んだ、ディスインフォメーション等の情報工作はあったのか。これら脅威に対して、兵庫県警の体制は十分と考えるのか伺う。