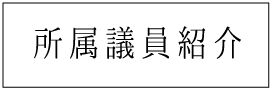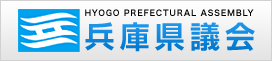概要 / 代表・一般質問 / 議案に対する態度と考え方 / 意見書案 / 提案説明 / 討論
質 問 日:令和7年2月27日(木)
質 問 者:中田 英一(ひょうご県民連合)
質問形式:一括

1 選挙や政治活動に関連する虚偽情報への対応について
兵庫県を中心に、選挙や政治活動に関連する虚偽情報(=デマ)が、主にインターネット上で拡散し、議会活動や選挙に甚大な被害が生じる社会問題となっている。
これを受けて、県警本部長が特定のインフルエンサーによるデマを否定し、Xの公式アカウントでもデマや誹謗中傷に対して「確たる証拠がないのに、推測・臆測で人を傷つけるような書き込みをするのはやめましょう」と呼びかけ、「例え、それが正義感に基づくものであったとしても、刑事上・民事上の責任が生じる場合があります」と警告している。
これらについては大きく評価する一方で、デマ等の投稿は一向に止まる気配を見せず、更には県内自治体の市議が、知事選において県警が特定の候補を応援するよう通達を出していたとのデマを拡散し、当該市議会で政治倫理審査会が設置されるに至っているなど、社会の混乱は広がるばかりである。
国では情報流通プラットフォーム対処法が公布されこの春施行される見通しであるが、この法律はあくまでインターネット上の誹謗中傷等に対処するため運用事業者へ申告のあった有害情報への迅速な対応等を義務付けるもので、虚偽情報発信者を処罰するものとはなっておらず、削除されることも厭わず悪意を持って投稿した虚偽情報が多数の利用者によって拡散される、今本県で起きているような事象を抜本的に食い止めることはできない。
そもそもこうした行為は表現の自由で保護される領域を越えて他者の権利を侵害する犯罪に該当し、現行法に基づいて、行政警察活動である警告から捜査・送検などの司法警察活動に踏み出す必要があるのではないかと考えるが、先の警告にもある刑事上の責任が追及された事案は聞こえてこない。
関連すると思われる罪名を具体的に列挙すると、名誉棄損罪(刑法230条)、信用棄損罪(刑法233条)、偽計業務妨害罪(刑法233条)、虚偽事実公表罪(公職選挙法第235条第2項)等がある。
このうち、名誉棄損罪は保護法益が「個人の名誉」とされるため、親告罪、すなわち被害者からの告訴がないと起訴できないこととなっている。自身や家族の名誉が棄損され深く傷ついている中で、犯罪者に立ち向かう気力が出ないことも想定されるが、被害者は救済されないまま被害が拡大するという不条理のなかにある。
今回は、偽計業務妨害罪(刑法233条)に絞って伺う。
偽計業務妨害罪の構成要件は、①「虚偽の風説を流布し」②「人の業務を妨害した」ことであり、これに対する故意、すなわち罪を犯す意思があれば原則として本罪が成立する。
例えば、特定のインフルエンサーが、ある議員が元県民局長の妻のメールを偽装して送った「でっちあげ」であると発信したことは、テレビ取材に対して県庁職員も否定している「虚偽の風説を流布し」たものであり、これを信じた者によって特定の議員自身や事務所に抗議や苦情を発生させたことが「人の業務を妨害した」と評価できることは自明であると考える。
仮に、これを当事者が「勘違いであった」と主張した場合、故意が認められず犯罪が成立しないということになるのか。名誉棄損罪では、昭和44年6月25日の最高裁判決で、故意について「真実であると信じたことに相当の理由が必要である」とし、偽計業務妨害罪では、令和4年10月18日の大津地裁において、コンビニで店員がせき払いをしたことからコロナ感染者と断定し、SNSに書き込んだため、当該店員が勤務を減らしたり、店への問い合わせに関する電話対応が増加した事例で、偽計業務妨害罪の成立を認めた裁判例がある。
虚偽の情報を裏付けもなく拡散し、議員の業務を妨害し、そのすべてについて故意が認められることは、こうした判例に照らしても何ら齟齬がないように思えるがどうか。
この間私が話を聞いた有権者の多くは「何が本当か分からない」と口にされ、その多くはデマと事実が混同された状況が背景にあると感じた。民主主義制度の根幹をなす議会・議員活動や選挙における有権者の判断が歪められるようなデマがまかり通ってしまう状況は異常だし、それが情報リテラシーへの呼びかけや、現行法での警察活動では限界があるというのであれば、選挙管理委員会が総務省へ改正を要望したように、現行法での限界を伝え、ルール改正の議論をしなければならないと考えることから、県警として現状の認識および偽計業務妨害罪についての見解を伺う。
2 セーフティステーション活動の推進強化について
兵庫県は、本年、現場執行力を強化し、各種事案対応をスムーズに行うため、54ヵ所の1人勤務交番を廃止し、近隣の交番に集約した。人員不足の中、現場執行力等が強化されることは評価するものの、交番という近隣住民の安心のよりどころとしての機能は低下することが懸念される。
特に子どもが犯罪に巻き込まれることを防止する観点から、「こども110番の家制度」があるが、近年はその登録数は大幅に減少し、実際に活用された事例も少なくなっている。一方で、街中に多く存在し、営業時間の長いコンビニエンスストアでは、「安全・安心なまちづくりに協力」することと「青少年環境の健全化への取組」の2つを柱とするセーフティステーション活動に取り組まれているが、店舗によって取組に対する認識に格差があるように思う。
近年では、特殊詐欺などでコンビニのATMや電子マネーカードが利用されることから、詐欺被害防止対策として、地元の警察署でも署長が自ら出向いてコンビニと連携をとるなど、関係性は深まっている。
子どもや地域住民が気軽に立ち寄るコンビニが、犯罪に巻き込まれそうになったときの駆け込み場所であるとの認識が高まり、店側への防犯装備の充実も含め警察との連携をさらに深めることができれば、更なる県民の安心に資することができるのではないか。
セーフティステーション活動を推進し、積極的に周知すべきと考えるが、県警としての所見を伺う。
3 違法駐停車対策について
関西大阪万博の開催が目の前に迫り、神戸空港の国際化も近づくなか、兵庫県がDCやフィールドパビリオンなど観光客の呼び込みを強化しているが、すでに週末や特定時期については、観光バスや一般車両による駐車違反車両を主な原因として、深刻な渋滞が発生するなど、受入れ体制が不十分であるように感じる。
例えば、神戸市では港湾付近の主要な観光地を連結バスで結ぶ「ポートループ」が運行されているが、バス優先レーン等やバス停前後の路上駐車によって円滑な交通が妨げられている。
フラワーロードに設置されているバス優先レーン等は、塗装が薄くなったまま放置されていて認識しづらいこともあってか、沿道の店舗利用者などによる違法な駐停車が常態化しており、事実上バスは走行できない状態となっている。
また、バス停については、前後10メートル駐停車禁止(道路交通法第44条)となっているが、その直近前後に駐車車両があれば、「ポートループ」はおよそ2台分の長さの連結バスであるので、バス停の枠内に停めることができず、危険が生じる原因となっている。もし、ぎりぎり停車できたとしても、後方に車両が駐車されていると、後方から進行してきた車両がバスの発車を認識しづらく、バスの発進妨害(道路交通法31条の2)となる危険もはらんでいる。
さらに、主要駅前ロータリーやその付近の路上において、送迎や集配等のために駐停車する違法車両によっても円滑な交通が阻害されるケースが散見される 。
観光政策は直接的な県警の業務ではないものの、駐車違反やこれに起因する交通事故は、交通の安全と円滑の確保の観点から無視することはできないし、観光客の増加により事故等の危険が増大することも予想されることから、違法駐停車対策について、地元市町との連携を含めて、県警の所見を伺う。
4 教員不足への対応について
兵庫県教育委員会が発表した令和6年5月1日時点の教員不足は、小学校で102人、中学校で 51人、高校で30人、特別支援学校で22人の合計205人となり、前年の164人から20%も増加している。
県として次世代・若者支援を打ち出すのであれば、1.8%にしか恩恵のない県立大無償化よりも先に、足元にある義務教育等の大きな課題である教員不足への対応が必要ではないか。
教員不足の要因は様々で、根本には志願者の減少があると考えられるが、年度途中の産休・育休や増加する病欠も挙げられる。年度当初で定数を満たしても病欠によって急な欠員が生じると、その分の仕事が残った教職員の肩にのしかかり、更なる病欠者を出してしまうという悪循環に陥る危険性もはらんでいる。
産休や育休については、ある程度予測できることから、先読み加配制度が設けられているが、病欠はそうなっていないことから、産休・育休と同様に年度当初から先読みした加配をつけるなどの対応策が必要だと考える。
また、昨年から、退職する教員を対象に「再任用短時間勤務制」が設けられたが、短時間勤務を希望される再任用教員の勤務時間が、複数人合わせてちょうど正規教員1人分の時間数にならないと利用できないため、マッチングがうまくいかず実際の運用に至っていない事例が多数あり、結果的に年度当初の定数割れに至っている状況もあると聞く。
退職される教員の知見は若手職員に引き継ぐべき財産であるし、教員不足の状況で、引き続き教職を担ってくれる可能性の高い方々に、現場を離れてしまう前に短時間でも残ってもらうことが重要であり、再任用短時間勤務制の枠外での年度当初からの加配という方法も含めた柔軟な対応が求められる。
さらに、こうした状況のなかで、教員や関係者から数件相談を受けたのが、婚姻による転居を理由とする市町を越える異動の希望が、受け入れ先の教育委員会が了承していても叶えられず、長距離通勤が過大な負担となり退職を考えているとの声である。
市町を越える異動は教育事務所が調整を担っているが、転出先の教育委員会が採用したいと考えても、転出元の市町の教員数が減少することなどを考慮して認められるケースが少ないとのことである。
当然、年度途中での異動や、教員の世代バランスが著しく損なわれるような場合、本人の能力や受け入れ先の事情が許さないケースまで誰でも異動を認めるべきとは言わないが、そこに何ら支障のないケースまで異動が認められず、優秀で経験豊富な教員が退職してしまう現状は改善すべきであり、教員不足の現状を踏まえればなおさらであると考える。
以上を踏まえ、教員不足を解消するため柔軟にスピード感ある取り組みを求めるが、所見を伺う。
5 産業用地の確保について
コロナや、円安、日本における労働者賃金の低迷などにより、国内への生産拠点回帰や外国企業の日本進出が加速し、産業用地の供給が需要に追い付かない状況が続いた。
県内でも、これまで売れ残っていた産業用地が売れた反面、用地買収や、農地転用、用途変更および開発許可等の行政手続を終えてから造成工事と、建設に着手するまでに長期間(3年から6年。5年以上とも言われている)かかることから、需要に見合うタイムリーな産業用地の供給はできていない。
この問題を解消するためには、短期間で使用可能な産業用地のストックを持っておくことが重要であるが、先の県政改革調査特別委員会でも指摘したように、今から兵庫県として企業庁等で産業団地を開発することは現実的でないとすれば、県として県下自治体や民間デベロッパーの取組について支援する必要があると考える。
経済産業省が、2023年に自治体と「地域経済産業活性化対策調査」を実施し、産業用地の候補を調査した中では、課題として特に①土地利用規制、②地権者交渉、③インフラ整備、④ノウハウ不足が挙げられている。
このうち①土地利用規制については、現在も柔軟な活用に向けて取り組んでいるし、②地権者交渉や、④産業団地開発のノウハウについては企業庁含め知見の蓄積があり、サポート体制を構築できる。③造成工事などのインフラ整備は多額の費用がかかり、買い手が見えてからでないと着手しにくいことから、補助制度を設けることも考えられる。
県では産業立地条例を制定し、立地支援の補助制度を設けているが、産業用地のストックがない状況ではそもそも企業は立地場所の選択肢が少なく、効果が充分に発揮されないように思える。
県として、全庁横断的なバックアップ体制を構築し、ストックを増やしていく必要があると考えるが、当局の所見を伺う。
6 「はばタンPay+」の電子地域通貨化について
これまで家計応援等を目的に、「はばタンPay+」を合計4回実施してきた。デジタルデバイド対策など課題はあるものの、一定の評価も得て県民にも一定周知されてきたように感じる。
ただ、単発の発行を繰り返し、その都度に生じる事務経費や委託料、手数料などのコストがかさんでおり、今後定期的に実施するのであれば、こうした経費を抑えるために、電子地域通貨として常用化することを検討してはどうか。
当初は、コロナや物価高騰で苦しむ家計の緊急支援として創設されたものであったが、この間取り組んだおかげで、県民への認知度も高まっており、ゼロから創設する場合に比べて親しみがありスムーズな導入が期待される。
また、電子地域通貨とすることで、コスト削減だけでなく、他の施策から生じる補助金などへの活用で一元化を図れることや、地域活性化に向けた公民連携の一環として、県下金融機関にも協力を得られることが想定されるうえに、他自治体の事例を参考にすれば、ふるさと納税の返礼品としても活用等も考えられる。
さらに、県下自治体がそれぞれにシステム開発し提供するサービス、例えば健康増進のために運動することでポイントを付与するようなサービスについて、プラットフォームとして「はばタンPay+」が活用できるようになれば、自治体の負担も軽減できると考えられる。
「はばタンPay+」のこれまでの振り返りと今後の在り方について、所見を伺う。
7 県立都市公園の活性化について
地元三田市にある県立有馬富士公園は、森林散策、家族連れに人気の広大な芝生広場、子供に大人気の遊具が集積する遊びの王国などを中心に週末は大勢の人で賑わいを見せるだけでなく、地域の各種イベント会場としても大いに活躍している。
しかし、人口減少が進む地方においては、さらに多くの県民が主体的に公園を活用し、例えば、平日は利用されていないフェンスで囲われた臨時駐車場をドッグランに活用するといった試みや、地域の方が園内で地場産品や加工した飲食物を販売する試みなど、交流や情報発信の場を作り上げていくことが重要になると考える。
これまで、広大な森林等を有する県立都市公園では、どうしても森林等の管理に主眼が向いており、地域の活性化や住民活動の場としての利用は、その範囲内に制限されることが多かったように思うが、令和4年度から実施された県立都市公園のあり方検討会において「民間活力の導入による活性化」がメインテーマの一つとして盛り込まれ、その中にある「管理運営協議会等の拡充」という部分について期待している。
検討会のまとめでも、公園の管理運営方針を協議する場に、より幅広い市民が参画できるようにとの工夫が込められているが、こうした仕組みの実装にむけて、具体的にどのように進め、公園の活用を行っていこうと考えているのか、当局の所見を伺う。
8 サンライフ三田の入居率向上について
公営住宅の収入基準を超える中堅所得者に居住環境が良好な住宅を供給するため、県では特定公共賃貸住宅をサンライフとブランド化して整備し、現在11ヵ所に全304戸を提供しているが、全体の入居率は50%程度と、有効活用されているとはいえない状況が続いている。
一昨年の決算特別委員会では、サンライフは中堅所得者向け住宅であるため、主たるターゲットが異なる一般の県営住宅と同じ募集方法、すなわち県営住宅募集のホームページや冊子に掲載するだけでは需要者に届きにくい点を指摘し、「民間ポータルサイトの活用などによる中堅所得者に的を絞った広報強化であるとか、社宅利用など目的外使用の拡充といったことも行いながら、入居率の向上を図っていく。」との力強い答弁があった。
しかし、96戸を備えるサンライフ三田は、既に活用されているグループホームを含めても空き家が50%以上に達しており、集合ポストはその大半が閉ざされているし、共用部の除草活動など自治会の活動にも支障をきたしているなど、居住環境の低下が待ったなしの状況である。
以前も指摘したが、サンライフ三田は、周辺の賃貸マンション物件と比較しても割高ではなく、広告方法次第で更なる入居が見込めると考えられることから、答弁にもあった民間ポータルサイトなど主なターゲットの目に触れやすい広告等の取組で改善できる可能性があると考えるが、未だ実行されていない。
また、賃貸条件が悪いのであれば賃料を下げたり、周辺で需要の高まりが予測される高齢者の住まいを確保すべく、サービス付き高齢者住宅等への活用を検討したり、あらゆる可能性を模索して入居率の向上、すなわち県有財産の利活用と県民福祉の向上を推進すべきであると考えるが、サンライフの入居率向上に向けた当局の取組と所見を再度伺う。