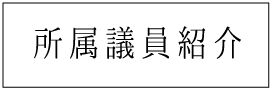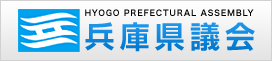概要 / 代表・一般質問 / 議案に対する態度と考え方
質 問 日:令和6年6月10日(月)
質 問 者:前田 ともき 議員
質問方式: 一問一答
1 高校生の就職改革 (教 委)
(1)就職のミスマッチ・早期離職の防止
空前の人手不足により、昨年の求人倍率はバブル期を超える過去最高の3・5倍。就職氷河期世代にはうらやましい。しかし、早期離職が問題だ。高卒の3年内離職率37.0%に対して大卒の3年内離職率は32.3%と高卒の方5%高い。
また、リクルートワークスの調査では高校卒就職者の4人に1人が、 卒業後に入社した会社について、10点中「0点」と評価し、約半数が4点以下と回答するなど、就職先に対する満足度は低い。離職率が高く、評価が低いのは独自の就職規制によるミスマッチにも要因があると考える。
高校生が就職で応募できるのは1人1社に限定され、ハローワーク経由での求人情報は文字情報が中心。内定辞退は不可、書類のみの選考は不可、指定校求人の3倍ルールなど、生徒・企業側にがんじがらめ。これらの 慣習・規制は50年前から続き、100万人が就職する時代に効率化だけで作られたルールであり、アップデートされるべきだ。
例えば、20年前の僕の就活ですらリクナビなどネットで検索し、企業の様々な情報に触れ、職種や応募先のイメージを膨らませ、書類作成や面接の過程で学び・キャリアプランを養った。しかし、ハローワーク経由の 求人情報は文字情報がほとんどで、しかも教師しか見ることができない。求人を紹介する教員のフィルターが発生し、生徒に届く就職先や職種の情報量が少なくなったり、選択肢の幅が狭くなると いった課題がある。
また、就職が多い商業・工業科はノウハウが豊富だが、普通科や就職が少ない高校では進路指導担当教員の経験・ノウハウが不足していること から、ハローワークに常駐し、高校生の就職支援を行う就職支援ナビ ゲーターの活用や、オンラインでの就職相談を実施し、就職指導力の強化と教員の負担軽減の両立を目指すべきだ。
さらに、生徒が既存の仕組みに乗らずに自ら就職先を探す、自由応募 への支援も必要だ。兵庫県が主催となり、高校生向け就職合同説明会や 面接・キャリア相談等の勉強会、学校と企業の接点の機会増加を目指し、開催するべきだ。
以上の指摘を踏まえ、高校生の就職における希望に応じた就職につながらない状況や早期離職、これらを生み出す要因となっている独自の就職 慣行などの課題をどのように捉え、改善すべき点は何なのか、当局の所見を伺う。
(2)就職規制 ~1人1社制度の緩和~
次に、改善策として1人1社制度の緩和を提案する。
県規制改革推進会議では第1回でこのことが取り上げられたが、当局は否決理由を後述の通りとしている。
否決理由の1つが、生徒の能力や適性に基づいた就職斡旋が可能。と しているが、ではなぜ離職率が高止まりしているのか。半年以内に約10%が離職するのか。従業員5人未満、飲食・宿泊業の離職率が60%超である。恒常的なミスマッチなら紹介を避けるべきではないのか。
2つ目が、就職活動の長期化による学校活動への影響や、生徒への過重な負担(身体的・心理的・経済的負担)軽減と、短期間で内定。とあるが、社会人の大事な一歩を短期間で決める必要性が全くない。私の高校生活を顧みても、そもそも暇で、就職活動が多大な影響を与えない。受験勉強や毎日部活の方が学校活動への影響は大きい。
また、就職活動も大事な学びの機会。誤解を恐れずに言うならば、卒業まで数ヵ月分の学業に多少の悪影響があっても、準備して・納得して・ 選択した就職先を選ぶ方が、子どもたちの人生には大切だ。短期の内定 獲得、学業への過度な懸念が若者・Z世代の社会人への道に悪影響を与えている。
求人票や企業情報を調べたり、企業の担当者から説明を聞いた会社数の平均は高卒2.2社に対して大卒は16.1社。ミスマッチ・早期離職が起きるのは構造的問題だ。
成人年齢は18歳となった。当事者である高校生の主体性・可能性を過度に制限し、職業選択の自由が奪われている。
高等学校就職問題検討会議ワーキングチーム報告など各種調査では、 1人1社を支持する企業・学校が多いが、就職指導の負担を軽減したい、確実に人材を採用したい大人の都合に感じる。
就職者も支持が多いが、連絡が取れない・離職した子どもたちの声は 本当に反映できているのか極めて疑問だ。
これらの指摘を踏まえ、兵庫県では10月31日までは1人1社、以降 でも2社と全国的にも制限が厳しい。一気に全国トップクラスまで緩和 する当初から3社までとし、選択の自由を増やすべきと考えるが、当局の所見を伺う。
2 県警の業務改革・働き方改革 (警 察)
(1)業務の廃止・縮小への取り組み
2017年、2020年の本会議で警察組織の合理化を問題提起した。不要な 業務、調査、報告を無くすべし。働き方改革は仕事の中身改革。本来 すべき仕事、質・量はどうあるべきか。何をするかも大事だが何をしないのか決めることがもっと大事。過去には交通違反の見取り図作成の名義 貸しで70名の県警察官が送検された事例がありましたが、過剰な書類 作成にも原因の一端がある。業務を再定義せよ。という趣旨。
警察庁は2021年のワーク・ライフ・バランス取組計画の中で、幹部職員は業務の廃止や業務プロセスの見直し等により課題解決を図ることも その職責。必要性や優先順位の低いものを廃止すべきとした。残業削減、有給取得率の増加、ワーク・ライフ・バランスは業務の廃止・合理化無くしては、実現しません。
他の県警でも窓口時間の短縮や自動音声での電話応対など業務の縮小、代替など細かい積み重ねがなされています。
効率化などは現場の職員で工夫可能ですが、業務の廃止・縮小は県警 幹部にしか意思決定できません。
そこで、本部長は着任以来、業務の廃止・縮小にどのように取り組まれ、成果を上げたのか伺う。
(2)交番勤務時間の短縮や通勤型駐在所
業務の廃止・縮小へ2点、具体的に伺います。
10年以上前から警察署や交番の再編・統廃合を訴えてきた。進行中の 計画は、主に1人交番の集約による再編統合などで先鞭をつけた。再編・統廃合の問題提起の根底は業務量に応じたリソースの最適配置。
今回は量的合理化から質的合理化へ。交番や駐在所の運用形態の最適化だ。
日本は交番があって当たり前、24時間が当たり前となっているが、そもそも交番を持たない国が大多数。その常識はネット犯罪が増加し、現場 対応が必要な警察事象が減少する現在も正しいのか。コンビニやファミ レスなども効率化や労働対策で24時間営業を廃止し、鉄道も終電を繰り上げた。
本来であれば、1時間ごとの交番業務量を分析して適切な交番の勤務 時間を把握。警察署・近隣交番の応援体制を考慮し、18時間運用、深夜 勤務の廃止などで、不要な業務・人員配置を削減できるのではないか。
また、勤務開始から終了まで拘束時間は27時間、昼夜逆転という負荷も軽減できる。
今年、警察庁は通達で、交番を2人で運用することも可能にし、既に 日勤交番などが試行されたが、現状は3人以上での運用がほとんど。1人交番の廃止で統廃合を進めても、本格的な合理化へはまだ途上。警察官が住み込まずに通勤する駐在所など、統廃合後の運用面での合理化余地は 大幅に残されていると考える。
そこで、交番・駐在所の統廃合後の運用面での合理化、勤務時間の削減を推進すべきと考えるが、当局の所見を伺う。
(3)宿日直制度のあり方 ~当番制の導入と宿直人員の削減~
業務削減、ワーク・ライフ・バランスに向けてもう一案。
警察庁における2021年のワーク・ライフ・バランス取組計画では、適切な勤務時間管理、柔軟な働き方、職員の心身の疲労回復や健康維持のために勤務間インターバルの確保、とある。
現状の労働時間は深夜を含む15時間30分で、休憩を含む拘束時間は 連続27時間。事案処理が長引けばそれ以上の拘束時間となる。就活の 口コミサイトでは、兵庫県警の職員が一睡もせず36時間勤務したとの コメントも見た。
海外警察の拘束時間は、米国、英国などで8時間から9時間、シンガ ポールでは12時間との報告もある。長時間労働をヨシとする慣習・常識を変えなければならない。
県警察の宿直は庁舎警戒、警察業務全般の応急処置等で労働密度の低い「断続的労働」としているが、実態は仮眠時間が4時間と短く、取れないこともあり、休憩とならず、生活リズムが崩れ、心理的・体力的疲労が 蓄積する。県立病院でも言えることだが、宿直が断続的労働と言えるのか極めて疑問である。
交替制勤務・夜勤者の約10%が勤務に起因する不眠と過眠を主訴とする睡眠障害に該当する論文や日本人の睡眠不足による経済損失は15兆円 との試算もある。市民の安全を守る県警が、「疲弊した組織」でいいはずがない。
長時間労働やパワハラが原因で自殺者を出した長崎県警や徳島県警では当直の見直しを進めている。
警察署の統廃合により、当直に入る日数の間隔を空ける、そもそもの 当直人数を業務量に応じて減らす、隣接警察署で共同管理などの合理化は可能だ。平日・休日ともに連続時間を抑えるため、当直明けの日勤を免除する当番制を採用すべきではないか。
これら働き方改革は仕事の質向上、優秀な人材の採用、女性警察官が 働きやすい環境につながり、ひいては警察力の向上につながる。
連続拘束時間の削減、職員のワーク・ライフ・バランス実現に向けて、当番制の導入と宿直人員の削減などの対策を考えるべきだと思うが、当局の所見を伺う。
3 補助金や公的サービスの厳格運用 (財 務)
政治家や公務員は税金で食っているくせに。皆さんも一度は言われた事が あるだろう。使途や生活にちょっと違和感があると、「税金の一部が使われている」と指弾されるが、給料の源資が税金であれ、労働の対価である。 100歩譲るとして、では税金で食っているのは我々だけなのか。実はそう ではない。
例えば、半導体工場には3年で4兆円の補助金、投資額の半額近い税金が投入されている。国益はあるが、労働対価はない。でも半分税金が入って いる。NTTは国が筆頭株主で1/3以上保有。つまり人件費や利益、経費の1/3は税金だ。
政務活動費で年に数回しか請求しないタクシー代、800円程度でも何の ためって確認される。しかし、半導体工場やNTTに半分から1/3の税金が 入っている厳しさでチェックはされない。懇親会でダンサー呼んでも怒られない。
今回の提案は公務員に向けられる厳しさの一部でも無償化や公的サービス、補助金などに反映した制度設計・運用をしませんか。
例えば、県立大学の無償化。高等教育を100%税金で勉強し、年間ざっくり300万円の税金が投入されている訳だ。無償化の対象外となる成績要件はjassoと同じ修得単位5割以下だが、100%税金で勉強しているのだから最低でも8割は修得して当たり前ではないのか。無償化と100%学費負担の間が ないことも少し懸念を持つが。私が大学1年目に修得したのは9単位ぐらい だった。私みたいな学生に税金で勉強させる必要はない。
また、コロナの委託・補助金で多くの不正が発覚している。PCR検査数の水増しで9事業者4億円に返還請求をしているが、全事業者を刑事告訴 すべきだ。東京都が102億円、大阪府が50億円の返還請求をしている。人口対比でみると兵庫県の4億円は調査漏れの可能性はないのか。他にも返還 請求すべき事業があるのではないか。
さらに、県が実施する交付金・補助金で不正があった場合の加算金は10.95%。金利の上昇や一般的な企業の調達コストを考えると、罰則的要素が少なく、大幅に上げるべき。
事例はまだまだあるが、キリがないし、敵を作りすぎるので、この程度にしておく。
しかし、予算制約がある中で、本当に必要な人に県民サービスを届ける には、時にこのような厳しさも重要である。
以上の指摘を踏まえ、補助金や公的サービスの厳格運用を図るべきと 考えるが、当局の所見を伺う。
4 公務員の自腹と低すぎる手当 (総 務)
兵庫県以外の多くの自治体では、名刺は幹部以外は自腹というのはご存じでしょうか。公務員の自腹問題は他にも存在するのでは。本年4月に発売 された書籍「教師の自腹」では、公立小中学校の教職員千人のうち、2022年度中に教材費などを「自腹」経験が75%以上、1万円以上を負担した人が 3割を超えていたとのことです。
部活なら遠征や大会出場のための交通費、審判資格費用など年13万円との試算もあります。他にも、業務上必要な書籍は適切に購入できているのか。高騰するホテル代に対し、規定の宿泊費で賄うことができるのか。
昨年の本会議でもインフレを見据えた予算編成の提言を行った。
国家公務員は今年4月に旅費法が改正され、宿泊費の上限見直し等の検討が行われている。
自腹の理由として、規定上は申請できるが、書類が煩雑だという声をよく聞きます。自腹あるあるでよくわかります。僕も在来線の交通費は同じ理由で請求していません。
安すぎる手当についても警察委員会で申し上げてきた。能登の災害派遣 だと廊下で寝泊りするような過酷な業務で日額840円。低すぎる手当で 割に合わない。ある種の自腹・自己犠牲だ。会計年度任用職員の勤勉手当はようやく実現し、地域手当の見直しを国は行う。
一方、過失とはいえ、排水弁を閉め忘れたら半額の300万円を払え。 キャリア官僚の東大卒割合が過去最低となるのも当然だ。
これまで、優秀な人材採用のため、爆速で出世できる制度、SPI入試、 受験要件の緩和や低すぎる手当などを指摘してきた。
急速な労働人口の減少が始まり、民間が給料を大幅に引き上げる中で、 当たり前のことをやらないと新卒採用で負けてしまい、また現職員も民間に転出し、組織が劣化し、結果として県民サービスが悪化する。
税金で食っていると言われながら、自腹を切っている公務員。是正すべきところは是正すべきではないかと考えるが、当局の所見を伺う。
5 NEXT GIGAスクールを契機とした県の役割拡大 (教 委)
(1)校務系DX
GIGAスクール構想開始から5年、タブレットや通信環境が整備された。 しかし、市町村単独で実行するにはリソース不足だった。
第1期の課題を踏まえ、文部科学省は「GIGAスクール構想」の運用を 市区町村から都道府県へ変更する。昨年、本会議で提言した県による市町業務の補完・共同事業といえ歓迎する。
端末の共同調達だけでなく、人員の共有化やコスト削減に向けて、 やるべき項目は更にあるのではないか。
例えば、推奨ネットワーク帯域を満たしている学校は約2割とも言われ、回線契約変更や通信アセスメントが必要。
自治体や学校、学級でさまざまな利用上の制約が課せられているが、 本当に必要か。持ち帰り規制やチャット禁止など、県によるガイドライン も必要ではないか。
また、生成AIやRPA・マクロ活用、指導要録や調査書・成績一覧表等の帳票統一化、工程表や経費精算など校務の自動化支援、MEXCBTの活用推進など市町村単独では人員不足・予算不足・ノウハウ不足で結果が出ない 事業が多々ある。GIGAスクール運営支援センターは県で代替・共同実施 するなど、せっかく強制的な合議体ができたのだから、あらゆる学校業務の統一化の実現に向けたプラットフォームに昇華させるべきだ。
そこで、県全体の教育レベルの向上へNEXT GIGAスクールを契機とした県の役割を拡大し、校務のDXを図っていくべきと考えるが、当局の所見を伺う。
(2)教育系DX ~動画授業による学習支援と遠隔授業配信センター~
校務系に続き教育系で実施すべき事業を提案する。
生徒一人ひとりの学びに合わせた活用は道半ば。せっかく、高スペックなタブレットや通信環境が配備されるのだから、フル活用したい。
私が11年前から問題提起してきたmoocsは今こそできる。動画授業を県で一括で安価に購入し、放課後学習支援に利用してはどうか。
工業や農業などの専門高校では大学受験を志望する生徒が増加。受験に必要な授業を受けられず、志望校が限定される。
また、中山間地域や離島、小規模校で開設できなかった教科で学びが 制限されている。塾が地域にない、塾代を支払うことが困難な家計への 支援も可能だ。
補講・放課後学習支援のため、動画配信事業者と契約し、個別最適化 授業や塾代支援をすべきではないか。
正規授業として遠隔授業も強化すべきだ。既に、千種高校と和田山高校にて研究が行われたが、その後、受信側が教師以外も代行可能とする国の規制緩和もあり本格的に推進できる状況に入ったのではないか。将来は 配信側が生である必要がなくなる規制緩和も期待したい。
小規模校が増加し、子どもたちの同質性が高まっていることも課題で あり、オンラインを活用した学校の枠を超えたつながりを持たすことが できる。
これら2つの新しい学びを推進すべきと考えるが、当局の所見を伺う。