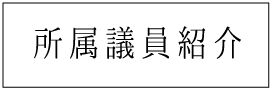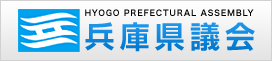概要 / 代表・一般質問 / 議案に対する態度と考え方
質 問 日:令和6年6月7日(金)
質 問 者:北上 あきひと 議員(ひょうご県民連合)
質問形式:分割
1 県民に信頼される県政構築に向けて
本年3月末以降、県民の県政への信頼は大きく揺らぎ、また県職員に動揺がひろがるとともに士気の低下が危惧されているところです。そして日毎その深刻さが増していることは、誠に居たたまれません。県政への不信を払拭するために、先ず重要なことは知事の誠実な政治姿勢ではないでしょうか。知事が疑惑に対してご自身の言葉で説明責任を果たされ、厳しい質問や批判にも真正面から向き合う姿勢こそが求められていると考えます。
私たちひょうご県民連合議員団は、県民本位の立場で議員の使命を果たし、透明性のある公正な県政の実現を全力で追求することによって、県民の負託に応える決意であることを改めて表明し、質問に入ります。
(1)前西播磨県民局長による告発文書に係る知事記者会見について
斎藤知事は本年3月27日の記者会見において、前西播磨県民局長による知事や県幹部を批判する内容を含む文書を巡り「事実無根の内容が多々含まれている内容の文書を職務中に職場のPCを使って作成した可能性」があり「本人も作成と一定の流布を認めている」とし、予定されていた退職を一旦留保し県民局長の職を解いたことを発表され、加えて「公務員としては失格」であり「懲戒処分を行うことになると考えている」と発言されたのです。
当該事案に、公益通報制度に詳しい上智大学の奥山俊宏教授は「文書の内容が嘘八百ではなく真実相当性がそれなりにあるのならば、報道機関への送付も『公益通報』に該当し、文書を作成した県幹部職員に対する報復的処遇が違法性を帯びる可能性がある」と指摘されています。前県民局長は知事記者会見の後「『ありもしないことを縷々並べた内容を作ったことを本人も認めている』という知事の発言があったが、私自身がそのことを認めた事実は一切なく、告発文は出来るだけ事実に基づいて書いたつもり」と文書で反論され、4月4日には、県の公益通報制度に正式に通報されました。前県民局長は公益通報者保護法に基づき不利益な扱いから保護されるべき対象者に該当する蓋然性があります。
これらの事柄に鑑みて、「公務員失格」「事実無根」「嘘八百」「告訴」等のご発言は不穏当であり、県民や職員に不信や怖気を与えている要因の一つだと考えます。よってご発言の撤回を含む善処を求めますが、知事のご所見をお伺いします。
(2)前西播磨県民局長による告発文書に係る本県内部調査とそれに基づく人事処分について
当該調査は知事が「事実無根」「嘘八百」等の言葉を用いて文書の信ぴょう性に評価をくだし、「懲戒処分を行うことになると思う」との見通しを示した上で、県庁内部において実施されたものであり、当初から公平性や第三者性、中立性や客観性についての疑念が指摘されてきました。それに対して知事は「内部の調査であるものの、弁護士が関与していることから、一定の第三者性、客観性は担保されている」と度々述べてこられたのです。しかしながら、県当局が別の弁護士に依頼して作成した5月29日付文書「職員処分手続きと『弁護士』関与の問題点の有無」において、そもそも弁護士に「中立性は求められていない」ので、当該調査に関与した弁護士の対応が「『中立的』でないとの批判は」「批判として的を得ていない」と明言されているように、前述の知事のご発言に説得力はありません。
加えて、調査に関与した弁護士は、知事の政治資金パーティーに関連し「保証業務を背景とした企業へのパー券の購入依頼が実行された」との疑惑が告発文書で指摘された兵庫県信用保証協会の顧問弁護士であることが、5月20日の新聞報道で明らかになりました。同紙面に掲載された専門家のコメントに「文書で指摘された団体の顧問弁護士に調査を相談したことは客観性や中立性を損ね、県政の信用失墜を招きかねない」との指摘があるように、当該調査とそれに基づく人事処分の正当性は著しく損なわれています。県民や県職員に、調査とそれに基づく処分への理解納得が得られているとは言い難い状況です。
よって、県民からの信頼を回復し、職員にとって真に「風通しのよい職場づくり」を実現するためには、当該人事処分の即時撤回が必要であると考えますが、知事のご所見をお伺いします。
(3)県人事当局による報道機関への調査について
本年4月、県人事当局が告発文書の受領の有無を新聞記者に問い合わせていたことが明らかになりました。報道によると、記者は文書を「受け取ったとも、受け取っていないとも答えられない」と返答し、「情報源の秘匿が必要不可欠な報道関係者に情報開示を迫ることの異常さを指摘した」とのことであります。また新聞労連からは「記者から経緯を聴取し、情報源の開示を迫る人事課の高圧的な対応は、報道の自由や市民の知る権利を侵害するもの」であるとの声明が発せられました。
報道によれば、県人事当局は「今後も一部報道機関や関係者への聴取を続ける」と発言したとのことでありますが、それは許されないと考えます。報道機関の大きな使命の一つは「権力の監視」であります。「行政権」を行使する県当局は正に権力であり、今回の記者の判断対応は至極当然であり健全なものです。県当局による情報源を巡る報道機関や関係者への聴取は、権力による報道の自由への干渉であり、強く自戒を求めます。
県におかれては、今回の記者への聴取についての非を認め謝罪するべきであり、今後は対応を改めるべきだと考えますが、知事のご所見をお伺いします。
(4)本県公益通報制度に外部通報窓口を設置することについて
消費者庁は「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン」を定めており、2022年6月の改訂版においては「地方公共団体内部の受付窓口に加えて、外部に弁護士等を配置した受付窓口を設けるよう努める」とあり、消費者庁の2023年度調査によれば大阪府・京都府・滋賀県等、都道府県の6割以上が外部に通報窓口を設けているところです。
本県は外部に通報窓口を設置しておらず、知事は定例記者会見で「外部に設置することも検討課題である」との認識を示しておられますが、私も組織として自浄作用をより発揮するために、独立性を担保する外部窓口の速やかな設置が必要であると考えます。そこで、改めて知事のご所見をお伺いします。
(5)知事のパワーハラスメント疑惑と職務遂行への影響について
告発文書に端を発し、知事のパワハラ疑惑が各種メディアで取り上げられ、県関係者の証言として「多くの幹部職員が理不尽に怒られている」「自分の意見を言う職員が全く聞き入れてもらえない」「『こうしたい』という意見が言えない組織になってしまっている」等と報道しています。
具体例として、「はばタンPay+」を広報するためのチラシ・ポスター・うちわに「自分の顔写真がない」と知事が立腹され、その後に顔写真が掲載されたこと、「尼崎の森中央緑地」で開催された兵庫ユニバーサルマラソン開催日には、会場の授乳室・救護室が知事専用個室になり、授乳目的の母子や熱中症患者を含め本来利用するべき人の入室が叶わなかったことが、各種報道や丸尾まき議員の独自調査で指摘されています。
知事は、両事案ともに専ら担当部局の自主的な判断だと説明をされていますが、知事の理不尽な言動が職員の職務遂行に悪影響を与え「県民本位の判断が出来なくなっているのではないか」との県民の懸念は拭えず、改めて知事のご所見をお伺いします。
(6)知事・県幹部職員への物品供与や供応接待について
4月16日の県議会産業労働常任委員会において、我が会派の上野議員の質問に対し産業労働部長は、加西市内の企業に6万円相当の家電製品の提供を依頼し、受領したことを認められました。加えて、兵庫県製品の㏚に繋げたいとの意思があったこと、半年以上経過した後に告発文での指摘を契機として、未開封で返還した旨の答弁をされました。
国家公務員倫理規程では、補助金等の交付や行政指導の事務等に係る利害関係者からの物品の贈与や供応接待を禁止しており、また国家公務員倫理法では、本県を含む地方公共団体にも国に準じた必要な施策を講じる努力義務を課しているものです。当該企業は本県奨学金返済支援制度の補助金の交付を受ける等、物品の贈与が許されない利害関係者ではないでしょうか。
また、本県人事課が作成した「不祥事防止読本」には「受け取った後に返した場合」も不正の有無を問わず収賄罪が成立すると記され「相手方がどのような名目で金品を送ったにせよ、裁判所では客観的な事実を基準に判断される」ことや「未開封であっても、直ちに返さなければ、受け取る意思があったものとして判断される」と注意を促しています。利害関係企業から6万円相当の物品を受領しても、PR目的であれば不正にならないと判断するならば、それは「不祥事防止読本」との齟齬が生じるのではないでしょうか。
もし仮に受領が許されるとしても、本県財務規則139条では「物品管理者は、寄附により -中略- 物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書により決定しなければならない」等と記されており、規則に則った手続きが求められます。
当該事案を巡っても各種メディアで連日大きく報道がなされ、知事並びに幹部職員の綱紀に関しての県民からの信頼は大きく揺らいでいます。知事並びに幹部職員は利害関係企業・団体からの物品供与や供応接待についてどう対応して来られたのか、「不祥事防止読本」に基づいた言動に徹し、財務規則に則った対応をされているのか明らかにしてください。また、今後においてはより透明性のある厳格な対策を講じて頂き、幹部職員共々に「李下に冠を正さず」の心持ちで一層厳正に対応頂くことを願いますが、知事のご所見をお伺いします。
2 本庁舎4割出勤と県庁舎再整備について
本年3月に発表された「新しい働き方モデルオフィス検証結果(中間報告)」では、在宅勤務中の業務効率については、約7割の職員が低下したと回答し、今後の在宅勤務の希望頻度については、約8割の職員が週2日以下と答えています。また、本年2月に職員団体が行ったアンケートでは、出勤率4割について「問題が多いので見直すべき」との回答が84%でした。記述欄には「出勤率4割で、今後の業務が円滑に回るとは思いがたい」との意見や「職員間のコミュニケーションの低下」「庁舎がない状態で災害が発生した際の対応」に不安を感じるとの声が寄せられているところです。これらの結果に示された職員の意向には、丁寧な対応が必要ではないでしょうか。加えて、我が会派の議員が度々指摘する通り、厚労省・総務省・人事院の各「ガイドライン」等には「実際にテレワークを行うか否かは本人の意思によるべき」「職員の希望・申告を前提として」等と記されていることを改めて申し添えます。
職員の出勤率や県庁舎再整備については、県民の理解も必要です。県民や事業者との意思疎通や情報伝達、個人情報や信用情報の取扱、緊急時の対応等、県民サービスへの影響を巡っても検証するべき課題は数多くあります。
知事の基本的なお考えは、昨年3月の記者会見から現在に至るまで、県庁1・2号館の跡地に庁舎は建設せず、4割出勤をめざすということなのでしょうか。県民と職員の理解合意を図りながら検討するべきと考えますが、知事のご所見をお伺いします。
3 今後の高齢者福祉について
ここ最近の新聞には「認知症2040年に584万人」、「65歳以上の一人暮らし高齢者数2050年に1,084万人。支援待ったなし」等、高齢者福祉に関わる見出しが続きました。実際私のもとにも、高齢の方から、話し相手がいないことでの孤独感、預貯金や不動産等の財産管理、病気の際の通院付き添いや入院の諸手続き、死後の家財処分や納骨等の相談が寄せられているところです。人生100年時代を迎えた今、個人としての尊厳が守られ、安心して充実した人生を全うすることが、誰もの切実な願いとなっており、県民各々の高齢期の暮らしを底支えする仕組みの強化拡充が求められていると考えます。
(1)高齢者本人の意思を尊重した権利擁護支援について
高齢者の福祉において、判断能力が低下した独居高齢者であっても、住み慣れた地域で引き続き本人らしい生活を継続するための支援を広めていくことが大きな課題です。そのため、一人で決めることに不安を覚える方を法的にサポートし、本人の意思を尊重した権利擁護支援を行う「成年後見制度」の果たす役割が益々重要性を増し、その需要は日毎大きくなるのではないでしょうか。
一方、それらの制度を担う人材の確保や支援体制の構築が十分なものか、懸念されるところであります。県においては、県内市町や社会福祉協議会等とも連携を図り、市町単位では解決困難な広域的な課題に対する取組を推進するなど、県民生活を支えるために制度が存分に機能するよう一層努めて頂きたいと思います。そこで、これまでの本県における取組み及び今後の方策について、当局のご所見をお伺いします。
(2)動物愛護管理施策と高齢者福祉の連携について
一人暮らしの高齢者がペットを飼っている場合、心の拠り所になり、認知症になりにくい傾向があるとの見解がある一方、施設入所や認知症になった際に、そのペットの世話をどうするのか等が大きな課題となっています。また、私自身も高齢者世帯での多頭飼育崩壊の相談等を度々受けているところです。専門家は「人間の福祉をきちんと進めるためにはペットの問題にも向き合わなければならない」と指摘していますが、今後、一人暮らしの高齢者がますます増加することを考えると、動物愛護管理施策と福祉の連携は、更に重要な課題となります。高齢者福祉を担う市町職員やケアマネジャー、介護福祉士等が、この課題を先ずは十分に認識して頂くことが必要不可欠だと考えます。
本県「動物愛護管理推進計画」には「関係市町の動物愛護管理部局や福祉部局との連携を強化し」との記載がありますが、2021年3月に策定されたばかりであり、その具体的取組は緒についたところです。介護現場が非常に多忙で激務であることは認識するものの、福祉現場における課題意識の醸成等、動物愛護管理施策との連携を深めていくことも重要です。既に地域包括支援センターの会議等において、相談窓口の周知等を行って頂いているところですが、本件にかかる今後の取組について当局のご所見をお伺いします。
4 教職員の確保と処遇について
文科省の実態調査によると、2021年5月1日時点における公立小・中・高校・特別支援学校での教員の欠員は全国で2,065人、神戸市を除く兵庫県で86人であり、昨年5月1日時点の県の不足人数は164人と、年々増加しています。教職員の確保や働き方改革については、本県でも取組が進められていますが、教育現場の課題は多様で複雑化しており、人員の確保は極めて重要です。
(1)外国籍教員の処遇について
県内の公立学校で働く外国籍の教職員は現在27名であり、その全ての教員は日本国籍の教員と同様に教員免許を取得し、教員採用試験に合格して採用され、各々の学校で教育活動を担っておられます。にも拘らず、本県においては外国籍であるが故に教諭としては採用されず、「任用期限を付さない常勤講師」として任用され、主幹教諭をはじめ給料表3級以上の職には就くことが叶わない実態があります。
このことについて改善を求めた2年前の私の代表質問に教育長は、1991年3月の旧文部省教育助成局長通知に基づいて対応している旨の答弁をされました。しかしながら、「地方分権一括法」では、国が自治体に指示できるのは法令に根拠がある場合に限られており、当該通知は助言に過ぎません。現に、東京都、川崎市、さいたま市では教諭として任用され、東京都においては既に外国籍教員を主任教諭(東京都独自の職)、指導教諭、主幹教諭に任用しています。また、大阪府、鳥取県、大阪市、堺市では教諭(指導専任)として任用し、なかでも大阪府は、指導教諭、主幹教諭相当級である特2級への昇級を認めているところです。加えて、兵庫県内でも、例えば尼崎市立高校においては、外国籍の英語科教員が2000年度から2003年度に教諭として勤務した実績があります。文部省通知を唯一の根拠として、外国籍教員を教諭として任用しないとする本県の姿勢は、地方分権改革の時代に似つかわしくない不合理なものであり、改めるべきです。
国籍にとらわれずに優れた人材をして確保し、適材適所の人事配置によって全職員が持てる力を存分に発揮することは、県政発展と全ての県民の幸せに資するものだと考えますが、県教育委員会は任命権者として、外国籍教員の処遇を今後どのように善処されるのか、ご所見をお伺い致します。
(2)臨時的任用教員の確保について
私はかねて、本来正規教員が配属されるべき定員枠に必要な正規教員が配置されない状況が常態化し、現場は臨時的任用教員で人材を確保せざるを得ないが、それがままならないこと、更に年度途中における産休、育休、病休等の代替配置としての臨時的任用教員の確保は一層困難であることを指摘し、正規教員の確保に努めること等を求めてきました。今議会では、特に臨時的任用教員の確保についてお伺いします。
県内市町の教育委員会が、臨時的任用教員を確保するにあたっては、原則週5日38時間45分の勤務ができる人材を求めます。必要な人員が確保できない場合においては、本来一人分の勤務時間を複数で担うことも解決策の一つであり、例えば、午前と午後や週3日と2日に分割した採用によって人員を確保することも考えられます。現に「半日だけなら」あるいは「週3日だけなら」勤務可能な人材がおられ、学校現場からは「一刻も早く学校に来て欲しい」との声が寄せられています。市町の教育委員会においても、そのような現場の声に応えたいとの想いであると認識するところです。
学校現場の人員不足の影響は、当然子どもたちに及びます。「子どもの最善の利益」を最優先にし、市町教育委員会との連携を更に図り、柔軟な確保策を採り入れる等、積極果敢に人員確保に努めて頂きたいと思いますが、当局のご所見をお伺いします。