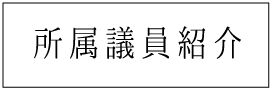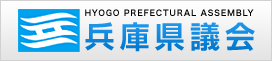概要 / 代表・一般質問 / 議案に対する態度と考え方 / 意見書案 / 提案説明 / 討論
質 問 日:令和7年2月26日(水)
質 問 者:橋本 成年(ひょうご県民連合)
質問形式: 一問一答

1 阪神タイガース、オリックス・バファローズ優勝記念パレードのあり方について【県民生活】
2023年11月に実施された阪神タイガース、オリックス・バファローズ優勝記念パレードについて伺う。
昨年の決算特別委員会で我が会派の黒田議員が「公務として担う理由」について総括で質問した際に、「スポーツが地域に大きな活力をもたらすことや県民と地域の安全確保」という答弁もあり、パレードの実施を公務で行ったことは一定理解している。
ただ、パレードの実施については、公金を支出しないとしたことから、歳入確保についても実行委員会で担う必要があり、9月22日に県庁内にプロジェクトチームを設置してから11月23日の実施まで、兵庫、大阪合わせて6億4千万円もの業務を、実質2か月ほどで執行するという、とんでもない負荷が事務局にかかっていたと思われる。そうした中で、事務局において責任ある立場を担ってくださった人材が、病を得て命を落とされたことは大変重い現実である。
私は、政治の道へ入る前に宝塚市役所で勤務した地方公務員であった。22年の間に、仕事でかかわった方を何人か失った経験がある。中でも、明らかに業務における精神的な負荷が原因で亡くなられたのだと受け止めざるを得ない別れがあった。私たち人間は、誰一人として完全無欠ではありえない、弱さを抱えた存在だ。だからこそ、その死を悼むとき、何がその背景にあったのか、防ぐことは出来なかったのか、私たちは可能な限り実態を把握し、教訓を得なければならない。
以下に、私が今回の実行委員会における課題と考える点を挙げていきたい。
まず、パレードを実施する意思決定について。知事記者会見によると、吉村知事と甲子園球場の始球式で出会った際に、パレードの話になり連携して取り組むことにした、とのことだが、実行委員会を組成してパレードを実施することの意思決定について、記録文書は残っていないのか?例えば、2005年の阪神リーグ優勝時には神戸でパレードを実施していない。やるかやらないかは知事の一存、トップダウンで決められる事項といえるのか。
次に、大阪と神戸の2拠点で2球団による同日開催というのは史上初とのことだが、その調整にかかる負担が相当に大きかったのではないかという点。実行委員会規約には、会長は関西経済連合会の会長、事務局は両府県に置きそれぞれの事務局長を両知事が務めると明記されている。聞くところによると、契約の相手方が兵庫県と大阪府で同一であるパレード実施に係る企画・運営等業務契約はそれぞれの事務局において行ったとのことだが、支払い業務は大阪府事務局において一本で処理されており、意思決定や事務処理が通常の行政事務とは異なり、複雑になっていると感じた。短期決戦でのイベント実施に向けて、各種調整は本当にご苦労が多かったと考える。
三つ目に、パレードの目的と成果の検証について。実行委員会規約には「パレードの実施により賑わいを創出し、都市魅力を発信するとともに国際博覧会条約に基づく大阪・関西における2025年日本国際博覧会に向けた機運と取組みを大いに盛り上げること」が目的として明記されている。神戸において45万人もの来場者を迎え、事故なく開催できたことはそれ自体が大きな成果と言えるだろう。しかし、実行委員会の目的である大阪・関西万博の機運醸成については達成できたのだろうか?事業報告書を見る限り、万博に関しては実行委員会の正式名称として記載があるだけで、当日のバナーなどにも万博の文言は見当たらない。スポーツの政治利用といった世論の批判を受けて万博機運の醸成という実行委員会の目的を取り下げたのであれば、事業目的の一部については達成できなかったことになるが、事業目的と照らし合わせた事業の評価はどのように行ったのか。
四つ目に、資金繰りのリスクについて。冒頭にも述べたが、この事業は当初の見込みで約5億円を要するといわれ、その費用はクラウドファンディングと協賛金などで充てるとされた。しかし、クラウドファンディングは手数料や返礼品の負担も大きく、思ったほどの成果が上がらず、また兵庫県での協賛金確保についても相当のご苦労があったと聞く。また歳出面においては、期日の決まった短期決戦で安全に配慮した運営を実施しようとすると、調達における競争性の確保が難しいことや、警備にかかる人員や資機材の増大も含めて費用が膨張したと推測され、最終的には総額6億4千万円に達した。一方、実行委員会規約には、費用負担は「寄付金及び協賛金等をもって充てる」との記載しかなく、歳入不足に陥った場合の責任所在はどこにあるのか、実際に資金不足となった場合にはどのように処理する方針であったのか、資金繰りリスクへの対処方針が不明である。事務局で会計を預かる立場であれば、その重圧はいかほどであったか、想像に難くない。
五つ目に、監査のあり方について。聞くところによると、今回のパレードについては、委託料や負担金といった形での公金支出がないことから、県の監査委員による財務監査および行政監査の対象とはならない、とのことである。しかし、令和3年3月18日付の新行政課長及び会計課長連名通知によれば、「県が事務局を担う団体の会計事務については、公金と同様に適正な事務の管理及び執行に取り組む必要」がある。本パレード実行委員会のように県が事務局を担うが公金支出のない団体の事務については、どのようにして適切な事務処理の確保を担保していくのか?当然に実行委員会での内部監査は行われたと承知しているが、県の公務として行う以上、単なる任意団体とは異なるレベルで適正性を担保する仕組みが必要だと考える。
知事は、実行委員会において兵庫県事務局長という立場であり、事務局を総括する立場であった。内部的にも対外的にも、責任を負っていただかねばならない立場である。決算特別委員会では、担当部局から「今後の事業実施の改善や職員負担の軽減につなげていきたい」との答弁を頂いているが、前述の具体的な課題も踏まえて今回のパレードをどのように総括しておられるのか、知事のご所見を伺う。
2 職員の安全衛生、特にメンタルヘルスの特別な対策の必要性について【総 務】
昨年来、私が兵庫県議会議員とわかると「大変やね」とお声掛けいただくことがとても増えたと感じている。これは、知事はもちろんのこと、議員の皆さんや幹部職員をはじめ一般職の皆さんも同様ではないかと思う。私たちは公務員として、それぞれの立場で成果を出していくことが求められているのはもちろんだが、その大前提として私たち自身が健康を保ち、イキイキと活動できることが重要であることは論をまたない。
そこで職員の安全衛生の現状について確認したところ、残念なことに今年度12月までの途中経過であるが、現職の県職員が病気や事故・その他で8名お亡くなりになっているとお聞きした。これは過去の5年間の各年度と比べてもすでに最大であり、ここに含まれない公営企業や教育委員会、警察も合わせるとさらに多数に及ぶ可能性がある。
なお、3か月以上の長期療養が必要となった職員数について、令和5年度では知事部局と部外局で合計76名、そのうち62名と圧倒的多数が精神疾患による療養であり、この傾向は過去5年においてもおおむね同様である。
一般疾病による疾患については、健康診断の受診率向上や保健指導の充実、長時間勤務の削減などが重要な取組みであろう。一方で、精神疾患については長時間勤務が原因となることもあるが、もう少し質的な問題が大きいように思う。
例えば、各種のハラスメント対策は重要な取組みの一つであろう。安心して相談できる内外の窓口を設けること、健全な労使関係によって風通しのよい職場環境を創ることなども重要だが、私はトップの役割も大きいと考える。ハラスメント行為は人権にかかわる問題であり、職員の尊厳を傷つけ、職場環境を悪化させる問題であること、兵庫県は全てのハラスメント行為を断じて許さず、全ての職員が互いに尊重し合える安全で快適な職場環境づくりに取り組むことを、知事自ら宣言なさってはいかがだろうか。
また、顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメントについても、職員に過度なストレスを感じさせ、通常の業務に支障が出るケースもあるなど、県庁組織においても大きな問題となりえる。自治労が行った令和2年10月の組合員1万人以上を対象とした調査では、回答した組合員の46%が過去3年以内にカスハラを経験したというデータもあり、深刻な問題である。特に兵庫県では、昨年から広聴部門をはじめ各部門へ多くの苦情が寄せられ、職員にとって大きな負担であると聞いている。公務職場においては、市民からの苦情を的確に処理することも重要なサービスの一つであり、正当な苦情とカスハラを識別することは容易ではない。しかしだからこそ、カスタマーハラスメント対策マニュアルの整備により統一的な基準を設けることや対応方針を明確化すること、電話への録音機能の追加など可能な対策を研究して職員を守る姿勢を明らかにしてほしい。
もちろん、メンタル不調の原因はハラスメントには限らないが、職員という県にとって最も大切な公共財を守り、活かしていくために組織としてなすべきことは必ずあると考える。職員の命を守り、安全で快適な職場環境づくりを進めるうえで、特別な対策が必要と考えるがご所見を伺う。
3 被災者が尊厳ある生活を営むための避難所のあり方について【危機管理】
災害時に、避難所において守られるべき最低限の基準として、スフィア基準が知られている。これは、「人道憲章と人道支援における最低基準」の通称であり、1997年に発生したルワンダの大虐殺後、難民となった人々へ国連やNGOが支援に入ったものの8万人もの死者が出てしまう事態となったことが発端となり、その課題解決のため「支援の質」を確保するためのスフィアプロジェクトがうまれた。その成果物として1998年に初めてのハンドブックがまとめられ、2018年には第4版が発行されている。
スフィア基準から見た日本の避難所の状況は、まだまだ「尊厳ある生活を営む権利」が保証されている状態とは言えない。30年前、阪神・淡路大震災において避難所生活を経験した方が避難生活で困ったことの第一位がトイレの問題だったと言われている。その後は、携帯トイレや簡易トイレ、マンホールトイレ、トイレカーなど様々な対策が用意されるようになった。しかし能登半島地震においても、断水や排水の状況によって使用時のストレスが異なり、慣れない環境でトイレの衛生状況を維持することには困難が伴ったと聞く。今回の2月補正予算では、トイレカーの取得に向けた予算が計上されている。車いす利用者など福祉的なニーズも充たすトイレカーを各自治体が確保することで、本県が主導して関西広域連合が中心となって始まったカウンターパート方式も活用しつつ、被災地への支援に活用してほしい。
また、プライバシーや居住スペースの確保も重要な課題。阪神・淡路大震災の時もそうだが、東日本大震災においても避難所における女性や子どもへの暴力は、なかったとは言えない。2016年熊本地震の際には、スフィア基準を知っていた登山家の野口健さんが100以上のテントを提供し、被災者の居住スペース確保に貢献されたことも知られている。能登半島地震では、被災地の地理的特性もあってインフラの復旧に長期を要することから二次避難も進められた。災害大国である我が国において、避難所のあり方は徐々に改善していることは確かだが、能登半島地震では当初ボランティアを自粛すべきという雰囲気も生まれてしまい、長期化する避難生活をいかに質的に向上させていけるか、残された課題は大きい。
被災者であっても尊厳ある生活を営む権利があり、目で見て分かる課題だけではなく、避難生活の「質の向上」を目指していくために、県としてスフィア基準をどのように活用していくか、また具体的にどのような取組みが必要と考えるか、ご所見を伺う。
4 都市計画道路中筋伊丹線(中筋工区)の着工に向けて【土 木】
宝塚市の山手に位置する中山五月台方面から伊丹方面への主要交通路となっている中筋伊丹線は、中筋2丁目交差点が主要渋滞箇所となるなど、整備が必要である。すでに4車線化が完了している伊丹市域と接続する形で2車線の現道を4車線に拡幅する予定である。また、県による街路整備と併せて市道部分の整備も実施することで、中筋2丁目及び中筋7丁目の交差点改良が実現すれば、周辺における渋滞の解消が期待されるところである。
今後の課題として、相当数の用地買収を実施する必要があり、おおむね10年程度の工期が予定されているが、交差点改良を早期実施してほしいとの地元からの要望があるので、整備順序について方向性をお示し願いたい。具体的には、中筋7丁目交差点へ進入する市道宝塚長尾線について、右折レーンが未整備のため渋滞が頻発している。市道部分の拡幅は宝塚市の事業となるが、交差点部分の改良は県と歩調を合わせて進める必要がある。終点部分にあたる中筋2丁目交差点の整備が最優先なことは理解するが、伊丹市との接続部分である中筋7丁目についても同時、または可能な限り早期に改良に着手してほしい。そこで、都市計画道路中筋伊丹線の整備について、事業化に向けた現在の取組状況と今後の見通しについて、ご所見を伺う。