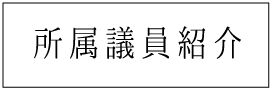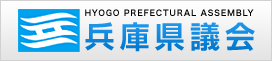概要 / 議案に対する態度と考え方 / 会派提案の意見書案
■請願
| 請願番号 | 件名 | 会派態度(議決結果) | 会派としての考え方 |
| 第2号 | 子どもの医療費を所得制限なしに18歳まで無料にすることを求める件 | 継続に賛成(不採択) | 1 子どもの病気の早期発見、早期治療を支え、すべての子どもの健やかな成長を保証するためには、医療費の不安を軽減する子どもの医療費助成制度は重要であり、本県においても段階的に支援拡充に取り組んできた。2 そのような中、県内の自治体では独自の制度拡充に取り組んでおり、令和5年度中に所得制限なしに通院・入院費が完全無償となる自治体は、中学校3年生までが25市町、高校3年生までが17市町となっている。3 住む地域により格差が生じるのは望ましくなく、県内、どこに住んでいても、一律の水準ですべての子どもに必要な医療が保証されるのが望ましい。4 一方、県の厳しい財政状況を踏まえると、県の制度を拡充して所得制限なしに18歳まで医療費を無料にすることは難しい面があると言わざるを得ず、前回から特に状況変化もないため、今回も継続審査を主張する。5 なお、継続が認められない場合には、「不採択」とせざるを得ない。 |
| 第21号 | 訪問介護費の引き下げ撤回及び介護報酬引き上げの再改定を早急に行うことを求める意見書提出の件 | 採択に賛成(不採択) | 1 令和6年度介護報酬改定において、政府は訪問介護の基本報酬を身体介護、生活援助等の各区分で2%超の引き下げを行った。2 厚労省が引き下げの理由として訪問介護の利益率が全サービスの平均を大きく上回ったことをあげているが、これは集合住宅併設型など大規模事業所の利益率によって平均値が引き上げられていることによるものである。3 基本報酬の引き下げによって、地域の在宅介護を支える小規模・零細事業所は人手不足も相まって経営難に陥り、独居高齢者などの地域での生活を支える介護事業の基が崩壊する恐れがある。4 地域での在宅介護が成り立たなくなると、介護離職の増加や孤独死などの社会問題が深刻化することが予想され、黙認することはできない。よって本請願の趣旨に賛同し、採択を主張する。5 なお、認められない場合は「継続」を主張する。 |
| 第22号 | 高等教育の学費無償化に向けた教育予算の拡充を求める意見書提出の件 | 採択に賛成(継続) | 1 高等教育は未来への投資であり、大学、高専、専門学校等の学生は、将来の日本の発展に大きな原動力となる世代である。2 しかしながら、高等教育の授業料は高止まりしており、物価が高騰している中、子育て家庭における高等教育の学費は負担となっている。3 また、大学(昼間部)に通う学生が何らかの奨学金を受給している者の割合は、約半数と若者の将来にも影響を及ぼしている。4 将来を担う若者が本分である勉学に集中できる環境になるよう、国において、全国一律に高等教育の学費無償化等の対策が必要と考える。よって本請願の趣旨に賛同し、採択を主張する。5 なお、認められない場合は「継続」を主張する。 |
| 第24号 | 兵庫県が削減した令和7年度医師臨床研修病院の研修医募集定員を、令和8年度は「0」から「2」以上に増員を求める件 | 採択に賛成(継続) | 1 県内臨床研修の充実のためにも、県内中小病院や研修定員の少ない病院においても地域医療の実際を学ぶことは重要であり、医師臨床研修病院全てに募集定員を設定することは必要であると考える。2 一方、国が配分する本県の募集定員は年々減少が続いており、特に令和7年度は、特例加算の廃止等により、令和6年度に比べ、10名の減少となっている。3 国に対して、特例加算の復活を求める提案を行うとともに、定員の増員を求めていくことは、非常に重要である。4 以上のことを踏まえ、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。5 なお、認められない場合は「継続」を主張する。 |
| 第26号 | PFASの実態把握の徹底検査をし、国に基準見直し、対応策を求める件 | 採択に賛成(不採択) | 1 PFASの一部は半導体の生産等に使われ、発がんの可能性がある物質として、健康への影響が指摘されている。 市民団体である「明石川流域のPFAS汚染を考える会」が周辺住民に実施した血液検査の結果、約半数がアメリカの血中濃度指針値を超えており、「健康被害が懸念される」と検査結果をまとめている。2 「水道水を飲料水として利用している方は数値が高い傾向にあり、浄水器を使う人は低かった」という結果もあり、汚染源の特定調査が急がれると同時に、水道供給のあり方についても健康の観点から早急に検討する必要があると考える。3 県議会では、令和6年2月第366回定例会において「PFAS対策の推進を求める意見書」を全会一致で採択しており、全国各地でこの問題への対応が迫られている。4 国においても実態調査地点の拡大を踏まえ、「PFASに対する総合戦略検討専門家会議」や「食品安全委員会」等で基準値の設定や対策が検討されていることから、請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。5 なお、認められない場合は「継続」を主張する。 |
| 第31号 | 選択的夫婦別姓を直ちに導入することを求める意見書提出の件 | 採択に賛成(不採択) | 1 選択的夫婦別姓については、1996年に法務大臣の諮問機関である法制審議会から導入を提言され、これを受けて法務省は、1996年と2010年に国会への提出を目指したが、いずれも提出が見送られている。2 一方、姓を変更するのは、大多数が女性で、「改姓によりキャリアが中断する」、「結婚・離婚の際に姓変更の手続きが煩雑であり、精神的・身体的ストレスが生じる」などの声もあり、不利益が生じており、経済界から導入に前向きな声が上がり、厚生労働省の調査でも賛意の広がりが明らかになっている。3 また、若年層を中心とした一部では「別姓を選べないことで、結婚を諦めたり、事実婚にした」といった声もあり、特に女性が苗字を変えることが多い現実や、苗字が変わることによる手続きの発生が結婚に対する障壁にもなりかねない。4 以上のことを踏まえ、本請願の趣旨に賛同し、「採択」を主張する。 |
| 第32号 | 2024年度の障害福祉サービス等の報酬改定の撤回及び再改定に関することを求める意見書提出の件 | 不採択に賛成(不採択) | 1 物価高騰、人件費の上昇が続く中、今年度の障害福祉サービスの報酬改定については課題が大きいことは認識している。2 もともと人件費水準が低い中で、今回の改定率が+1%程度となっており、多産業の平均賃金改定率と比べて低く、さらに業界全体での人材不足や経営不振が惹起される恐れがある。3 しかしながら今回の報酬改定では、全面的な報酬減額ではなく、増収となっている事業所もあると聞くため、即時撤回と再改定を行うことは現実的に困難と考える。4 制度の持続可能性を確保しながら、障害福祉サービスの充実を図っていくため、早急に改定による影響を調査検証すべきと考えるが、即時撤回を求める請願の趣旨に賛成することはできない。5 以上のことから、「不採択」を主張する。 |
| 第33号 | 教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちに行き届いた教育を求める私学助成に関する件 | 不採択に賛成(不採択) | 1 私立学校は、各々建学の精神に基づき特色ある教育を展開し、公立学校とともに公教育の一翼を担ってきたところであり、あらゆる生徒の就学機会を確保するためには、私立学校の維持発展が欠かせない。2 現在、国では、私立学校の教育環境の維持向上や保護者の教育費負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図り、各学校の特色ある取組を支援するため、都道府県による経常費助成等に対し補助を行っている。3 保護者の深刻な学費負担を軽減するとともに、私立学校が新しい時代の要請に応えていくためには、私立学校への一層の支援充実が求められる。我が会派としても、これまで年収590万円以上世帯への補助の充実を求めてきたところである。4 しかしながら、県の厳しい財政状況の中、世帯年収に応じた段階的な支援については一定理解するところであり、所得制限のない授業料無償化に向けた取組においては、まずは国が推進すべき政策である。5 よって、現時点においては、本請願に対して賛同することができず、「不採択」を主張する。 |
| 第34号 | 障害児の豊かな教育のための条件整備を求める件 | 継続に賛成(継続) | 1 障害のある子供たちが、豊かな教育を受けられるよう教育環境の充実を求める請願の趣旨については、概ね理解できる。2 県では、これまでも「兵庫県特別支援教育推進計画」に基づき、学校の新設や建替え、老朽化した施設や設備の改善に加え、寄宿舎を置く学校においては赤外線センサーライトや防犯カメラの設置、交通事情にあわせたスクールバスの選定など改善を行ってきた。3 しかしながら、教育環境の充実を図るには大きな財政的負担が必要となる。そのため、特に義務教育段階においては、日本全体における教育環境の公平性も考慮した上で、国が財政支援を行うべきである。4 今後、国の予算の状況を踏まえて、さらなる支援の充実が必要であるか判断する必要があることから、本請願については、「継続」を主張する。5 なお、継続が認められない場合は、状況を的確に見極めて判断する必要があることから、現時点において直ちに本請願の趣旨に賛同することはできず、「不採択」を主張せざるを得ない。 |
| 第35号 | 全ての子どもたちへの行き届いた教育を目指し、35人以下学級の前進、教育費の軽減、教育条件の改善を求める件 | 不採択に賛成(不採択) | 1 現在の学校現場の状況を見ると、子どもたちの基本的な生活習慣、規範意識、学習意欲・態度などに課題があり、いじめ等の問題、指導が困難な児童生徒や特別支援教育の対象となる児童生徒への対応など、子どもたち一人一人に目の行き届いた指導を行うことがより一層求められている。2 文部科学省の調査(「今後の学級編制及び教職員定数の在り方に関する国民からの意見募集」)では、小中高生の保護者の約8割が30人以下の学級規模を求めており、少人数学級を望んでいる。3 我が国の教育環境は、個別の教育課題に対応するための教職員配置の充実により改善されてきているものの、1学級当たりの児童生徒数は国際的に見て依然低い水準である。(小:日本27人 OECD平均21人 中:日本32人 OECD平均23人)4 一方、学級の規模については、20人以下であると少なすぎると約半数の教員が感じたとする意識調査もあり、また、「社会性の育成」の観点からも「20人学級」が適正であるかどうか、十分な検証が必要であり、県としては、こうした検証結果を注視して判断する必要がある。5 県立高校の統廃合については、少子化に伴う生徒数減少による学校規模の縮小が、高校での多様な学びに支障を来している中、複数の学校の特色・伝統を継承しながら更に発展させ、学校規模を大きくすることで、多様な学びや活動の機会を保障し、高校生が成長し自己実現を果たせる魅力と活力ある高校の教育環境を確保するために推進している。6 全ての子どもたちの教育環境の充実を求めるという請願趣旨については概ね理解するものの、県立高校の統廃合凍結等の内容が含まれていることから、本請願の趣旨には賛同することはできず、「不採択」を主張する。 |
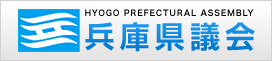
県議会ホームページでは、すべての議案に対する会派態度をご覧いただくことができます。(別ウィンドウが開きます)