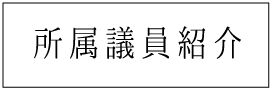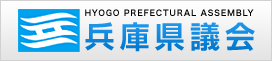ひょうご県民連合議員団の小西です。
会派を代表し、ただいま上程中の第95号議案「特定調停及び債権の放棄」に対し、反対の立場から討論をおこないます。
兵庫県森林組合連合会(以下、県森連)への貸付金9億900万円について、調停案では、保有する林業会館等を売却するなどして工面した県への確定弁済額約2億7,300万円、それを控除した残額の債権約6億3,600万円すべてを放棄するという内容は、税の負担者でもある県民の不利益につながる重大な内容にもかかわらず、十分な説明もないまますすめられることに強い懸念を抱きます。以下、3点について反対の討論をおこないます。
まずは、この間の融資のあり方と県森連の経営責任についてです。
2019年度の県森連への貸付時に前年度の4億円から7億円に増額されていますが、当初計画にはない増額です。県森連側からの働きかけがあった可能性があります。また、農林⽔産部は県森連が2018年度末に農林中金からオーバーナイト融資を受けている事実を知っていたはずです。さらに、知事や財政当局に2021年度末まで報告しなかったこともその理由が理解できませんし、財政当局も2021年度の包括外部監査の段階でオーバーナイト融資があり、相当に厳しい経営状況が指摘され、そのことを把握していたにも関わらず、2022年度当初におこなった9億円もの貸付をなぜ、知事が中止の指示をしなかったのか、理解できません。
2020年度予算の査定資料からは、この時点で既に「破綻」ということばもみられます。それでも増額した上で貸し続けた理由も理解できません。
その結果、2022年11月29日に県森連は大阪地方裁判所に特定調停を申し立てており、結局9億円は返還されないままです。県森連の非常に厳しい経営状況を把握しながら、単年度融資を増額・継続し、結果として9億円が回収できない現状と責任を県としてどう考えるのでしょうか。
また、過去に県森連において、役員報酬が支給されていた方々の経営責任について、その報酬の返還も含めて、6億円という大きな額の債務を返還する努力が十分になされていたのか県としての認識が不透明です。
県森連が特定調停を申し立てる約1ヶ月前の10月13日に「ひょうご森林林業協同組合連合会」(以下、森林連)の設立登記が確認されており、その設立目的や代表理事が県森連とほぼ同じでありました。
県が県森連に委託してきた事業は、2023年1月5日に森林連に事業移管されていますが、「随意契約」により移管されたのは優良事業ばかりです。
さらに、県森連のこの間の経営責任について、代表者らが記者会見等を通じて説明をしたことは一切ありません。民間企業であれば株主をはじめ、顧客・取引先のほか、金融機関、行政機関、各種団体など、あらゆる利害関係等であるステークホルダーとよばれるみなさんに説明する責任があります。
これまでの本会議や決算・予算委員会、常任委員会では、お金を貸している側の県当局だけが説明をしています。お金を借りている県森連から、県からの貸付金を返還しない、返還できないことを直接、県民に説明すべきです。これらの経過をふりかえってみますと、改めて県民や県議会に対しての説明がなかったことはたいへん大きな責任があると考えます。
次に、6/11の農政環境常任委員会で我が会派の黒田議員からも指摘しましたが、兵庫県林業会館の今後のあり方について、なぜ、林業会館を公募の上、売却をしてその原資を返済に充てなかったのかという問題です。
常任委員会において、会館を譲渡する相手について、明確なお答えはありませんでしたが、登記簿上での所有者は、土地の按分で一般社団法人兵庫県治山林道協会81.41%、兵庫県木材業共同組合連合会14.16%、兵庫県林業種苗協同組合4.43%となっています。建物は建てられたばかりで、法的な減価償却の考え方でも残存価値はあるにもかかわらず、無償譲渡は誰が見ても違和感を覚えます。林業会館を公募の上、売却をしてその原資を返済に充てるべきではないのでしょうか?これらの重要な課題について、なぜ、外部調査による売却資産の最大化をはかり、県負担、県民負担を少なくするための努力をしなかったのか?県からの明確な説明はありません。
また、主な区分所有者である治山林道協会の会長は、県森連の会長と同一人物であり、この状況は利益相反の関係でもあり、断じて認められません。特定の人・団体が仲間うちで利益を得て、債権放棄にともない、県民が不利益となることは、県民感情からも納得いくものではありません。
最後に、県森連が厳しい経営状況になった理由についてです。
これまでの本会議等における質問に対する答弁では、「2021年からのウッドショックの影響による⽊材価格の異常な高騰、2022年からのウクライナ情勢によるロシア材の輸出禁⽌を起因にする木材価格の高止まりといった経営計画の策定時には予期しえなかった急激な外部環境の変化が生じたこと」とありました。
しかし、県民も状況は同じであり、現在も物価高騰による影響が大きく、予期しえなかった急激な外部環境の変化があったとしても、何とか家計をやりくりして、我慢もしながら生活しています。物価高だから、外部環境が変化したからと言って、例えば住宅ローン等の借り入れがなくなるわけではありません。人が生きていく上で、やむを得ず生活が破綻する場合もありますが、多くの県民は何とか工夫しながら、必死の想いで日々生活をしています。
お金を借りたくても借りることが叶わない県民も多数いるなか、大きな金額の債権を放棄する場面で、十分な説明がない状況での賛成はできません。
これまでの当局の説明や本会議等における我が会派の議員からの質問に対する答弁、6/11におこなわれた農政環境常任委員会の議論からも県森連による事業譲渡、その他の資産処分、弁済計画案の内容に対して、いずれも相当性や合理性を認めることはできません。
議員のみなさまにおかれましては、何とぞご賛同いただきますようお願いを申し上げ、ひょうご県民連合議員団を代表しての討論を終わります。
ありがとうございました。