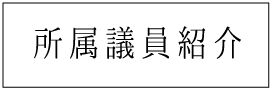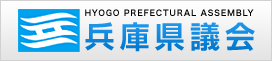質 問 日:令和6年12月9日(月)
質 問 者:黒田 一美 議員(ひょうご県民連合)
質問形式:一問一答

1 出勤率の概念を取り払い、職員のワーク・ライフ・バランス並びに行政サービスの向上について (総 務)
齋藤知事は、県本庁職員4割出勤を実施するとしていたが、令和5年度決算特別委員会部局審査において、当局は、「モデルオフィスの繁忙期の検証結果で、繁忙期のピーク時には、9割弱の出勤率になった。」と答弁している。
厚生労働省のガイドラインでは、「実際にテレワークを行うか否かは、本人の意思によることとすべき」と明記している。
先の決算特別委員会総括審査で、知事職務代理者の服部副知事は、「庁舎のあり方等に関する検討会の有識者からも、先に出勤率を設定すると働き方が制約されるため望ましくないとの意見も出ており、今後は出勤率という概念を取り払い、職員のワーク・ライフ・バランス向上や行政サービスの向上の観点から議論を進めて行きたい。新しく就任される知事のもと、方向性を示して行きたい」と答弁している。
あくまでも、職員の出勤率は、服部副知事の決算特別委員会における答弁のとおり、出勤率という概念を取り払い、厚労省のガイドラインのとおり職員本人の意思によることとするべきであると考えるが、新しく齋藤知事が就任された今、どのように考えるか、所見を伺う。
2 県教育委員会をはじめ、行政機能を集約する県庁舎のあり方について (総 務)
すでに、県教育委員会事務局が県本庁舎から離れた神戸市東灘区に移転し、私たち議員と教育委員会事務局職員とのレクチャーに不便が生じている。また、知事部局との連携に不便が生じている。
このことについて、先の決算特別委員会総括審査において有田総務部長は、「物理的な距離が離れることにより、課題が生じる可能性があるということは、私どもとしても十分に認識している。」「3号館の工事終了後の令和8年5月を目途として、暫定的な庁舎再編に向けて、全庁的に順次移転に着手していくことも検討しているところ。」「対面でのコミュニケーションも大事ということで、部局間連携が円滑に行えるよう工夫、研究し、課題に対応していく。」「その上で新たに就任される知事のもとで、将来的な県庁舎の整備方針を検討するに当たっては、できる限り本庁舎の機能を集約することに意を用いて、県庁舎のあり方を検討していきたい」と答弁している。
新しく齋藤知事が就任したが、この方針には間違いがないか。教育委員会事務局を、本庁舎周辺に機能集約する必要があると考えるが、所見を伺う。
3 兵庫県立大学生のみの授業料無償化だけでなく、県内全ての若者への支援について (総 務・企 画)
私は、兵庫県内全ての若者への支援は、非常に大切であると考えている。
齋藤知事は、兵庫県の若者の支援の一環として、ごく少数の兵庫県立大学生のみの授業料等を無償化し、今後、毎年約20億円(20.8億円)もの多額の県予算を使用する事業を実施した。
令和5年3月に高校を卒業して兵庫県立大学に進学した県内の若者757人が授業料無償化の支援の対象となるが、同じ令和5年3月に高校を卒業した県内の若者は、4万1,408人であり、圧倒的多数が私立大学や各種専門学校、就職へと進んでいる。この圧倒的多数である若者への支援が示されていない。
また、令和6年3月で中学校を卒業した後、高校へ進学せず、就職や専修学校、職業訓練施設へ進んだ若者は兵庫県内で718人となっている。兵庫県立大学へ進学した757人とほぼ同数であり、このような若者への支援も同様に行われるべきであると考える。
若者・Z世代応援パッケージとして、兵庫県内の全ての若者への支援が行き届く事業の展開を望むが、当局の所見を伺う。
4 兵庫県における感染症の拡大防止対策について (保 健)
新型コロナウイルス感染が一定落ち着き、感染者数の全数報告が終了し、定点当たりの数値が発表されるようになってから1年7ヵ月となり、徐々に新型コロナウイルスをはじめ、感染症に対する意識が薄れつつあるのではないかと危惧する。
しかしながら全国的に見ると、今年度、子どもを中心に流行的発生が見ら れた手足口病やマイコプラズマ肺炎は、成人にも感染しているとの情報も聞く。また、インフルエンザの定点当たりの報告数が流行開始の目安である「1」を上回り、流行シーズンに入ったとの情報もある。さらに、新型コロナウイルス感染症については、例年、冬にかけて感染者が増加する傾向が見られるなど、予断を許さない状況となっている。
特に高齢者や基礎疾患のある方が感染すると、重症化するリスクが高まることから、我々個人としても日ごろからの感染症予防が必要であることは、言うまでもないことである。
新型コロナウイルス感染症のように兵庫県全体に感染が広がり、医療がひっ迫するなど、混乱が生じた経緯もあり、感染症の感染拡大防止の策を講じることが必要であると考える。
そこで、兵庫県において、感染症が発生した際の周知や調査など、どのように拡大防止に取り組んでいるのか、当局の所見を伺う。
5 来年のいかなご漁獲量向上への取り組みについて (農 林)
いかなごは「瀬戸内海の春告魚(はるつげうお)」とも言われ、特にシンコ(新子)と呼ばれる稚魚を対象とした船びき網漁業は、兵庫県瀬戸内海における重要な漁業のひとつです。
いかなごのシンコをしょうゆや砂糖で甘辛く炊いた「くぎ煮」は瀬戸内の郷土料理であり、県民は例年2月末から3月上旬に解禁されるいかなご漁を今か今かと待ち望んでいる。来年で30年を迎える阪神・淡路大震災が起きた時、被災地のいたるところでいかなごの「くぎ煮」の匂いが漂い、元気づけられたことを思い起こす。
兵庫県立農林水産技術総合センター水産技術センターでは、漁業者だけでなく消費者へのいかなご漁のPR等を目的に、毎年の操業見込みについて予報を出しているが、近年は、下水道の普及で海へ流れ込む窒素などが減る栄養塩類不足により、餌になるプランクトンが育たないことに加え、地球温暖化による海水温の上昇による影響も心配されており、漁獲量が大幅に減少している。
このため、漁業者は、海底耕うん、ため池のかいぼり、肥料を用いた海への栄養塩類添加試験などを実施しているほか、翌年の親魚資源の確保に向けて、例年より早めの終漁日を設定し、取り組んでいるものの、厳しい状況が続いている。
令和6年漁期の操業日は、試験操業の結果が低調であったことなどから、翌年度の資源を残すため、関係漁業者の協議により、大阪湾海域は、自主休漁、播磨灘海域は、3月11日(月)の1日のみの操業で終漁となり、県民にとっていかなごは、手に入りにくい状況となっている。
近年、不漁が続く中ではあるが、資源管理に取り組んでいる漁業者や、春の風物詩を楽しみにしている県民のためにも、いかなご漁獲量の向上が期待されるが、来年のいかなご漁獲量向上への取組について、当局の所見を伺う。
6 温暖化へ向けた水稲の品種改良をはじめとする農作物の高温対策について (農 林)
近年、地球温暖化の影響により、記録的な猛暑や豪雨が観測されるなど、異常気象とも言うべき状況が続いており、米や野菜、果樹など農作物の生育や品質に悪影響を及ぼすことで、スーパーなどでの小売価格の変動が大きく、県民は家計への圧迫を心配している。
県では、加西市にある兵庫県立農林水産技術総合センターで、農作物の温暖化対策として、水稲では、高温に強いオリジナル品種の育成に取り組み、令和7年度には新たな品種がデビューするとのことである。また、と高温の時期が重ならないようにするため、田植え時期を遅らせたり、地温を下げるための水のかけ流しなどの水管理、高温で肥料成分の溶出が早まることによる肥料不足を補うための追肥などの栽培技術の改善にも取り組んでいる。
さらに、ピーマンでは夏期の土壌水分不足による品質低下やを防ぐための日射量に応じた自動装置による適切な水管理、カーネーションの施設栽培では切り花の品質向上につながる夏季の日没後の短時間冷房などの取組を支援するなど、さまざまな取組が行われているところである。
今後も深刻化する地球温暖化に向けて、夏季の高温等に対応した安定的な農業生産を行うためには、水稲の品種改良をはじめとする農作物の高温対策に更に力を注いでいく必要があると考えるが、当局の所見を伺う。
7 若手警察官の獲得に向けた兵庫県警の魅力アップのための警察学校の整備充実について (警 察)
兵庫県警察学校では、新たに採用した警察官に対し、警察庁から示された教授科目等に基づく、職務倫理、憲法・刑法などの法学、捜査・交通等の基本実務、柔道・剣道・逮捕術等の術科の教育訓練により、地域警察官としての基礎的な現場執行力を身に付けるための教養が全寮制で実施されている。
とりわけ、兵庫県警察学校の訓練は日本一厳しいとも言われており、「根性坂」と言われる坂での訓練は有名である。
日々、職務を遂行できる力強い警察官を育成するための取り組みが行われていることに敬意を表するものである。
このような厳しい訓練に臨む若手警察官にとって、警察学校入校中の寮生活環境は、日々の訓練による疲れを癒やし、また明日への活力を養うために重要な役割を果たすと考える。
今年度の警察常任委員会管内調査において、警察学校を訪れ、実際の訓練の模様や施設を見学し、関係者との意見交換を行ったが、その際に私が感じたことは、特に居住空間における壁紙や床、ベッドのマットレスなどの老朽化が顕著であることから、若手警察官にとって十分に安らげる環境とは言いがたいのではないかと感じた。
今後、警察官を希望する若者に対して、兵庫県警察に就職することをお勧めできる環境であってほしいと願うものである。
社会のシステムが急速に変化する中、公共の安全と秩序を維持していくためには、社会の変化に柔軟に対応できる優秀・有用な警察官の育成が重要であり、若手警察官を獲得していくためにも、警察学校の寮生活環境を向上し、兵庫県警の魅力をアップさせる必要があると考えるが、当局の所見を伺う。