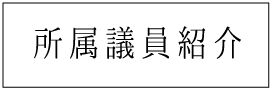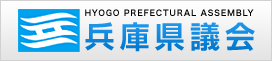平成25年2月 第317回定例県議会 一般質問要旨案
質 問 日 : 平成25年2月26日
質 問 者 : 盛 耕 三 議員
質問形式 : 分割方式
1 業務量の把握と適正な職員数について
最初の質問は、「業務量の把握と適正な職員数」についてです。
県では、行財政構造改革に伴い平成30年度には平成19年度を基準として30%を目標に職員数の削減を図るとしており、今年度時点で基準年度に対し正規職員1,637人19.8%の削減となっている。
一方、基準年度に対する今年度の非正規職員数の比率を見たところ、臨時的任用職員数は38.8%、非常勤職員数は97.0%、日々雇用職員数は87.5%にそれぞれ減少、雇用対策に係る若年者等の雇用については131.9%に増加した結果、非正規職員全体としては92.1%に減少しており、正規・非正規の合計人数では82.5%に減少しております。
このような現状を踏まえ、以下2つの視点からお尋ねします。
まず1つ目の視点は、「業務量の把握」についてです。
年度当初の予算規模(一般+特別+公営企業)を比較すれば、平成19年度の3兆6,058億円に対し今年度は3兆2,377億円と89.8%となっております。
必ずしも業務量が予算規模に連動するとは言えませんが、仮に業務量が予算規模に比例すると考え、職員1人あたりの負担を増やさないとするならば、職員の削減比に合わせて、平成30年度には予算規模も70%とすることが求められますが、来年度当初予算(案)とともに示された財政フレーム(事業費ベース)によれば、平成19年度に比べた平成30年度の歳出規模は104.7%となっており、今後、職員削減により1人あたりの業務量はますます増えていくと予想されます。
ところで、皆さんもご存じだと思いますが、工場などの製造現場を持つ企業においては、前年度の実績から、直接製造に関わる作業員の1時間当たりの人件費(時間等価単価)を算出して、それを基にした工賃を見積金額に反映し受注競争に臨みます。
また、利益を出すため、コストダウンの一環として製造に要する時間を減らし、製造原価を下げる努力を惜しみません。各製造工程の作業時間を的確に把握するため、作業員自らが作業標準を作り作業内容の見直しを行うことが当然とされています。これにより受注製品の製造工数を計算することができ、納期に間に合わせるために、どの作業にどの程度の作業員を投入すれば良いかを把握することが出来るのです。
これに対し、設計など製造部門の間接要員には作業標準が無いものの、各工程に間に合うように事務や交渉などをこなさなければならず、担当者やその上司は、事前におおよその必要時間を把握して必要であれば要員の増員を要請します。
このように民間企業では作業時間の把握は当然とされております。
私は、行政においても、職員の健康管理を行うとともに効率的な事務執行や人員配置を行う観点から、これに倣い、それぞれの業務について業務量を定量的に把握するとともに、その執行に必要な業務時間を算定するための全庁的な業務標準を作成すべきだと考えますが、いかがでしょうか。
2つ目の視点は、「適正な職員数」についてです。
業務量とそれに対する必要時間を定量的に把握することが出来れば、これを基に業務執行に必要な職員数を導き出すことが出来ます。
先ほど述べた平成30年度における職員数の削減比70%と財政フレームでの歳出規模の増104.7%から単純計算すれば、1人あたりの業務量は約1.5倍に増える計算となります。
このように今後も増え続けるであろう業務の見込み量から考えると、非常勤職員数について、仮にこれまでと同様、今後も減らしていくとすれば、正規職員の負担を増やすしかありませんが、それには限界があると考えます。
職員の負担が限界を超える部分について、非常勤職員の増で対応する、指定管理者を含めた民間へ委託する、あるいは、市町への権限移譲を実施するなどの方法も考えられますが、いずれの場合であっても、その業務に要する職員数をほぼ正確に把握しておく必要があるのではないでしょうか。
そこで、県として、正規職員の定数を定めるにあたってどのような基準に基づいているのか、現在の職員数は適正なものだと認識しているのか、また、来年度の第2次行革プランの見直しに当たり、平成30年度までの定員削減計画も見直す予定はあるのかについて、1つ目の視点に対するご見解も含め、知事のご所見をお伺いします。
2 安心して子供を産むことが出来る環境整備について
2番目の質問は、「安心して子供を産むことが出来る環境整備」についてです。
私の住む相生市では、平成12年11月に最後の産婦人科医院が産科の診療を止めてから、市内で子供を産むことが出来なくなりました。また、近隣の赤穂市民病院産婦人科の医師不足により、平成20年4月から平成23年6月までの間、同病院での新規の受診及び分娩は赤穂市民及び同市内に里帰りされた方に限るとされた時期がありました。
自分が住む場所あるいは親元で、安心して子供を産むことが出来るかどうかは、出産に思いを巡らせる世代にとっては大変重要なことであり、住まいを定める際に考慮する重要ポイントの一つにもなっています。
そこで、以下2点についてお尋ねします。
(1) 産科の地域偏在について
まず1点目は、「産科の地域偏在」についてです。
県内の各医療圏域における現状を比べてみると、産婦人科医の人数では、人口10万人あたりの人数は、神戸圏域が但馬圏域の2.2陪、面積100㎢あたりの人数は、阪神南圏域が但馬圏域の154倍となっています。また、産婦人科の数についても、人口10万人あたり及び面積100㎢あたりの数は、ともに、阪神南圏域が但馬圏域の2.7倍、194倍となっています。
県では、このように大きな地域偏在があることについては十分認識をしておられるとのことですが、その原因は、そもそも産科医の人数が少ないことに加え、出産数が少なくなり産科の経営が成り立たず、病院や医院が産科を廃止することなどもその要因の一つとなっていることはご存じの通りであります。
加えて、産科医特有の勤務環境・条件の悪さや近年多くなってきた医療訴訟への抵抗感などから、産科医を目指す医師が少なくなったことも、産科の地域偏在に拍車をかけています。麻酔科や脳外科でも同様ですが、医師が少なくなった病院では、ローテーションもままならず、残された医師にますます負担が掛かり、耐えきれずに辞めていくにもかかわらず補充が出来ない、という悪循環に陥っています。
そのような現状に鑑み、県は、産科医が不足している圏域においては、限られた産科医を集約し拠点病院へ配置することで、個々の産科医の負担を減らし、産科の存続を図っており、その取組自体は十分に評価ができます。
ただ、このことは面積が広い圏域においては、もともと点在していた産科医院や病院がもっと少なくなることを意味し、地元あるいはその近くでの出産をますます困難にさせることにつながります。このような環境では、若い世代は結婚して新居を構える場合、地元を選ぶことを躊躇せざるを得ないと推察できます。
しかし、県民福祉の向上と安全・安心な生活を守るべき我々としては、このような状況を憂いて、手をこまぬいてばかりはおられず、こうした地域偏在の是正を図っていくことが強く求められます。
そこで、県として、これまで産科の地域偏在の是正をどのように進めて来られたのか、また、今後、いつ頃までに偏在を完全に解消させることを目指し、どのように取り組んでいくのか、当局のご所見をお伺いします。
(2) 助産所の設置促進について
2点目は、「助産所の設置促進」についてです。
仮に産科の地域偏在の完全解消が困難であるとしても、県として何らかの代替的な手立てを打つ必要があります。それは、県として果たすべき県民の方々に対する義務でもあります。
私は、その最も有効な手立てとして、助産師をもっと積極的に活用していくべきだと考えます。つまり、現在、県が推進している病院内助産所の設置支援に加え、産科の開業が望めない空白域において病院外助産所の設置を積極的に促進していくことで、県民の要望に県として、より応えていくことが出来ると考えます。
ただ、助産所が増えていかない現状には、多くの課題があります。助産師の方のお話では、最も大きな課題は、連携病院を見つけることとのことですが、何故、連携を取ってもらえる病院がなかなか現れないのでしょうか。
産科医からすれば、重篤な妊婦を急に連れて来られても、処置をするのに大変な苦労がある。加えて、もしもの時には、産科医が責任を問われる。正常分娩のみを扱う助産所の乱立は、産科の経営を圧迫しかねない等の思いがあるでしょう。
一方、助産師からすれば、妊娠中の検査は連携病院を受診させるなど連携病院とは常に意思疎通を図ることができる。故に異常な状況は事前に判明し、適切な処置をすることで異常分娩になる割合は非常に少なくなる。また、病院ではなかなか出来ない産前産後の心身両面からの細やかなケアを行えるなど、助産所には大きなメリットがある等の思いがあるでしょう。
このように、それぞれの主張があるとは思いますが、助産所の設置を促進し、助産師の積極活用を図っていくためには、まずは産科医と助産師の間における信頼関係を築いて行くことが必要です。産科医と助産所は、相互に補完し合うことで、今以上に様々な課題に対応していくことが出来ると私は考えます。
そこで、今後の方向性として、病院内のみならず病院外も含め更なる助産所の設置促進へ向けて、産科医と助産師とがお互いに補完関係になることが出来るような政策を推し進めていくことが必要だと考えますが、当局のご所見をお伺いします。
3 中学校のクラス内における人間関係について
3番目の質問は、「中学校のクラス内における人間関係」についてです。
「いじめ」、特に学校現場における「いじめ」ということが、1980年代半ばから、社会問題として報道機関等で大きくクローズアップされ始めました。
それ以降、多くの方々が検証を重ね、問題解決のために様々な取組がなされていますが、状況は酷くなるばかりだというのが、多くの方の見方ではないでしょうか。
県教育委員会においても、他人を思いやる心や人間性豊かな心の育成を図るとともに、スクールカウンセラーによる相談業務を始め、いじめを予防するための様々な取組を行っています。これまでの取組そのものについては、私も評価しておりますが、どこまで効果が出ているのかは疑問を感じています。
以上のことを踏まえ、以下2点についてお尋ねします。
(1) スクールカーストについて
1点目は、「スクールカースト」についてです。
同学年の児童や生徒の間で共有されている「地位の差」としての「スクールカースト」について、東京大学社会科学研究所の鈴木翔氏は、生徒側の捉え方として、『スクールカーストで上位グループに位置する生徒の特徴は「人気者で気が強い」。下位グループに位置する生徒は特徴がなく、強いて言えば「地味で目立たない」。下位グループは、クラスに影響力を持つ上位グループに恐怖心を抱いており、この地位は固定的で、クラス替えがあったとしても、努力では変えられない。上位の生徒と下位の生徒が同じことをしても、教師の反応が違うと捉えている』と分析され、これらのことから、『生徒側は、スクールカーストを「権力による序列」と捉えている。』と説明されています。
その一方で、教師側の捉え方を『上位と下位の生徒の特徴こそ生徒側と同様に感じているが、スクールカーストを、積極性、生きる力やコミュニケーション能力といった「能力」による序列だと肯定的に捉えている。』と分析され、『スクールカーストの中で、自分の「能力」の足りない部分に気づき、「努力」や「やる気」を通じて社会性を身に付けることで、この序列は改善可能と捉えている。』と説明されています。
仮に、これらの分析が事実であるとするならば、この「スクールカースト」が一人ひとりの生徒に与える影響には計り知れないものがあります。すなわち、一つには、スクールカーストの中で下位に置かれた生徒は、クラスメイトから身分の低い目下の存在だと見なされて、いじめの標的になりやすくなること、二つには、たとえいじめに遭わなくとも、クラスが居心地の悪い場所となるばかりか、自分に自信を無くし、学校生活への適応だけでなく、将来にわたり大きな影響を及ぼす恐れさえあります。
にも関わらず、いじめのように問題が顕在化しない限り、クラス内における生徒の人間関係は、大人の間では「ささいなこと」とされ、これまで解明すべき重要な問題として捉えられてこなかったと思われます。
しかし、近年、学校現場で頻発しているいじめ問題の大部分は、この「スクールカースト」の存在が大きく影響していると考えれば、非常に的確な分析と説明ができるのではないでしょうか。
そこで、これまであまり重要視されて来なかったクラス内における生徒間の人間関係について、平時から、市町教育委員会とも連携し、個々の教師一人ひとりがその状況を把握できるよう積極的に支援していくとともに、県教育委員会としても、その現状について、より正確に把握しておくべきだと考えますが、当局のご所見をお伺いします。
(2) いじめの背景としてのスクールカーストについて
2点目は、「いじめの背景としてのスクールカースト」についてです。
先程紹介した鈴木翔氏は、いじめとスクールカーストの関係について、『日本におけるいじめは、絶対的な優劣関係が生じやすい縦のつながりの場面ではなく、同じ学年の児童生徒が集められた教室で多く起こるが、自他ともにはっきりと認識できる定義通りのいじめは、実はかなり少ない。教室という閉じた空間で大部分の時間を過ごさなければならない日本の学校は、効率的に知識を伝達しやすいという利点がある一方で、本人に隠れて悪口を言う、くすくす笑う、無視するといった、「コミュニケーション操作系」と言われるいじめを生み出しやすいという副作用を持つ。いじりや悪ふざけなどを含め、こうした「いじめのようなもの」は、ささいなことと見逃されがちではあるが、それがいじめと認識されるか否かに関係なく、行為それ自体を対象として検証する必要がある。「スクールカースト」はそのような状態により近い現象である。』と分析されております。
県教育委員会では、今年度の新規事業で、「他人を思いやる人間性豊かな心」を育むため、「学級経営指導員」として教員OB5人を小中学校へ派遣し、若手教員を中心に指導力向上を図るとともに、高校40校において「いじめ対策教育に関する実践」を実施するなど、いじめ防止に向けた取組を強化されています。
しかし、言うまでもなく、それらの施策が十分に効果を発揮するためには、現に起こっている事柄を十分に把握することが必要であります。つまり、どのようなことであれ、根本的な解決を図るためには、その原因ないし背景を綿密に分析・検証し、これに的確に対処していくことが肝要であります。
そこで、来年度、県立教育研究所の心の教育総合センターにおいて、大学等の専門機関と連携していじめ問題に関する研究を推進するとされていますが、その研究の中で、学校現場でのいじめ根絶を目指し、いじめの原因ないし背景としての「スクールカースト」の現状についても分析・検証を行い、有効な対策を検討していくべきと考えますが、当局のご所見をお伺いします。