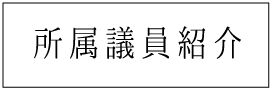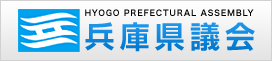決算特別委員会
理 事 橋本 成年 議員(宝塚市)
委 員 黒田 一美 議員(神戸市垂水区選出)
橋本 成年 議員
財政状況 | 企画部・県民生活部・部外局 | 福祉部 | 公安委員会 |
黒田 一美 議員
総務部・財務部・危機管理部 |企画部・県民生活部・部外局 | 産業労働部 | 土木部 | まちづくり部 | 教育委員会 |総括審査
<橋本 成年 議員>

●財政状況
1 県財政状況の認識について
2 県債管理基金への基金集約の解消による令和5年度決算への影響について
(1)基金集約の解消によるメリット・デメリットについて
(2)基金集約のメリットがなくなることの影響について
(3)財政基金への積み立てを県債管理基金への積み立てより優先する意図について
3 農林水産資金特別会計のあり方について
4 中小企業高度化資金について5 短期貸付金におけるオーバーナ
イトの防止について
全文
1 県財政状況の認識について (財政課)
本県は、阪神・淡路大震災の影響もあって実質公債費比率、将来負担比率などの財政指標、財政基金や減債基金といった主要基金の積み立て状況から見ても、厳しい財政状況だと言われてきた。
また、地域整備事業、分収造林事業など、いわば含み損とも言える将来的な財政負担も踏まえると、余裕がある状況とは言えないと考える。
一方で、令和5年度には財政基金残高が127億円と、約30年ぶりに100億円を超えるなど、財政状況が改善しているかのようなイメージが強調されている。
財政当局としては、現在の財政状況をどのように捉えているのか、所見を伺う。
2 県債管理基金への基金集約の解消による令和5年度決算への影響について
(1) 基金集約の解消によるメリット・デメリットについて (財政課)
県政改革方針を踏まえ、県民や債券市場に対して比較可能性が求められる中、本県の財政状況をより分かりやすく伝えるため、本県独自の取組である、内部基金・関連法人事業基金の集約の解消、政策目的で保有する株式の基金集約の解消が令和4年度までに行われた。
基金集約の解消によって、減債基金積立不足による加算が増額となり、実質公債費比率が上昇しているとのことだが、令和5年度末で17.5%となっている同比率が18%を超えると起債が許可制になるなど、財政運営に 影響が出るのではないか。基金集約によって、財政状況を実質より良く見せることで、財政が緩みやすくなったことはないか。
集約を解消することの影響をどのように考えているのか、当局の所見を伺う。
(2) 基金集約のメリットがなくなることの影響について (財政課)
基金集約を行うことのメリットとして、一括運用による効率化があると されるが、集約を解消し、運用を各団体・基金に戻すことで、利回り等に影響が出ているのではないかと考えるが、当局の所見を伺う。
(3)財政基金への積み立てを県債管理基金への積み立てより優先する意図について (財政課)
基金集約を解消したことで、減債基金への積立てが不足する状況を改善 するために、財政基金よりも県債管理基金への積み増しを優先すべきとの 考え方もあり得ると思われるが、令和5年度決算においては財政基金への 積み増しを優先したのは、どのような意図によるものか。
いわゆる改革によって、財政状況が改善していると県民にアピールする ため、約30年ぶりに財政基金残高が100億円を超えるといった分かりやすい 成果を出す意図はなかったか、当局の所見を伺う。
3 農林水産資金特別会計のあり方について (農林水産)
令和5年度決算においては、分収造林事業における民間金融機関からの 借り入れ解消などに伴い、歳入において解約清算金、歳出においては造林資金損失てん補金が計上されている特殊事情があるものの、その他については農業畜産、森林林業、水産の各資金について利子補給を行う費用が主に計上されている。
これらの費用については、一般会計からの繰入金で賄われている一方で、繰越金として6億6千万円の資金が過年度から継続して引き継がれている。
当局によると、繰越金は複数年度にまたがる貸付事業に充てるため保有しているが、過去5年間の貸付は2件のみと非常に低調な実績となっている。
厳しい財政状況が続く中で、農林水産資金特別会計に6億円を超える繰越金が引き継がれ、活用されていないことを鑑みると、特別会計の廃止も含めて検討すべきではないかと考えるが、当局の所見を伺う。
4 中小企業高度化資金について (産業労働)
新たな債権管理目標の対象としている特定債権の令和5年度末における 収入未済額は約83億円であり、取組開始前の平成24年度末の約105億円から22億円減少するなど、着実に取組が進められているが、中小企業高度化資金の収入未済額は65億円と、特定債権全体の約8割を占めている。
今後、収入未済額を更に縮減するためには、中小企業高度化資金の債権回収及び整理を進めることが不可欠である。
また、新型コロナウイルス感染症やその後の物価高騰などの影響により、経営悪化を理由に償還猶予を行ったことで後年度の償還額が増加する事例もあるなど、債権回収が滞るのではないかと危惧される。
そこで、債権回収に向けた取組状況と、今後の債権回収の見込みについて、当局の所見を伺う。
5 短期貸付金におけるオーバーナイトの防止について (財政課)
県は、兵庫県森林組合連合会が実施するbe材供給センター事業の運営等に必要な資金として、短期貸付金である森林組合機能強化資金貸付金の貸付を行っていたが、経営環境の悪化により事業が行き詰まり、令和4年11月に県森連は特定調停を申し立て、令和6年6月定例会において、県からの貸付金9億円のうち、6億3千6百万円の債権放棄を議決することとなった。
このような事態に至ったことに関しては、森林組合機能強化資金貸付評価委員会において検証がなされているが、県の対応が遅れた要因のひとつと して、県の貸付金が、いわゆるオーバーナイトに陥っていることを当局が把握できていなかったことが挙げられている。
オーバーナイトは、県からの短期貸付金について、民間金融機関からの 借入により、年度末に一旦全額返済させ、翌年度当初に貸し付ける仕組みで、実質的に長期貸付となっているもので、実質的な財政負担リスクが把握できなくなる等の理由により、総務省の通知により避けるべきとされている。
今後、オーバーナイトが二度と生じないよう、県としてどのような対策を講じているのか、当局の所見を伺う。
●企画部・県民生活部・部外局
1 関西広域連合の目指すべき方向性について
2 地域再生大作戦の成果と評価及び持続可能な多自然地域づくりプロジェクトの効果について
3 若い世代への消費者教育の充実に向けた課題について
(1)くらしのヤングクリエーター養成事業について
(2)SNS上の詐欺的な投資トラブルなどへの取組について
4 不登校やひきこもりなどの課題を抱える青少年への支援について5 阪神タイガース、オリックス・バファローズ優勝記念パレードの事務局運営について
6 無料PCR検査事業に関する調査結果を受けた内部管理評価の取組について
全文
1 関西広域連合の目指すべき方向性について (広域調整課)
関西広域連合は、2府5県による平成22年12月の設立以降、平成24年に4政令市、平成27年に奈良県が加入するなど、構成団体を拡大しながら7分野の広域事務を中心に広域行政の担い手として一定の役割を果たしてきていると認識している。
兵庫県は広域防災担当として、副担当である奈良県・神戸市とも連携しながらカウンターパート方式による被災地支援等を実施しており、こうした取組については、国の第33次地方制度調査会答申においても評価されるなど、具体的な成果も見えるようになってきている。
しかしながら、設立当初から目指してきた、国の事務・権限の移譲により、分権型社会を実現していく役割は十分に果たせているだろうか。
主要施策の成果及び基金運用状況説明書にも記載があるが、「地方分権改革に関する提案募集を活用し、国と地方の役割分担を踏まえた広域連合の役割の 法制化や、地方分権特区による広域連合への実証実験的な権限移譲等」の提案は、具体的な進捗が見られるのだろうか。
私は、将来的に広域連合の役割を強化していくべきだと考えている。例えば、淀川水系のように広域にまたがり、その恩恵も広く及んでいる自然環境を いかに管理運用していくか、といったテーマを適切に意思決定していくこと など、広域連合として国の事務・権限の移譲を求めていくことの現状と課題について、当局の所見を伺う。
2 地域再生大作戦の成果と評価及び持続可能な多自然地域づくりプロジェクトの効果について (地域振興課)
平成20年度から令和4年度まで継続されてきた地域再生大作戦については、都市部を除く29市町にある小規模集落を対象に地域づくりに取り組んできた。
しかしながら、人口減少の進展により小規模集落数は平成20年度には247 集落であったところ令和4年度には918集落と約3倍に急増し、また、都市部にも小規模集落が拡大してきたところである。
個々の集落で地域運営の担い手が枯渇するなど、県が直接主導して地域を 支援する施策としての限界が見えたことから、市町との連携により重層的な 支援体制を作り、都市部も含む37市町を対象に旧小学校区等の広域的な地域運営組織を面的に支援する施策として「持続可能な多自然地域づくりプロジェクト」が令和5年度から開始されたと聞いている。
人口流出が加速するなど、地域の持続性を維持することが難しくなってきている多自然地域において、移動・買い物支援など生活機能の確保と、地域資源を活用した雇用・収入拡大や移住促進など幅広い取組を支援する施策は非常に重要だと考える。
一方で、15年近くにわたって取り組んできた地域再生大作戦が、人口減少による地域課題の逼迫化をどの程度緩和することができたのか、新しいプロジェクトが地域の持続可能性を上げるためにどのような効果を見込んでいるのか、評価していくことも重要だと考えるが、当局の所見を伺う。
3 若い世代への消費者教育の充実に向けた課題について
(1)くらしのヤングクリエーター養成事業について (県民躍動課)
県は平成22年度から「次世代の消費者教育・学習に関する協定」に基づき、消費生活に関する研修を受けた大学生を「くらしのヤングクリエーター」と位置づけ、自ら消費者問題に関する事業を企画・実施することにより、 県民の消費者力向上とくらしのヤングクリエーター自身の消費者リーダー力向上につなげる取組を継続している。
令和3年度からは、県内の大学生協などを構成団体とする一般社団法人ひょうご大学生支援機構を委託先として大学生への消費者教育に取り組んでいると聞いている。
令和5年度には、くらしのヤングクリエーター16名に認定証を交付し、これまでの累計で262名を認定したとのことだが、学生たちは卒業すると 疎遠になることもあると思われ、継続的に活動が充実しているのか疑問もある。
そこで、これまでの取組による具体的な成果、今後の課題について、当局の所見を伺う。
(2)SNS上の詐欺的な投資トラブルなどへの取組について (県民躍動課)
20から30歳代の若年層も含め、詐欺的な投資トラブルに関する相談は激増していると聞いている。
これらの対策には、詐欺事案としての検挙も含め、警察力に頼らざるを得ない部分もあるかと思われるが、啓発の面では消費生活部門にも大いに役割があると認識している。
そこで、SNSを通じた詐欺的な投資トラブルについて、実効性のある広報啓発を行うために、ヤングクリエーターの活用や警察部門の広報との連携協力も含め、積極的な展開が必要と考えるが、当局の所見を伺う。
4 不登校やひきこもりなどの課題を抱える青少年への支援について
(男女青少年課)
不登校やひきこもりなどの課題を抱える青少年へは、学校教育部門はもちろん、福祉部門、地域の市町や社会福祉協議会など多様な主体による連携した取組が重要と考えている。
県では、兵庫ひきこもり相談支援センターによる電話相談「ほっとらいん相談」を実施しているほか、県内5ヵ所でNPOなどと連携して地域ブランチを開設している。
また、「ひょうごユースケアネット推進会議」を約20年前から設置して、保健・医療・福祉・教育・雇用等の分野から32の機関で構成し、社会生活を 営む上で困難を有する青少年への支援にかかる情報交換や連携による支援を実施しているとのことだが、支援を行う中でどのような成果があったのか、また、今後の課題の認識について、当局の所見を伺う。
5 阪神タイガース、オリックス・バファローズ優勝記念パレードの事務局運営について (県民生活部総務課)
阪神タイガース、オリックス・バファローズ優勝記念パレードは、実行委員会形式で行われ、クラウドファンディング収入や協賛金についても公金としての経理処理は行わず、今期の決算資料にも計上されていないと聞いている。
しかし、兵庫県事務局長を知事が担い、同所在地として兵庫県県民生活部総務課と実行委員会規約に明記されている以上、事務局運営については公務として行われたと考える。
同パレードは、単に優勝した両チームを祝し、ファンの希望を叶えるのみならず、スポーツの振興や神戸の魅力発信、観光などの公益性を有するとの判断から公務として事務局を担ったと考えるが、運営面でのガバナンスは十分に機能したのだろうか。
実行委員会の収入には、過去のパレードの剰余金約1,800万円が計上され、残余金は公益財団法人関西・大阪二十一世紀協会への寄付として約1,300万円が引き継がれている。
これは、次回開催の際の原資に充てることも想定した取り扱いと思われるが、もし今後も優勝パレードが行われるとした場合に、職員の負担を軽減しながら、公正な運営を担保するために経緯を記録し、運営面での実務を改善できる可能性を残す必要があると考えるが、当局の所見を伺う。
6 無料PCR検査事業に関する調査結果を受けた内部管理評価の取組について
(会計課・審査指導課)
新型コロナウィルス感染症の無料PCR検査等実施事業に関して、架空の検査実績を計上する検査数の水増しなどの不適正な処理が発覚し、該当事業者に対して訴訟も含めた対応を行っていると承知している。
今回のケースは、コロナ禍という緊急事態の中で、悪質な事業者による不正が行われた事案と思われるが、こういった事案に対して県として予防策がないか、どのような対応が適切だったのかといった事後検証を行うことは非常に 有益と考える。
一方で、内部管理評価の事務そのものが、通常の監査に屋上屋を重ねるといった意見もあり、職員の間で取組への認識が十分に根付いているのかが課題とも聞いている。
ついては、無料PCR検査等実施事業における不適正事案を受けて、内部管理評価をより有効に機能させるための対応策や、職員への制度周知などについて、出納局としての取組を伺う。
●福祉部
1 介護人材の確保対策について
(1)外国人介護人材の参入促進と定着支援について
(2)訪問サービス分野の人材確保対策について
2 障害福祉分野のICTやロボット等の導入による生産性向上対策について
3 自殺対策強化事業の成果と課題について
4 児童虐待情報共有システムの運用開始について
全文
1 介護人材の確保対策について
(1)外国人介護人材の参入促進と定着支援について
超高齢社会の到来により、介護需要は増大を続けている中で、介護人材の確保は喫緊の課題となっている。
県においても、多様な人材の参入促進、定着促進とキャリア支援、働きやすい職場づくりの三本柱を立てて、あの手この手の対策に取り組んでいると聞いている。
しかしながら、介護職の給与水準が他業種と比べて低位に留まっている実情からも、抜本的な改善が期待しにくい中で、外国人介護人材の活躍が大いに期待される。
その点からも、公民連携による特定技能外国人確保など、先駆的な取組を行う事業者の力を借りて、業界全体の活性化につなげていく取組は重要だと 考えるが、現在の取組状況、課題、今後の方向性について、当局の所見を伺う。
(2)訪問サービス分野の人材確保対策について
今年度の介護報酬改定により、訪問介護の基本報酬が減額されたこともあって、特に施設併設型ではない小規模な訪問系介護事業者にとって、人手不足の解消は大きな課題だと認識している。
中には、70歳代のヘルパーに頼らざるを得ない現場も多いと聞いている。
県の取組メニューの中にも、訪問サービス分野での介護サービスの理解促進といった項目があるが、現在の課題認識と取組状況について、当局の所見を伺う。
2 障害福祉分野のICTやロボット等の導入による生産性向上対策について
障害福祉分野でも、賃金水準が他業種と比べて低位に留まり、人材不足の現状があることから、業界全体として事業所運営における生産性向上は、サービスの質の向上のみならず、人材の参入・定着促進の意味からも大きな課題であると認識している。
県では、国からの補助事業としてICT導入モデル事業、ロボット等導入支援事業を展開しているが、実際に導入されている事業者は県全体から見るとまだまだ少ないように思われる。
国からの補助枠内でしか予算措置されない現状はあると理解するが、今後の更なる生産性向上に取り組む上で、事業者側も含めた課題と対応方針について、当局の所見を伺う。
3 自殺対策強化事業の成果と課題について
平成18年に自殺対策基本法が制定され、平成28年には地方自治体に自殺 対策計画の策定が義務付けられるなど、自殺対策は進展してきたことを実感 している。
しかしながら、令和5年の死因を分析すると、40歳未満の死因トップは自殺であり、G7諸国の自殺死亡率では我が国はワーストであることからも、まだまだ取り組むべきことは多いと考えている。
兵庫県においても、昨年中の自殺者数は995人と1,000人近くの方が自ら 命を落とす事態となっており、決して他人事とは言えない状況である。
県の自殺対策強化事業については、年齢階層別に様々なフェーズでゲート キーパーとなりうる人材を育成すべく研修に取り組むなど、実効性のある対策が取られてきたと考えているが、その成果と課題について、当局の所見を伺う。
4 児童虐待情報共有システムの運用開始について
令和5年度の補正予算において措置され、今年10月1日から運用開始された児童虐待情報共有システムについては、現場の警察官が迅速に過去の通告 状況なども含む児童相談所の取扱歴を確認することができ、児童を安全確保 するかどうかの判断をより適切に行うことができるようになったと聞いている。
また、従前は毎月更新であった情報連携が1時間ごとのリアルタイム連携になったことで、情報の出し手である児童相談所側の運用が改善され、緊急夜間対応などの負担軽減効果も期待できる。
運用開始からまだ1週間程度しか経っておらず、具体的な成果は現れていないかもしれない。
虐待防止の観点からは警察と福祉の連携は不可欠であり、今回のシステム導入が連携強化の契機になったのではないかと考えるが、当局の所見を伺う。
●公安委員会
1 犯罪被害者を支援するための民間支援団体との連携について
2 外国免許の切り替えについて
3 南海トラフ地震など大規模災害時の警察対応について
4 拾得金品の保管体制と警察本部での内部管理制度の運用状況について
全文
1 犯罪被害者を支援するための民間支援団体との連携について
犯罪被害者等基本法が施行されてから約20年が経過し、兵庫県においても令和5年4月に、犯罪被害者等の権利利益の保護等を図るための施策の推進に関する条例が施行された。
犯罪被害者やその家族を取り巻く環境は少しずつ改善されてきたものの、被害に遭われた方にとっては、犯罪行為による直接的な被害に留まらず、精神的な負担、刑事手続きへの協力や民事訴訟への対応、各種行政機関への相談など様々な負担を余儀なくされる。
こうした犯罪被害者への支援に当たっては、警察など行政機関のみならず、民間支援団体を含めて支援体制を構築する必要がある。
本県では、公益社団法人ひょうご被害者支援センターが犯罪被害者等早期援助団体に指定され、電話や面接による相談活動、裁判所への付き添い支援、生活支援など中長期にわたる支援も実施している。
また、性暴力に関しては、近年、女性の被害のみならずジャニーズ事件の影響もあって男性の被害相談もあると聞き及んでいるところ、兵庫県が兵庫被害者支援センターに「ひょうご性被害ケアセンターよりそい」を設置し、性暴力被害者の潜在化を防止するなどの運営をしている。
こうした犯罪被害者支援については、関係団体との連携も含めて相談者の状況に応じたきめ細かな対応が求められ、民間団体が専門性をもって関わる 必要があり、更なる機能強化が望まれるが、兵庫被害者支援センターの周知に伴い、直接支援等の活動が増加し、支出も増加していることから財政基盤の整備が喫緊の課題であると承知している。
そこで、県警察として兵庫被害者支援センターに対して、どのような財政的支援を行っているのか、所見を伺う。
2 外国免許の切り替えについて
深刻な人手不足による労働力確保が喫緊の課題となっているため、本年4月から新たな特定技能分野として自動車運送業が追加されるなど、来日外国人の運転免許切り替えニーズが増加することが予想される。
こうした中で、全国的に外国免許から日本の免許に切り替える外免切替について、年々その取扱件数が増加し、全国的にかなり待ち日数が生じていると聞いている。
そこで、本県における外免切替の取り扱い状況と、待ち日数が生じているならその理由、解消方法など、県警察として外国人が運転免許を円滑に取得できるための対策について伺う。
3 南海トラフ地震など大規模災害時の警察対応について
本年1月に発生した能登半島地震においても、県警察は支援のため現地へ要員派遣を行ったと承知している。
また、8月には宮崎県日向灘を震源とする震度6弱の地震が発生し、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表された。
このような背景を踏まえて、大規模災害時の警察対応について様々なケースを想定した訓練や想定が行われていると考えているが、県警察の対応状況を 伺う。
4 拾得金品の保管体制と警察本部での内部管理制度の運用状況について
拾得金品の保管や受け渡しについては、遺失物法の規定により運用されていると承知しているが、令和5年度決算においても拾得金品期満後収入は、約1億8,000万円にのぼることからも、確実な管理体制の整備が求められる。
また、具体的な管理方法については、マニュアル整備がなされていると思うが、財物的価値が低く、保管に手数がかかる傘や衣類、自転車などの物品と、現金やクレジットカード、携帯電話など占有者にとっての逸失価値が高い金品とでは、取扱いに要する負担にも軽重があると思われる。
最初に届出を受ける施設管理者とのやり取りや、交番など派出先との受け 渡しも必要で、厳重な管理が求められると同時に、現実的に機能する体制も考慮する必要がある。
一方で、全国的に見ると拾得物の横領や紛失といった事件も散見され、不正や不適切な取扱いが発生しにくい体制を整備することも重要な課題であると考える。
令和2年4月から、県内部管理制度の導入により県警本部においても知事部局に準じて運用がなされていると聞いているが、拾得金品の保管体制の現状と課題、内部管理制度の運用状況について、当局の所見を伺う。
●環境部
1 野生動物の保護管理事業における民間事業者との連携について
2 生物多様性ひょうご戦略の推進について
3 温暖化対策事業における事業者としての県庁の取組について
全文
質問に入る前に一言申し上げたい。
決算審査を行うに当たり、環境部に係る予算の執行状況と事業の概要を把握するため、「主要施策の成果及び基金運用状況説明書」を精査したが、大枠の事業ごとでしか決算額の記載がなく、個別事業の予算執行状況については全く記載がなかった。
これでは、どのような事業にどの程度の予算を投じ、費用対効果はどうか、といった観点が一切伝わらず、説明責任の観点からいかがなものかと感じた。
来年度以降は、適切に資料へ記載するよう要望しておく。
1 野生動物の保護管理事業における民間事業者との連携について
ワイルドライフ・マネジメント、つまり野生鳥獣の保護管理とは、科学的な調査・研究に基づき「生息地管理」、「個体数管理」、「被害管理」を状況に応じて組み合わせ、人と動物と自然環境の関係を適切に調整し、共存を図る手法のことで、県においても、農林業被害や人身被害の防止、自然の恵みに裏付けられた中山間地の振興、自然環境資源の持続的な利用など5つの基本 目標を定めて取組を推進している。
これらの取組には、国からの交付金を活用した鳥獣被害防止総合対策が大きな役割を担っており、市町が作成する鳥獣被害防止計画に基づき実施する防護柵などのハード整備、あるいは有害鳥獣捕獲などの事業に約3億2,600 万円の予算が投入されている。
捕獲作業など具体的な活動には、一般社団法人兵庫県猟友会に所属するハンターをはじめ、民間事業者との連携が不可欠であると考える。
中でも、猟友会については、例えば「狩猟のいろはと魅力発見支援事業」や「狩猟免許講習会支援事業」、「狩猟技能向上促進事業」などに補助金を交付することで支援しているほか、県が実施する「有害鳥獣捕獲入門講座~狩猟マイスター育成スクール」の受講要件に「兵庫県猟友会に入会しようとする者」と明記されているなど、密接な関係にあると思われる。
また、シカ丸ごと一頭活用大作戦事業では、平成27年5月に設立された「ひょうごニホンジカ推進ネットワーク」を中心に、例年神戸で「文鹿祭Bunkasai」を開催するなど、食・文化・皮革など多彩な領域から民間事業者の力を結集し、ジビエ食材としての活用やペットフードとしての流通、レザーや骨の利用など、地域資源としてのPRに努めている。
以上のように、ワイルドライフ・マネジメントを推進するうえで、兵庫県猟友会を始めとする民間事業者との連携を整理し、どのようにマネジメントしていくのかが問われていると考えるが、県としての戦略的な方針について所見を伺う。
2 生物多様性ひょうご戦略の推進について
生物多様性の保全については、生物多様性条約による国際的な規範のもと、国内では生物多様性基本法によって保全と利用のバランスを取りつつ、長期的な観点から施策を実施するよう地方自治体にも責務が課されている。
県では、平成31年2月に生物多様性ひょうご戦略を改定し、「担い手不足による里地・里山の維持管理の困難化や、侵略的な外来生物の防除など顕在化する課題に対して一層の取組強化が求められている」と、その趣旨が明記されている。
ところで、令和5年度決算によると、生物多様性ひょうご戦略の推進として、レッドデータブックの改訂や自然保全事業推進、貴重動植物の普及・啓発活動などが行われたとされている。
ついては、当該事業の実績・成果と、今後の課題について、当局の所見を伺う。
3 温暖化対策事業における事業者としての県庁の取組について
県では、企業版ふるさと納税の財源を活用して、GHG(温室効果ガス)排出量算定サービス導入補助事業を令和5年度から開始するなど、温暖化対策にも 積極的に取り組んでいることと承知している。
また、事業者としての兵庫県庁にも、当然のことながら温室効果ガス排出量削減などの取組が求められ、環境率先行動計画に基づき搬出量の算定を行っていると聞いている。
同計画では、令和7年度までに令和元年度比で20.5%削減を目標としているが、令和5年度実績では12.6%減と、目標達成には今一歩の努力が必要な状況と考える。
ところで、県庁舎3号館の改修工事が行われるが、全ての照明器具をLED化する予定と聞いている。
蛍光灯の製造中止が2027年に迫る中で照明器具のLED化は必須の取組と 考えるが、県庁自らの事業活動で生じる温室効果ガスの削減について、具体的な取組状況と今後の課題を伺う。
●教育委員会
1 主権者教育の充実について
2 地域と学校の連携・協働体制の推進について
3 文化財保存活用地域計画の策定状況について
4 高校生による生産物の販売と地域活性化の取組について
全文
質問に入る前に一言申し上げる。
今回、教育委員会の決算審査にあたり決算資料を精査したところ、主要施策の成果及び基金運用状況説明書への記載について、各事業の仕切り方は「ひょうご教育創造プラン」の体系に基づいてはいるものの、項目の大小が気になった。
例えば、「確かな学力」の育成などプランの基本的方向性に基づいた小さい 項目、「子どもたちの学びを支える環境の充実」などプランの基本方針に基づいた大きい項目がある。「子どもたちの学びを支える環境の充実」の項目には 「教職員の資質・能力の向上」から「いじめ対応」「不登校対応」「施設等の ハード整備」「GIGAスクール」「就学支援」「家庭・地域と学校の連携」と多岐にわたっており、総額320億円余りの事業がごちゃ混ぜで記載されている。
しかも、それぞれの取組ごとの事業費が記載されておらず、何にどれくらいの経費を要したのか全く分からない。様々な取組を踏まえて、今後の対応としても具体的にどのように対策していくのかが必要ではないかと思う。
前例踏襲ではなく、第4期プランがスタートする来年度以降の資料作成に おいては、分かりやすく整理し直されるよう要望して、質問に入らせていただく。
1 主権者教育の充実について
令和4年度から成年年齢が18歳に引き下げられたことを受けて、主権者 教育の充実が求められている。
現在は、公民科や家庭科などの教育活動を通じて、生徒に必要な政治的教養を身に付けさせるとともに、金融教育や消費者教育にも取り組むため、全県立高校の担当教員を対象として実践研修会を開くなど、指導に関する事例を共有する取組がなされていると聞いている。
一方で私は、主権者教育には狭い意味での「政治的な教養」を身に付け させる以上に、「主体的に共同体を育む態度」を育成し、自らの人生と他者の 幸せを願う市民性(シティズンシップ)を養うことをも視野に入れるべきではないかと考える。
先日読んだ「なぜかいじめに巻き込まれる子どもたち」というTBSの報道 特集ディレクターを務める川上敬二郎氏の著書では、「いじめ予防授業」 「いじめ免疫プログラム」といった取組の紹介に続き、欧米のいじめ研究者の言葉として「いじめ対応の目標は、詰まるところ市民性教育だ」と述べ、 「いじめに歯止めをかけるには、抑止力を日常的に埋め込んで自浄作用を図ることが不可欠であり、それを市民性教育にゆだねている」とあり、私も目からウロコが落ちる思いであった。
ぜひご一読いただけたらと思うが、要は「いじめに抑止力を働かせるには、集団の中で傍観者を減らし、主体的にいじめを仲裁する個人を増やす」ことが肝要だと言える。
私は、主権者教育には主体的な市民を育てるということを通じて、学校内の自治的な文化を育む意義もあると考えており、高校生に限らずより低学年から一貫性を持って取り組むべきだと考えるが、当局の所見を伺う。
2 地域と学校の連携・協働体制の推進について
昨今、教員の働き方改革などの動きも踏まえ、地域と学校の連携・協働の 取組は重要性を増している。
例えば、部活動の地域移行においても学校教育と社会教育の枠組みを超えた地域全体でのスポーツ・文化活動を視野に入れた改革が求められている。
そのような中で、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく学校 運営協議会を設置した学校「コミュニティ・スクール」の推進が平成29年から努力義務化され、県における取組も進んでいると聞いている。
また、学校運営協議会には社会教育法に基づく地域学校協働活動推進員が 参画して、地域の人々や団体による緩やかなネットワークである地域学校協働本部が取り組む、例えば放課後における学習支援・体験活動であったり、授業補助・登下校対応・部活動補助など学校における活動、防災活動やお祭り等の地域を活性化させる活動などをコーディネートすることが想定されている。
私は、学校が持つ独特の文化あるいは閉鎖性を、風通しの良いものに変えていくために、地域と学校の連携は重要だと考えている。
そこで、現在までの地域と学校の連携協働の取組の進捗と成果、課題認識、今後の方向性について、当局の所見を伺う。
3 文化財保存活用地域計画の策定状況について
平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、指定文化財は修理された一方、未指定の文化財は修理できずに失われてしまった経緯がある。その状況を踏まえ、兵庫県で生まれたヘリテージマネージャーの育成は、全国的に広がりを見せていると伺っている。
私は以前に、一般社団法人宝塚まち遊び委員会という団体の設立にかかわり、指定・未指定に関わらず宝塚のまちにある文化財を楽しむことを大きな活動目的として取り組んできた。
平成30年に文化財保護法が改正され、指定又は登録文化財を個別に保存・活用するのみならず、未指定の文化財も含めた地域文化財の総合的・一体的な保存・活用に取り組むために、各市町が「文化財保存活用地域計画」を作成し、文化庁の認定を受ける制度が整えられたと承知している。
現在のところ、県内では11市町が作成済みと聞いているが、まだまだ各市町の取組には温度差もあるように感じる。
そこで、文化財をまちづくりの中に位置付けて、地域総がかりで文化財を守り、活かし、伝える体制の構築を図る取組の更なる活性化に向けて、当局の意気込みを伺う。
4 高校生による生産物の販売と地域活性化の取組について
教育委員会の歳入決算を調べていると、生産物売払収入として、畜産類約7,000万円、花き類約2,900万円、牛約1億1,200万円といった数字が並び、かなりの金額になっていることを発見して、驚きとともに大変うれしくなった。
農業に関する学科を設置する高校で、授業の一環として生産した農産物や 畜産物の販売が県の歳入の一助になることは、農業を目指す高校生にとって 大きな励みになるとともに、地域にとっても良質な産品を安価で入手できることで、地域の活性化にも貢献しているのではないかと考える。
少し種類は違うが、三重県多気町の相可(おうか)高校食物調理科調理クラブの高校生たちが、調理のみならず接客やコスト管理を学ぶために高校生レストラン「まごの店」をオープンし、20年にわたって様々なメディアにも取り上げられ、ふるさと納税の返礼品としても活用されるなど、大いに活躍されていると聞いている。
ついては、兵庫県においても農業に関する学科をはじめとする職業系の学校が、その授業や部活動を通して地域活性化に貢献できる取組を応援していければ、大いに夢がふくらむと考えるが、当局の所見を伺う。
●病院局
1 粒子線医療センターのあり方検討について
2 医療安全対策の推進について
3 子どもの療養を支える専門職の役割について
全文
1 粒子線医療センターのあり方検討について (企画課 企画調整班)
令和5年度決算は、県立病院全体での経常損失が約91億円と、大変厳しい決算となった。
中でも県立粒子線医療センターについては、例年9億円前後の損失を計上しており、現在そのあり方を検討する委員会を立ち上げて議論が進んでいると承知している。
すでに平成13年の開設から20年以上が経過し、複数の箇所で老朽化が進んでいるため保守等にかかる経費が増大しているだけでなく、部品の在庫が切れるなど、安定的な診療継続に対するリスクもある。
また、粒子線治療装置保守管理・維持運転業務の委託契約が令和9年度までとなっていることもあり、以降も診療を継続するには大規模な改修が必要で ある。
あり方検討委員会での議論を参照すると、近隣施設の設置による影響を受けて、可能な集患対策として、がんセンターを含む県立病院をはじめ紹介元となりえる医療機関でのカンファレンスへの参加、一般向けの講演活動、広告や医療雑誌への掲載など考えられる限りの努力をされ、一定の成果も見られる。
経費節減対策としては、基準を満たす範囲での人員削減などにも取り組んでいるが、材料費などの高騰により限界があるとのことである。
粒子線医療センターのあり方については、移転・廃止等も含めて一定の方向性を見出していく必要があるが、現時点での議論の進捗や、移転も含めて新規投資を行う場合のリスクと、廃止を決断する場合の課題について、当局の所見を伺う。
2 医療安全対策の推進について (企画課 企画調整班)
医療行為が侵襲性を伴うものである以上、一定の医療事故発生リスクは必然的に伴うものであると承知している。
現在、兵庫県立病院医療安全標準マニュアルを策定して、病院局と各病院が一体となって組織的に医療安全管理を推進しており、また病院運営の透明性向上と信頼される県立病院を実現するため、患者ご本人やご家族が公表に反対しない場合は、県立病院で発生した医療事故を公表する取組も進めている。
これらの取組によって医療事故のリスクは低減していくと考えるが、事故対応においては法的な争いに発展するケースもあるものと思われる。
ついては、医療安全対策の現状と課題、訴訟も含む医療事故対応の管理体制について、当局の所見を伺う。
3 子どもの療養を支える専門職の役割について (管理課 組織給与班)
長期にわたる入院治療を要する病気にかかってしまった子どもたちにとって、入院先の病院は単に治療の場であるだけではなく、生活の場、学びや成長の場でもある。
例えば、化学療法や移植によって6ヵ月間の入院が必要でも、大人にとっての6ヵ月と子どもにとっての6ヵ月は全く意味が異なる。
アメリカで始まった、遊びやコミュニケーションを通して子どもの治療を 支える専門職であるチャイルド・ライフ・スペシャリスト(CLS)は、アメリカで資格を取った先駆者によって日本の小児科病棟にも導入され、イギリスの 資格であるホスピタル・プレイ・スペシャリスト(HPS)や、日本で新たに設けられた資格である子ども療養支援士などとともに、入院患児や家族が 抱える精神的負担を軽減し、主体的に治療に臨めるよう支援して「子ども家族中心医療」を目指す役割を果たしている。
子どもにとって心理的負荷の高い検査や手術などについても、人形を使ったロールプレイなどで年齢に応じた理解を促し、またコミュニケーションから 得られる子どもの気持ちや心理状態を医療者に伝える役割も担っていると 聞いている。
ついては、県立こども病院での子どもの療養を支える専門職の役割について、どのように認識し、活用しているのか、当局の所見を伺う。
<黒田 一美 議員>

●総務部・財務部・危機管理部
1 県人事当局による報道機関、新聞記者への告発文書の調査を行った件について
2 県職員公益通報(内部通報)制度の公益通報者保護法に基づいた通報者保護の徹底について
3 本庁舎整備、本庁職員出勤率4割の見直し、教育委員会事務局の勤務地について
(1)新しい働き方モデルオフィス 繁忙期における検証結果を踏まえた本庁舎整備について
(2)県教育委員会事務局の庁舎移転について
全文
1 県人事当局による報道機関、新聞記者への告発文書の調査を行った件について
県人事当局は、本年4月に、元県民局長の告発文を受け取ったかどうかを新聞記者に調査をし、記者から「答えられない」と拒否され、報道関係者に情報開示を行政が迫る異常さを指摘された事が明らかになりました。
さらに、全国組織の日本新聞労働組合連合から「情報源の開示を迫る県人事当局の高圧的な対応は、報道の自由や市民の知る権利を侵害するものである。」との声明が出されました。
報道によると、県人事当局は「今後も一部報道機関や関係者への聴取を続ける」と記載されています。
この件は今年6月7日、わが会派の代表質問で北上あきひと議員が前斎藤知事に質問し、前齋藤知事は「単なる事実確認の手続きの一環として行ったものであり」「報道の自由や取材源の秘匿権を侵害するものではない」と答弁しているが、現在、人事当局はどうお考えですか。
2 県職員公益通報(内部通報)制度の公益通報者保護法に基づいた通報者保護の徹底について
県職員にとって、違法行為、不当行為が職場、公務上あってはならず、それを、見たり知ったら、黙っていてはいけない、通報をする義務があります。
兵庫県職員公益通報制度実施要綱第8条にも通報者の保護とありますが、その時は徹底して通報者の保護をしなくてはなりません。
しかし、現在の兵庫県では、通報者の保護に対する県職員の信頼は大きく揺らいでおり、そのため、県職員公益通報制度の在り方を見直す必要があると考えますがご所見を伺います。また、通報者保護の観点からも通報窓口を県庁外部に設置する必要があると思うが今後の対応についてお聞きします。
3 本庁舎整備、本庁職員出勤率4割の見直し、教育委員会事務局の勤務地について
(1) 新しい働き方モデルオフィス 繁忙期における検証結果を踏まえた本庁舎整備について
齋藤前知事は本庁職員の4割出勤について、昨年12月の定例会において我が会派の竹内議員の質疑に対して、「この道しかない」と言い切っていましたが、この9月に発表された「新しい働き方モデルオフィス繁忙期における検証結果」では、年度末・年度当初のピーク時の出勤率は、85・8%となり、職員アンケートでは、約8割が週2日以下の在宅勤務を希望しています。
課題への対応策として、「十分なコミュニケーションが図れるよう、希望する職員が勤務可能な執務空間を確保」するとなっています。
この現状を踏まえて、本庁舎職員出勤率4割と、県庁舎1号館と2号館をまず解体して、建設せずに緑の広場にするとの斎藤前知事の方針は変更する必要があると考えますが、ご所見を伺います。
(2) 県教育委員会事務局の庁舎移転について
斎藤前知事の方針で、県教育委員会事務局が県庁より約9㎞離れた神戸市東灘区の旧神戸市水道局東部センターに庁舎を移すことになり、今月末から順次移転を始めます。
いつまでの移転か、県庁周辺に戻れるのか分かっていないため、職員から不安の声を聞きます。
県の教育行政を高めるためにも、仕事の連携・効率化をはかるためにも、県教育委員会事務局の場所を県庁内か隣接地に置く必要があります。
移転の期間も含めて基本方針、方向性を早期に示すよう強く求めますが、お考えをお聞きします。
●企画部・県民生活部・部外局
1 インターネット上の人権侵害等の防止を図る条例の検討状況と今後について
2 令和5年度人権に関する県民意識調査の結果と今後の対応について
全文
1 インターネット上の人権侵害等の防止を図る条例の検討状況と今後について
近年、SNSの普及に伴い、インターネット上の誹謗中傷や不当な差別的言動等が後を絶たず、大きな社会問題となっている。
このことについて、私は令和4年12月の本会議代表質問、令和5年9月の一般質問で対策の強化を訴えてきました。
また、本年3月の予算特別委員会で、公明党の越田議員、我が会派であるひょうご県民連合の小西議員からも同様の質問が行われ、当局は「深刻な社会問題であるSNS上の誹謗中傷等の抑止を喫緊の課題とし、条例化の検討を 進めていきたい」と答弁している。
県では、インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害を防止するため、人権情報誌等による啓発やインターネット・モニタリング事業、弁護士による専門相談などの施策を進めていますが、インターネット上での差別、人権侵害は 後を絶ちません。
また、モニタリングは対処対策であり、本来の目的は差別そのものを無くす、全ての人が差別をしない社会を目指さなくてはならないと考えます。
そのための方策として、条例化が必要であると考えますが、条例化の検討の現状と今後の方針について、当局の所見を伺います。
2 令和5年度人権に関する県民意識調査の結果と今後の対応について
本県では、多岐にわたる人権課題の解決に取り組み、人権文化を進めることを目的として、5年ごとに県民の人権に関する意識調査が行われております。
この調査は、今後の効果的な人権施策を検討するための基礎資料となるもので、平成10年度に始まり、令和5年度は6回目の調査として、3,000人を対象に実施され、1,234人から回答があったとの報告書がとりまとめられています。
調査結果では、人権を身近に感じる人の割合は平成30年度調査と変わらないが、身近に感じない人の割合は低くなっているとのことである。
今回の調査における分析結果の特徴と課題、それらを踏まえた今後の取組について、当局の所見を伺う。
●産業労働部
1 商店街の活性化について
2 県内企業商品のPRについて
全文
1 商店街の活性化について
県内にはシャッター街と呼ばれる商店街も多くあり、どう活性化していくのかが大きな課題となっています。商店街の活性化は地域の活性にもつながるため、県では商店街に賑わいを創出するためイベントへの支援等さまざまな取り組みを実施されているところです。
一方、補助を受けるためにも組合の維持も難しい商店街も出てきているなど新たな課題もあるのではないかと思います。
魅力ある商店街づくりについて、昨年度どのように取り組んでこられたのかお伺いします。
2 県内企業商品のPRについて
県内には、五国それぞれに様々な企業や組合があり特色のある商品が多くあります。それらの商品の県内外への認知度を向上させてブランド力を高め、魅力を発信していくことは重要であります。
県下の企業の商品PRをどのような手法で行ってきたのかお伺いします。
●土木部
1 命とくらしを守る急傾斜事業の充実について
2 神戸電鉄粟生線の更なる活性化の取組について
全文
1 命とくらしを守る急傾斜事業の充実について
災害から命とくらしを守る急傾斜事業のうち県単独事業の対象となるのは、人家5軒以上、斜面の高さ5m以上、傾斜度が30度以上と国の採択基準の人家10軒以上、斜面の高さ10m以上よりも広く対象となるよう制度化されています。特に阪神・淡路大震災以後、災害から県民の命とくらしを守るため、予算を増やし、精力的に事業展開されており、大いに評価しています。
しかし、昨今の資材高騰の中、予算不足で対象となる急傾斜事業が進まず、県民の命とくらしが脅かされることになっているのではないかと心配されます。
そこで、現在、兵庫県内で約3,500箇所ある未整備の箇所の事業実施が今後どのように展開していくのかお伺いします。
2 神戸電鉄粟生線の更なる活性化の取組について
私は、兵庫県議会議員神戸電鉄粟生線を守る会議員連盟の副会長を行っておりますことから、粟生線の更なる活性化について質問します。
神戸電鉄は、六甲山、菊水山を越える山岳鉄道であり、車両も山岳鉄道用の車両であることから更新する費用も高額となるため、老朽化対策の支援が必要です。
また、粟生線の沿線には、県立高校が多くあり、多くの高校生の通学の足となっているほか、沿線には、北播磨総合医療センターもあり、病院へ通う県民の足にもなっています。
更なる利用促進に向け、沿線の各市が参画している「粟生線活性化協議会」による「神鉄おもてなしきっぷ」、「パーク&ライド駐車場」、「クリスマス等のイベント列車」、「トレインフェスティバル」等、様々な取組も行われています。
沿線の県民の方々、高校生の通学の足としても粟生線の更なる活性化の取組が必要だと考えますが、ご所見をお伺いします。
●まちづくり部
1 明舞団地再生の新たな展開について
全文
1 明舞団地再生の新たな展開について
明舞団地は大阪の千里ニュータウンと並び、国の方針で兵庫県と兵庫県住宅供給公社が昭和30年代から40年代にかけて神戸市垂水区と明石市にまたがって開発し、昭和39年に入居が開始された県内最古のニュータウンである。
現在、明舞団地においては、住宅供給公社が分譲したマンションが開発から60年近く経過し、オールドニュータウンとして様々な課題が出てきているが、多くの人々にとって「ふる里」となっている。
県では、明舞団地の活性化を目指して平成15年度に明舞団地再生計画を策定し、平成18年度に実施した「明舞団地再生コンペ」の結果を受け、明舞団地再生計画を見直すなど、地元の明舞まちづくり推進協議会と連携し、県営住宅の建て替えや明舞センターの整備を進めてきた。
また、平成29年度に、明舞団地再生計画の見直しから10年が経過することや、明舞センター地区再生事業などの整備が概ね完了することから、更なる住民主体のまちづくりを関係団体、事業者、行政とともに進めるための新たな10年に向けたまちづくり計画を策定し、団地内で活動する団体、事業者、個人等のそれぞれが実施できる活動・事業が展開されている。
しかし、明舞団地内の3ヵ所のサブセンターの整備や公社等の分譲団地の整備、バリアフリー化が残っている。
また、明舞団地の高齢化がますます進んでおり、住民ニーズも変化している。そういった住民ニーズに応えるため、この10月7日、神戸市が垂水区役所明舞出張所を新たに開設した。明舞団地再生も新たな展開が必要となっていると考える。
そこで、従来から課題となっている、公社等の分譲住宅の整備やバリアフリー化、各サブセンターの整備の現状及び今後の取組について、当局の所見を伺う。
●教育委員会
1 地域で育むトライやる・ウィークの充実について
2 兵庫型「体験教育」を含めた神戸市教育委員会との連携について
全文
1 地域で育むトライやる・ウィークの充実について
私は兵庫の教育で、小学校における「環境体験事業」や「自然学校推進事業」、中学校における「わくわくオーケストラ教室」や「トライやる・ウィーク」等の発達段階に応じた体系的な兵庫型「体験教育」を大いに評価しています。
なかでも、中学2年生で実施している「トライやる・ウィーク」は阪神・淡路大震災後、神戸市須磨区での児童殺害事件をきっかけに、5日間学校へ登校せず、地域で様々な社会体験をして過ごすという取組です。
当初から、「活動範囲は校区内とすることが望ましい」としていましたが、近年は「職場体験」という意識が強まったり、新型コロナウイルス感染症の影響で受け入れ先が減少したりしたため、「校区内の地域で過ごす」ことが難しくなっているという声を聞いており、残念に思います。
この事業は、学校現場の教職員の方々のご努力と受け入れをお世話していただける地域の方々との連携の賜です。
体験学習として全国に先駆け実施され、多くの成果を得ているこの「トライやる・ウィーク」を県教育委員会として継続し、さらに充実する必要があると考えますがご所見をお伺いします。
2 兵庫型「体験教育」を含めた神戸市教育委員会との連携について
7年前、平成29年度より、政令指定都市神戸市の義務教育諸学校の教職員の給与等の負担、学級編成基準の決定は兵庫県より神戸市へ移譲され、神戸市民は個人県民税所得割の税率が4%から2%になり、2%が神戸市へ税源移譲されました。
これにより、神戸市教員の給与が、兵庫県からでなく、神戸市から支払われることになり、神戸市教育委員会の独自性がより高まっていると考えられます。7年が経過して、神戸市教育委員会との連携、協力関係の継続が図られているのか気になるところです。
先程の「トライやる・ウィーク」の質問でも取り上げました体験学習も神戸市の義務教育でも充実される必要があると考えています。
そこで、県教育委員会として、義務教育における兵庫型「体験教育」を含めた神戸市教育委員会との連携、協力関係について、7年の経過を踏まえ、いかに考えているのかお伺いします。
●総括審査
1 公益通報への取り組みについて
(1)兵庫県行政への外部通報の取り組み強化について
(2)公益通報者保護制度の県民への広報・周知の取り組みについて
2 県民のための信頼される兵庫県行政づくり
(1)職員の不安解消と県政の推進について
(2)県内企業商品の受領に関連した産業労働部長の訓告処分及び警察からの事情聴取について
3 職員の働き方と庁舎整備について
(1)出勤率を決める必要性について
(2)県教育委員会事務局庁舎のあり方について
4 高等教育への授業料支援、負担軽減の推進について
5 阪神タイガース、オリックス・バファローズ優勝記念パレードを公務として担う必要性について
全文
1 公益通報への取り組みについて
消費者庁では、令和4年6月から改正公益通報者保護法を施行し、その改正のポイントを説明したリーフレットには、「事業者は体制整備を 通報者に安心を」と大きく記載されています。今回、体制整備が非常に重要だと考えています。
(1) 兵庫県行政への外部通報の取り組み強化について(総 務)
公益通報者保護法では、通報先として、①事業者、国・地方公共団体の内部通報、②行政機関への外部通報、③報道機関等への外部通報の3つのパターンを明記しています。
①の県行政への「内部通報」については、総務部・財務部等の部局審査で、信頼できる外部窓口を年内にも設けられるとの答弁があり、通報者の負担が軽減され、通報しやすい体制になると考えますので、②の行政機関である兵庫県行政へ外部通報がなされた時の県の取り組みについてお伺いします。
県内の労働者等が企業や様々な事業所での一定の違法行為を兵庫県へ通報(外部通報)がなされた時、どこが窓口となり、どのように対応し、通報者の保護をどのように行い、違法行為の解決にどのように取り組むのかが分かりにくいと感じます。
処分権限を有する各部局で外部通報への対応を行っているとのことです。所管部局が不明な場合には、兵庫県民総合相談センターや各県民局の「さわやか県民相談室」内に公益通報総合案内窓口を設置されており、該当部局へ引き継がれるようですが、体制づくりを強化するためには、県として外部通報を集約する体制が必要ではないかと思います。そしてきちんと対応できているか等のチェック体制も必要だと考えますが、ご所見をお伺いします。
(2) 公益通報者保護制度の県民への広報・周知の取り組みについて(総 務)
今回、「文書問題」が発生し、県議会においても本会議での質疑や百条委員会の設立等一連の動向で、「公益通報者保護法」等制度について、報道も多くされ、初めて詳しい内容を知った県民が多くいると思います。
しかし、本来、職場の中等で不正があれば、「通報」し、通報者が匿名でも保護される「公益通報者保護法」と「制度」は、多くの県民が対象となっており、周知する必要があります。
兵庫県においても、県民への広報、周知する責務があると考えますが、現状と取り組みについてお伺いします。
2 県民のための信頼される兵庫県行政づくり
(1) 職員の不安解消と県政の推進について(総 務)
3月にいわゆる文書問題が表面化されてから、これまで、県民等から多くの苦情やご意見が寄せられ、先月末時点の広報広聴課で受け付けた電話だけでも約6,500件、その他人事課や他の部局にも多くの電話が県庁にかかったと聞いております。応援で対応された職員も含めて、苦情への対応、また通常業務に加えての対応で、心身ともに大変な想いをされた方も多かったのではないでしょうか。また、関連団体との関係悪化等に伴い、業務に支障が出て対応に苦慮されたり、県政の停滞等、どうなるのかといった職員の不安は大きいと思います。
本来、県の職員は、「県民の役に立ちたい」、「兵庫県の未来のために働きたい」という志を持って入庁しており、兵庫県のためを思ってのことでも、これまで知事や一部幹部の顔色を伺って言いたいことも言えなかったという状況もあったのではないでしょうか。
さらに、この16日、兵庫県人事委員会は、齋藤元彦前知事らに対する告発文書問題で混乱した県政を立て直すため、「県民の信頼を回復するとともに、職員が自信と誇りを持って職務にまい進できる環境を整える必要がある。」とする異例の提言を盛り込まれました。
こういった状況で、職員一人ひとりが持つ力を発揮して、風通しのよい職場環境で、力を合わせて、停滞していた県政を進めていく必要があると考えます。職務代理者である副知事を筆頭に、どのように県政を推進していくのか、お伺いします。
(2) 県内企業商品の受領に関連した産業労働部長の訓告処分及び警察からの
事情聴取について(産業労働)
先日の産業労働部の部局審査において、県内企業商品のPRを目的に商品を受領することについて、産業労働部長に質問したところ、「例えばわたり廊下にも兵庫のふるさとの物品なんかを展示することがある。そういった時には、企業からの協力を得てそういう商品を提供していただくことはある。」とのことでした。わたり廊下の展示商品を見ると、三木の金物、日本酒、そうめん、そば、豊岡カバン等、地場産品です。加西の企業のコーヒーメーカーなど、特定の一企業の商品はありません。特定の一企業の商品をPRする場合は、慎重になる必要があると考えます。
また、部局審査において、産業労働部長は「返却するのを長期間にわたり怠ったことで処分を受けたことについて、県民から様々な意見を電話等でいただき、その対応を産業労働部の職員にも負担をかけ申し訳なく思っている。県政全体が停滞しており1日も早い信頼回復に努めてまいりたい。」との答弁がありました。さらに、収賄で告発され、警察から事情聴取されたと新聞、ネットで報道されたことについて、「誤解を招くような行為をしたことについて申し訳なく思っている。職員にも企業にもみなさまにご迷惑をおかけしたことがあったと思うので申し訳なく思っている。」との答弁がありました。
どのように信頼回復していくのでしょうか。申し訳なく思っているとのことでしたが、県民や県内企業、職員にはきちんと説明して謝罪されたのでしょうか。お伺いします。
3 職員の働き方と庁舎整備について
(1) 出勤率を決める必要性について(総 務)
齋藤前知事がうち出した「出勤率4割」は、職員の働きやすい環境、さらに行政効果、県民への行政サービスの向上からの発想ではなく、1号館、2号館を解体して新たな新庁舎を建設せず、広場にして、予算を節約し、3号館他周辺の建物、いわゆる箱物に合わせて、職員の人数を割り出しています。
本来、職員の働きやすさ、行政効果の向上、県民の行政サービスの向上を基本に考えるべきであり、建物、箱物に職員の出勤人数を決めるのは、本末転倒です。在宅勤務など多様な働き方を推進することには、理解しますが、それ自体が目的となってはいけないと思います。
また、厚生労働省のテレワークにおける適切な労務管理のためのガイドラインにおいて、「実際にテレワークを行うか否かは本人の意思によることとすべき」と記載があり、また、事業主、企業の労務担当者の方向けのガイドラインにおいても、「実際にテレワークを実施するに当たっては、労働者本人の納得の上で対応を図る必要があります。」としています。
先日の部局審査においても、本庁舎整備についてお伺いし、モデルオフィスの繁忙期の検証結果では、ピーク時は9割弱の出勤率となったこと等課題についてご説明いただき、「災害時の対応や職員が対面で十分なコミュニケーションを図れる執務スペースに意を用いる」といった前向きなご答弁もいただきました。
しかし、出勤率4割を8割、9割としても出勤率ありきという考え方には賛同できません。
出勤率から発想するのをやめ、本来の職員の働きやすさ、県民の行政サービスの向上、行政効果の向上から働き方を考えるべきで、それに合った庁舎整備をするべきと考えます。ご所見をお伺いします。
(2) 県教育委員会事務局庁舎のあり方について(総 務)
県教育委員会事務局の庁舎については、県庁3号館の老朽化対策工事の実施に伴い、今月下旬から順次、東灘区の旧・神戸市水道局東部センターへ移転するとのことです。
県教育委員会事務局の庁舎移転については、部局審査でも質問いたしました。それについて、「現時点では全体的な方針をお示しできていないことは十分認識している。」とのお答えがありました。
全体的な県庁舎のあり方の方針が出ていないので、何とも言えないということでしょうが、私は、県教育委員会事務局庁舎を県庁舎に戻すことをまず方針決定して、県庁舎整備計画を進めるべき、県教育委員会事務局のスペースの確保を県庁舎整備方針でまず決定すべきと考えますがご所見をお伺いします。
4 高等教育への授業料支援、負担軽減の推進について(総 務)
大学教育等高等教育での授業料等の負担は大きく、奨学金の返済も長年にわたり、若者の成長、人生に大きな負担となっています。
兵庫県では、令和5年4月、27,767人が大学(国公立・私学)へ進学しました。
うち県立大学へ進学する兵庫県民は757人と全体のわずか2.7%だけが、無償の対象となります。
さらに、令和5年3月に県内高校を卒業した41,408人のうち県立大学へ進学する兵庫県民は757人と全体のわずか1.8%です。
我が会派は、昨年度令和6年度の県立大学無償化の予算案について、公平性が保てないこと、突如打ち出され議論がつくされていないことなどから、反対の立場で討論いたしました。
しかし、すでに県立大学の無償化は今年度から始まっています。
県立大学だけの無償化の課題を議論するだけではなく、もっと県行政全体の課題として、兵庫の多くの大学生、高等教育への支援について、若者全体のこととして十分に議論をして、基本方針をうち出し、その中で考えていくべきではないでしょうか。
給付型奨学金の創設、産業労働部で取り組んでいる兵庫型奨学金返済支援事業の拡充、国の制度の活用等、大きな視点で高等教育の授業料支援、負担軽減の基本方針を示し、その関連で県立大学無償化の今後を考えていくことが必要だと考えます。ご所見をお伺いします。
5 阪神タイガース、オリックス・バファローズ優勝記念パレードを公務として担う必要性について(県民生活)
昨年は、関西を本拠地とする「阪神タイガース」と「オリックス・バファローズ」がそれぞれリーグ優勝し、優勝記念パレードを大阪府と連携して11月23日に2会場で行われました。
多くのファンを持つ人気スポーツ球団の優勝記念とはいえ、本来は両球団をはじめとする民間事業者がその能力の範囲内で実施すべき事業で、自治体はあくまで協力する側にとどまるべきではなかったのかと考えます。
仮に、スポーツ振興や観光振興といった目的があったのなら、どのような成果があったのかきちんと検証すべきだと思います。
優勝記念パレードの実行委員会兵庫県事務局規程をみますと、「パレードの実施により賑わいを創出し、都市魅力を発信するとともに、大阪・関西における2025年日本国際博覧会に向けた機運と取組を大いに盛り上げることを目的」とされています。パレードの実行委員会の名称には、わざわざ「2025年大阪・関西万博500日前!」と付け加えられています。万博の盛り上げといった政治的な目的のためにパレードを利用する思惑があったのではないでしょうか。
事務局を兵庫県が公務として担う必要があったのかお伺いします。