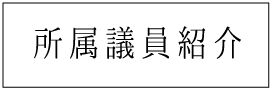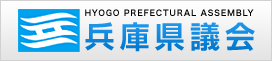概要 / 議案に対する態度と考え方 / 意見書 / 代表質問 / 一般質問 / 議案討論
第371回(令和7年6月)定例会 代表質問
質 問 日:令和7年6月6日(金)
質 問 者:小西 ひろのり 議員(ひょうご県民連合)
質問形式:分割

1 文書問題報告書とその関連する事項における知事の受け止め、態度について
(1)風通しのよい職場環境づくり、職員との信頼関係の構築について
知事がパワーハラスメント防止研修を受講することだけで大きく注目される兵庫県。研修を受けることは大事なことですが、ハラスメントのない、風通しのよい職場環境づくりの推進や日常的に職員とのコミュニケーションを図る ことは当たり前のことです。当たり前のことをするのになぜ大きなニュース として扱われなければならないのでしょうか。
知事のパワハラについてご自身へは処罰を科さない以上、職員が「齋藤知事と一緒に仕事をしたい」と思うはずがありません。
このような状態で、職員との信頼関係の構築ができるはずがありません。また、起こってしまった事例に対して相手の立場になって真摯に対応していない、定例記者会見においても同じ答弁を繰り返し、兵庫県が直面している課題について、すべて他人事としか思っていないような知事の下では県職員が安心して働くことはできません。
県の職員、県議会、県内各市町、関係団体等との信頼関係の構築は、県政運営にあたり必要不可欠です。とりわけ、最も身近にいる県職員との信頼関係の構築にあたっては、日常的なコミュニケーションや知事からの励まし、やさしい声かけがなければ信頼関係が構築できるはずもありません。再選されてからリーダーである知事が自ら、どれだけの方と積極的にコミュニケーションを図り、相手の立場に立って、気持ちのこもった対応をしましたか。私にはその行動は全く見えてきません。リーダーの資質として疑問です。
知事は、「より風通しのよい職場環境づくり」を掲げておられますが、具体的にどのような方法で構築されるおつもりですか。知事の決意をお聞かせくだ さい。
(2)兵庫県議会文書問題調査特別委員会(以下、百条委員会)、第三者委員会の調査報告書に対する知事の受け止めと態度について
3月4日に公表された百条委員会調査報告書の総括には、「全体を通して、客観性、公平性を欠いており、法令の趣旨を尊重して社会に規範を示すべき行政機関の行うべき対応としては大きな問題があったと断ぜざるを得ない」、「齋藤知事におかれては、本報告書の期するところを重く受け止め、兵庫県のリーダーとして厳正に身を処していかれることを期待する」、「文書問題に端を発する様々な疑惑によって引き起こされた兵庫県の混乱と分断は、いま、憂うべき状態にあることを真摯に受け止めなければならない」と記載されています。
同報告書では、パワーハラスメントは「おおむね事実」と記載されています。12月に内部通報に対する是正措置として発表された「組織マネジメント力向上特別研修の実施」にあたり、百条委員会からの提案を受けてアンガーマネジメント研修も組み込んでいただきましたが、研修開催は5月12日と、即時の実施とはなりませんでした。
また、文書は公益通報者保護法が定める外部公益通報に「当たる可能性が高い」こと、公益通報者保護法で禁止されている通報者探索が行われた上に、元県民局長の処分が撤回されておらず、「現在も違法状態が継続している可能性がある」とも指摘されています。
知事自らが高い中立性を確保して設けた文書問題に関する第三者委員会は、元裁判官3人を含む6人の弁護士で構成されていました。3月19日に公表された第三者委員会の報告書は、元県民局長の文書作成・配布行為を外部公益通報と認定しています。元県民局長に対して行った懲戒処分のうち、文書の「作成・配布行為」の部分を懲戒処分の対象にすることは、「公益通報者保護法に違反する」と指摘されており、処分のうち、これを理由とする部分は無効、知事らの対応を「違法・無効」と認定しました。
その結論が知事の意に沿わないのか、「見解が違う」、「県の対応は適切である」として知事は報告書の内容を受け入れない、元県民局長の処分の撤回もされない、公益通報者保護法に反していることもお構いなし、その姿勢を正そうともせず、公人としての資質を疑わざるを得ません。自らの進退をも決すべき重要な内容でもあると私は考えます。
百条委員会及び第三者委員会の調査報告書に記載されている知事のパワーハラスメント、公益通報への対応について、問題はなかったのか、兵庫県の責任者である知事として分かりやすく、丁寧にご説明ください。
(3)元県民局長の処分撤回、名誉回復に対する知事の見解と人権感覚について
3月5日の記者会見において知事は、元県民局長のパソコンの中に「不適切な文書」があったと公表した点についても第三者委員会報告書には「人を傷つける発言は慎むべき」と記載されています。報告書の内容を謙虚に受け入れるどころか、記者会見の場で私には到底理解できない人権侵害にもあたる発言をされました。知事自身がこれまでの対応や姿勢を改め、県民が納得する説明と元県民局長の処分撤回、名誉回復を即時に行い、ご本人・ご遺族に対して直接謝罪を行うべきです。
加えて、知事のパワハラ疑惑も、調査した16件中、10件が認定されたほか、令和6年3月27日の記者会見における「嘘八百」、「公務員失格」という知事の発言もパワハラに該当するとされています。パワハラに対する自らの処分への言及は避けたままです。職員のパワハラ案件は懲戒処分の対象となっているにも関わらず、自身の処罰はないのでしょうか。
元県民局長の処分を撤回しない理由、さらには、文書問題への対応において、告発者捜し、告発者潰しを行った知事自身の処罰を未だに行わない理由は何ですか。知事の説明を求めます。
(4)公益通報者保護法「違反」状態である兵庫県の現状と消費者庁からの技術的助言について
公益通報者保護法の取扱いをめぐり国会では、「外部通報である3号通報に対しても体制整備義務があり法的拘束力がある」、「法定指針には法的拘束力がある」と消費者庁から発言がありました。
また、大臣からは、「県議会と第三者委員会等で長時間にわたり審議されてきているものとして、その解釈や結論には一定の納得をしなければならない」、「各任命権者は、為政者としての良識のもと、抑制的に権限を行使すべきであり、職員が安んじて職務に精励できるように率先して環境整備に取り組む 責務を有している」と発言されています。
消費者庁は5月22日付で、全国の自治体等に対し、地方自治法に基づく「技術的助言」として、「行政機関における公益通報者保護法に係る対応の徹底について」を発出し、「3号通報をした者も含めて不利益な取扱いの防止に関する措置をとること」を下線付きで強調もされています。知事はこの通知を受け、今後、どのように行動されるのかその真意が伝わってきません。
しつこいようですが、大事なことですので改めて述べます。
県が設置した第三者委員会の調査報告書において、「本件文書問題に対する県当局の対応は、公益通報者保護の見地から見て違法、不当なもの」、「通報者を探索した知事らの対応は公益通報者保護法違反である」とされています。また、消費者庁からも下線付きで同様の技術的助言があった後においても知事は、「対応は適切であった」と持論を主張し続けるのはなぜですか。その理由を分かりやすく説明してください。兵庫県のリーダーである齋藤知事の文書問題への対応は、公益通報者保護法違反だったのですか、違法ではなかったのですか。どちらだとお考えですか。
(5)県保有情報漏えいの指摘に関する第三者調査(法務文書課)結果の取扱いについて
元県民局長の公用パソコンに記録されていたとされる私的情報が外部に流出し、SNS等で拡散された問題で、5月13日に県の第三者委員会は「インターネット上に流出した情報は県が保有していた情報と同一のものと認められる」、「それらの情報を県から外部に持ち出すことは公益通報者保護法上の公益通報には該当しない」、とする調査結果を公表しました。
また、「元データの保存場所を知るのが人事課職員の一部に限られ、ネットワーク外部から侵入された形跡もないため、情報を外部に漏洩したのは県職員の可能性が極めて高い」と指摘されています。
個人のプライバシーに関する事項は、公共の討論に必要なものではなく、公務員が守秘義務として守らなければならない事項です。週刊文春電子版に 掲載された「片山元副知事による元西播磨県民局長事情聴取の音声データ」、 「3月25日の調査実施手順書」等は、県の調査手続きの情報のため、守秘義務の対象の「秘密」にはなりません。そもそも週刊文春の記事を調査対象としたこと自体が不適切です。
一方で、YouTubeやXで発信された調査4項目は、すべて「私的情報」、プライバシーに関する事項となり、秘密にしなければなりません。このように個人であるYouTuberと報道機関では、漏えいした情報の性質が異なっており、「行政の動きの検証」まで刑事告発をしたことは大きな間違いです。
兵庫県警は6月2日に告発状を受理しました。「行政の動きの検証」にかかる刑事告発を取り下げなかったのはなぜですか。その理由をお聞かせください。
(6)秘密漏えい疑いに関する第三者調査(人事課)結果と刑事告発について
地方公務員法第34条では「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする」とあります。
人事課が所管する県の第三者委員会は、5月27日、「元県民局長の公用パソコンにあった私的情報を前総務部長が県議会議員に漏洩した」と認定し、「知事及び副知事の指示のもとに行われた可能性が高い」とする最終調査報告書を公表しました。
この調査は1月27日で終了していましたが、井ノ本前総務部長がこれまでの説明を覆し、県議に私的情報を伝えたのは「知事及び副知事の指示」であった旨の弁明書を県に提出したことを受けて、追加調査が行われていました。井ノ本前総務部長は、百条委員会の証人尋問で「証言が手がかりとなり、守秘義務違反の嫌疑を受ける可能性が生じるので、証言は控えたい」、「情報を持ち出したかどうか私は証言しておりません」等、理解に苦しむ証言もされていました。
また、「他の幹部職員と元副知事の供述が前総務部長の主張とほぼ一致。整合しない知事の供述は採用が困難。知事と副知事の指示により、根回しの趣旨で情報漏洩をした可能性が高い」という第三者委員会の報告が出ています。
さらに、百条委員会の聞き取りに対し、県議会議員は「前総務部長から文書を作成した元県民局長の私的な情報を見せられた」と証言しています。
井ノ本前総務部長には停職3ヵ月の懲戒処分が発表されました。しかし、「漏えい行為や総務部長という職責を考えると、停職6ヵ月が相当だったが、知事らの指示を受けていた可能性が高いとされたことで処分を軽くすることになった」との報道もあります。知事はこれまで「指示はしていない」としていますが、自らが指示した可能性を理由に処分が軽くなったと把握した上で、懲戒処分を決裁していたのでしょうか。さらに、知事はこれまで何度も「最後は司法での判断を」とおっしゃっていましたが、この件で刑事告発をしないのはなぜか、理解できません。
また、片山元副知事は、SNS上で「秘密に属することの話をすることは慣例。総務部長の行為は正当な業務」、「総務部長は細心の注意を払っておりますから、資料の写しは絶対2人の議員に渡しません」等と発言しています。なぜ、ここまでの詳細について片山元副知事がSNS上で発言されるのか、これも理解 できません。
行政の手続きや政策等に関して、議会に対して事前に説明すること、意見を聞くことは正当な業務です。しかし、報告書にも「保護されるべき『秘密』に該当する」、「人事課において非公開情報として決定された」とあり、人事に関する秘密情報でもある一個人のプライベートな情報について見せて回ることは正当な業務にあたりません。そもそも井ノ本前総務部長が持ち出してはいけない個人のプライバシー情報を外部に持ち出すこと、さらに他人に見せて回ることがまずもって大きな問題です。
元県民局長の私的な情報を持ち出したこと等の違法行為は、「知事及び副知事の指示のもとに行われた可能性が高い」とされていますが、知事ひとりの言い分だけが食い違っています。
これまでも齋藤知事と片山元副知事や職員との証言の食い違いはたくさん あります。百条委員会の証人尋問における証言「風向きを変えたい」発言があったかどうか、PR会社への報酬支払問題に対する言い分の違い、文書問題に関して県幹部から知事へ第三者機関での調査を進言されたかどうか、公益通報者保護法の解釈をめぐる国の見解との違い等、ほかにも県民に対して事実経過を丁寧に説明できていないことが多数あります。
さらに、県の業務に関して、職員から事前に説明があったはずの内容について「聞いていない」という趣旨の発言があったことの証言も多数あります。職員は知事に対して丁寧な説明をしたにも関わらず、不誠実な態度をとられる。
第三者委員会の報告で明らかとなった井ノ本前総務部長の守秘義務違反について、6月3日に4会派で申し入れを行ったところですが、刑事告発についての検討状況をお伺いします。
2 県庁舎の再整備における進捗状況について
県庁舎、元町再整備については、これまでもあらゆる機会でその進捗状況等について本会議や常任委員会等での質問がありました。
教育委員会は神戸市東灘区住吉に移転し、半年が経過しました。場所が離れてもなるべく対面で相手の顔を見ながら話がしたいという考え方のもと、職員の皆さんは丁寧な取組を進めています。
知事は先の2月定例会において、「機能的でコンパクトな新庁舎整備の方針を進めていく」と述べられていますが、「コンパクト」という言葉が意図する具体的な内容が全く見えません。県の考え方として、「必要な面積の最適化・合理化による コスト削減」、「県民会館との合築(がっちく)による有利な財源を活用する」等、示されていますが、具体的な基本構想が未だ示されておらず、日々県庁舎で働く 職員や県民の不安は増すばかりです。
神戸市やJR西日本等と連携し、三宮・元町エリアの再整備を一体的に進めることは重要な要素であり、兵庫県と神戸市の連携のもとでの元町エリア全体の活性化の具体策も含めた基本構想を早急に策定することが求められています。計画が先延ばしになればなるほど、現在の物価高、資材価格の高騰、人財不足の影響を受け、総予算に大きな影響が出ないか大きな懸念を抱いています。
兵庫県の新庁舎完成までの必要経費について、5月16日の総務常任委員会において我が会派の中田議員から民間オフィスの賃貸料等について質問をしましたところ、テナント料等を含めると年間6億円から7億円、つまり毎月5,000万円を超える予算が必要と答弁がありました。テナント料だけでも巨額の予算を確保しなければならず、加えて新庁舎建設に係る資材高騰や物価高の影響も考えられる状況で、工期が一年延びると多額の予算が必要となる現状は一刻も早く回避し、スピード感をもった対応が求められます。
阪神・淡路大震災を経験した兵庫県だからこそ、震災の教訓を生かし、県民が安心できる防災機能を備えた県庁舎の再整備が必要であると考えます。県民サービスの低下を招かないよう、職員が働きやすい執務環境を整え、職員のモチベー ションの向上と業務の効率化が図られるとともに、災害発生時の防災拠点となりうる新庁舎の整備を求めますが、知事のご所見をお伺いします。
3 有機フッ素化合物(PFAS)対策の推進について
2023 年12 月1日、世界保健機関の専門組織である国際がん研究機関は、有機フッ素化合物(以下、PFAS)のうち、PFOAをヒトに対して発がん性があるもの、PFOSをヒトに対して発がん性がある可能性があるものとしました。PFASの一部は半導体の生産等に使われ、発がんの可能性がある物質として、健康への影響が指摘されています。
市民団体である「明石川流域のPFAS汚染を考える会」(当時)は2024年9月3日、周辺住民33人に実施した血液検査の結果を公表しました。検査対象の約半数の16人がアメリカの血中濃度指針値を超えており、「健康被害が懸念される」と検査結果をまとめています。
この検査は、小泉昭夫京都大学名誉教授も関わられたPFAS血液検査により、検査対象者9人のうち、3人がアメリカ基準を超え、6人がドイツ基準を超えた2023年8月の結果を再現していると言えます。2回の調査がともにPFAS汚染を示していることから、たまたま見つかったのではなく、地域住民に汚染が広がっていると考えられます。特にPFOAに関しては、極めて数値が高く、「摂津市や東淀川区の汚染レベルに匹敵あるいは超えるレベルであった」と報告されています。
さらには、少なくとも次に述べる3つの観点について、県民の生活に直接的な影響を及ぼすことが懸念されています。
一つに、農業用水として利用している地域もあり、地元の農産物とその生産基盤となる土壌は大丈夫なのか。二つに、川の河口からPFASに汚染された水が海に流れ出すことで、水産物は大丈夫なのか。三つに、環境汚染による健康被害や風評被害。
明石川での課題に関しては、市民団体から汚染源の撤去や健康調査を求める要望書を明石市や神戸市に対して提出しましたが、納得のいく回答を得ることができていません。兵庫県に対しても2025年2月13日に「PFASについて対策強化を求める要望書」を提出しています。
健康にどう影響するのかを調べるには、血液検査が適切な手段だと考えます。ところが、先ほど述べました血液検査においても、1万円以上の自己負担をされており、責任ある行政の立場としての検査を行うことも必要であると考えます。
県議会では、令和6年2月第366回定例会において「PFAS対策の推進を求める 意見書」を全会一致で採択しております。県内では神戸市、明石市のほかにも尼崎市、西宮市、宝塚市や西脇市、東京都では多摩地区、岡山県では吉備中央町を始め、全国各地でこの問題への対応が迫られています。
兵庫県は、昨年7月30日にPFOA、PFOSについての2023年度調査結果として、神戸市、尼崎市、西宮市の河川・地下水の複数地点で国の暫定指針値を超過したことを発表しました。
また、兵庫県はこれまでにPFOAを使用していた工場に対して代替物資への転換等の指導を行ってきた他、河川の監視地点の拡大、県環境研究センターとの連携や情報発信をはじめ、様々な対策を講じていますが、県民の不安が解消されているわけではありません。
日本ではPFASの血中濃度に関する基準が定められていません。国への要請も含めて、河川におけるPFASの監視を高めること、汚染源を断つこと、PFAS汚染が懸念される地域で健康調査の一環としてPFAS血液検査を行うこと等、兵庫県として今後の更なる対策を求めるものですが、当局のご所見をお伺いいたします。
4 教職員の未配置問題の解消に向けた取組について
全国の公立学校で教職員の未配置問題が解決せず、ここ数年、「学級担任がいないクラスがある」という信じがたい実態が年度はじめから起こっています。 子どもたちや保護者からは「いつ担任の先生が決まるんやろ」等の不安な声、深刻な声が挙がっています。未配置は学期を追うごとに増加の一途をたどっており、兵庫県においても課題となっている。
学校現場では、教頭が学級担任を掛け持ちしたり、学級担任がいないクラスの授業を教職員が互いに交代で進めたりする等、一人が二人分、三人分の業務を担い、対応を迫られています。また、支援を必要とする子どもたちが年々増え、保護者や子どもたちの価値観も多様化しており、その対応を担う教職員の役割は以前と比べると大きく増えています。
産休・育休からの復帰を考える教職員は、「このまま仕事を続けることができるのか」という不安に陥り、復帰を迷う事例も増えています。残念ながら、現在の学校は魅力ある職場とはなっておらず、子どもたちにとってもよい状況となっていません。
このような環境下でも、「子どもたちを安心させ、落ち着いた環境で生活できるようにしたい」という使命感から日々懸命に取組を進めている教職員もおり、中には70歳を超えても学校現場で働く方もいらっしゃいます。そのような教職員が疲弊してしまう前に抜本的な対策が必要です。
兵庫県教育委員会が発表した令和6年5月1日時点の教員不足は、205人となっています。これまでも教員採用試験において、臨時的任用教職員の加点措置、魅力ある職業や職場であることをPRする動画の作成等の人財確保を目指した取組を進められています。
また、今年度実施される採用試験では、常勤の臨時講師を対象とした第1次選考試験一部免除の実施や「東京」試験場の新設等、受験しやすい環境づくりに尽力いただいていることも十分理解しています。しかし、現場の根本的な課題解決には至っていません。
文部科学省は、『「教師不足」に関する実態調査』の結果公表を行って以降、特別免許状の積極的な活用や臨時免許状の適切な授与等について依頼しています。
しかし、実際に教職員を採用するのは兵庫県ですし、人財を確保するのは各市町教育委員会との連携なしでは未配置問題の解決には至りません。県全体でのこれまでの取組成果や課題の総括、今後の取組方針や方向性について当局の見解をお伺いします。
〇動画URL(第371回6月定例会6月6日 質疑・質問(代表)):https://smart.discussvision.net/smart/tenant/pref_hyogo/WebView/rd/schedule.html?year=2025&council_id=115&schedule_id=606
第371回(令和7年6月)定例会 一般質問
質 問 日:令和7年6月9日(月)
質 問 者:中田 英一 議員(ひょうご県民連合)
質問形式:一括

1 知事および片山元副知事の守秘義務違反(教唆)について
第三者委員会の調査報告によれば、元総務部長に対して知事および元副知事から私的文書を県議に漏洩するよう指示があった可能性が高いとされているが、これは、知事や元副知事が情報漏洩を指示した、すなわち守秘義務違反教唆の可能性が高いというものであり、職員に告発義務を課した刑事訴訟法第239条第2項の「犯罪があると思料する」に相当の理由がある状況と言える。
しかし、元総務部長の処分についての県当局の会見でも「第三者委員会の調査結果が前提」であり、元総務部長への処分を軽減させる方向での理由にも「知事・副知事からの指示があったと前総務部長が信じている状況にあったこと 」をあげながら、本人達への聞き取りも行わないで、知事については「本人が否定していて、裏付ける証拠もない」ことを理由として、元総務部長の漏洩事案に関して、知事および元副知事の指示(教唆)の部分についてはこれ以上対応しないこととしているのは全く筋が通らない。
(元総務部長を)そそのかして、あるいは命令によって犯行に手を染めさせた、まさに「黒幕」として疑わしい知事及び片山元副知事を追及せず、トカゲがしっぽを切るように、元総務部長に責任を擦り付けて幕引きをはかるような対応は、独裁的な体制、コンプライアンス機能が働いていないとしか映らず、県当局は県民の信頼回復を狙うというが、さらなる不信を招いているのではないか。
警察のような強制力をもった捜査権限がないにしても、教唆の疑いが強いという事実に立てば、可能な限りの調査を尽くすのが県の正常な役割であり、それが行使できない場合や、客観的に納得できる合理的な調査結果が得られず、真相が解明されない状況では、それこそ知事が口にしていた「司法判断を仰ぐ」ためにも、県として知事および片山元副知事を刑事告発する以外にないのではないかと考えるが、当局の所見を伺う。
2 国の法令解釈等と知事判断とが異なる場合の対応について
法は、職員に法治主義原則のもと法令に則った職務を義務付けると同時に、知事の補助を義務付けており、知事が法令に反することを想定していない。
ところが、本県においては、これまでも指摘されてきたように、知事の発言を発端にして法令や判例などと異なる解釈、行為が取られてきている。
具体的には、元西播磨県民局長の作成した文書について、県が弁護士会に依頼して設置した第三者委員会が公益通報者保護法違反に該当すると結論付けた件で、知事は、外部通報には通報者の探索を含めた体制整備義務が含まれないという見解があるとして、元県民局長へ処分は適法である旨を示唆しているが、法令を所管する消費者庁も外部通報が含まれるとの解釈を示しており、客観的に見れば、法曹界の代表および国の法解釈と知事の解釈が異なっている。
また、週刊文春に掲載されていた「元副知事が元県民局長を聴取した際の音声データ」を外部に漏洩した事案についても、(総務常任委員会で聞いた際にも)「秘密」の定義こそ判例通説の実質説を採用しているように見せて、「実質的に保護に値する」内容や判断基準の説明はないまま、私的情報の漏洩と同様に扱い刑事告発した行為は、判例通説に照らして大きな問題があり、国民の知る権利を脅かす恐れがあると考える。
知事は、たしかに県民の民意で選ばれているが、全国民の代表者である国会で制定された法律を曲げることまで許されるわけではないし、法律の世界に身をおき修練と経験を積み上げられた法曹界の推薦する専門家よりも優れた法解釈ができる理屈はなく、これらを無視できる権限も道理もどこにもない。
「さまざまな解釈がある。最終的には司法が判断する。」と言われるが、知事が今の判断を続けたままこの道を進めば、職員は法治主義原則と知事の補助機関としての義務に板挟みの状況で、1問目で指摘した身内への甘い処分、公益通報者潰し、報道の自由や国民の知る権利を軽視するという、法治主義の原則をも脅かし続ける危機的な状況を招くのではないか。
このような状況にあっても、あくまで知事は自身の判断に職員は従うべきと考えるのか。当初掲げられていたボトムアップの精神に今一度立ち返り、職員の助言に耳を傾け、今からでも、まずは、公益通報者保護法の解釈や週刊文春に掲載されていた情報の漏えいにかかる刑事告発について方向転換することは考えないか。知事の所見を伺う。
3 営利目的の兼業・副業の解禁について
石破首相の施策方針演説(2025年1月24日)のなかで「地方公務員の兼業と副業の弾力化」が盛り込まれ、人事院報告(令和6年6月19日、令和5年度 人事院年次報告書)でも、(国家)公務員の兼業について「職員の自律的なキャリア形成」や「組織のパフォーマンス向上」につながるような兼業の在り方について検討を進めるよう示されている。
地方公務員法は第38条1項で任命権者(知事)の許可を要件として職員の営利目的での兼業を認めており、大阪府が2024年に営利目的の副業解禁に踏み切るなど、民間企業はもちろん地方自治体でも兼業・副業解禁の動きが進んでいる。
しかし、兵庫県では、会計年度任用職員は、届出を出せば原則として営利目的の兼業も認めているものの、正規職員は、原則として営利目的の兼業・副業は認められていない。
安定的に長期間働いてもらい、経験を積み上げてもらうことももちろん重要であるが、個別の事情で一時的にお金が必要になり空いた時間でさらなる稼ぎを得たいと思う職員もいるだろうし、外部の刺激を受けて成長を目指したい職員もいると考えられる。
また、現状で自主退職される職員の中には起業が理由である場合もあると聞く。起業する前に、兼業によって民間企業のノウハウや技術を学べるようになれば、起業後のスムーズな活躍が期待でき、こうした多様なキャリア形成を目指せるということは、職場の大きな魅力の一つになる。
優秀な職員が県庁から抜けることは残念な側面もあるが、公共の大切さや役割を熟知した起業家が地域に飛び出して活躍することは、県の発展にも寄与すると考えられることから、兼業を解禁することにより、県職員としての経験が、そうした人材を育てることにも繋がる。
もっとも、残業時間数が多ければ、希望があっても兼業・副業の機会は奪われるし、秘密の漏洩や職員の信用の低下を招かないような配慮が必要なことは言うまでもないが、兼業解禁は、兵庫県として内定辞退者数や自主退職者数の増加に歯止めをかけ、働き方改革の進んだ職場としてPRできる要素になるし、外部交流で職員が得られる知識や経験は県行政にとっても大きな財産になると考えることから、営利目的での兼業・副業の解禁についての今後の取組や当局の所見を伺う。
4 オールドニュータウン対策の新展開について
高度経済成長期に開発されたニュータウンにおいて、住民の高齢化、施設の老朽化などによる地域活力の低下、衰退が懸念されるいわゆるオールドニュータウン対策は全国的にも各地で取組が進められている。
例えば、大阪府河内長野市の南花台では、民間事業者から建物の提供をうけて交流拠点を整備したり、大学との連携によるソフト事業、国の近未来技術等社会実装事業を活用した自動運転の実装モデルに着手したり、様々な手法を用いて取り組みを進めている。
県内でも、三田市では河内長野市と同じく自動運転バスの実証実験や関西学院大学と連携したまちづくりを進めたり、独自で住み替え支援の補助制度を設けたりするなどの取組みを行っている。
県内のいくつかの地域で進むオールドニュータウン対策について、その目玉として「オールドニュータウン商業施設等空き区画活用支援事業」を令和4年度から明舞団地での成功事例として他の地域にも拡張してきた。
事務事業評価では、40歳未満人口の比率が29.4%に達したとして、目標達成とあるが、当該事業への申請業種は特定されておらず、40歳未満人口の増加との因果関係に疑問が残る。実際に現場を見たが、新規入居店舗の多くは徒歩圏内の高齢化の進む既存住民をターゲットにした商業形態であるように感じた。
この事業自体を否定するものではないが、以前から指摘しているように住み替えを進め地域内での世代構成の平準化を進めなければ、刻一刻と迫るオールドニュータウンの衰退は防ぐことができないと考える。
明舞団地は県内オールドニュータウンのなかでも、神戸都心へのアクセスも良く、明石市域も含めて利便性の高い立地条件で、若者世代・子育て世帯にも人気が高く周辺にも多くの戸建住戸が新築されてきた。また、近隣に高齢者施設や住戸のストックも多く、いわば自然に世代構成の平準化が進む条件が揃いやすい。
一方で、郊外のオールドニュータウンでは、人口減少かつ各地域での人口誘致が活発化するなかで、バブル期はもちろんだが、今の明舞団地と比べても、若者世代・子育て世帯の新規入居の需要は低く、より政策的な誘導が求められることから、明舞団地の本事業が成功モデルだったとしても、それを拡大するだけでは不十分であると考えられる。
私の地元の三田市フラワータウンでも同様の課題を抱えており、世代構成の平準化等に向けたさらなる展開が必要と考えるが、オールドニュータウン対策の今後の展開について当局の所見を伺う。
5 三田市民病院の再編統合計画における補助金について
三田市民病院と済生会兵庫県病院の再編統合計画が発表された。新市長が白紙撤回を掲げたことなどから計画の進捗は2年程度停滞し、その間に物価高・建設費の高騰によって当初の約254億円という見積りから先日発表された基本計画では約521億円と倍増している中で、計画策定時点での現行制度における推定ではあるものの、県からの補助金は約19億円と示されている。
三田市民病院の再編統合に関する県としての支援を令和4年に質問した際、「国による助言や支援が受けられる重点支援区域への申請」、「医療介護推進基金を活用した整備に対する支援」を行っていきたいとの答弁を頂き、今回の再編統合計画はこれを踏まえて進められてきたものであるが、医療介護推進基金の財源である国の「地域医療介護総合確保基金」は、今年度終了予定であったものが1年延長され、現時点では令和8年度で終了予定となっている。
もし国の基金が終了した場合、三田市の事例では1円の補助金も受けられないこととなり、他地域でも、再編統合を計画されている病院の施設整備に補助されないのであれば、あまりに大きな影響であり、大きな混乱も予想されることから、地域医療介護総合確保基金の再延長についての見通しと、県としての支援について当局の所見を伺う。
6 人と自然の博物館のさらなる活用について
兵庫県は歴史博物館や考古博物館、研究機関を兼ね備えた人と自然の博物館といった、県立博物館を運営しており、これらの施設は大学と連携した研究機関であったり、専門性の高い研究員や学芸員および展示収蔵物を保有していたりと、教育人材・教材の資源の宝庫でもある。
こうした資源のさらなる活用に向けて、近隣の小中学校との連携をさらに深め、もっと子ども達に身近な学びの場所となるような取組みはできないか。
例えば、三田市にある人と自然の博物館では、広く来館者への対応やセミナーを始めとしたイベントの企画運営に加えて、アウトリーチ活動も積極的に実施されているが、維持運営費が下げ止まりしている現状では資金的にも人員的にも広い県内を均等に回ることには限界がある。
本県は「兵庫五国」として地域特性や多様性を尊重して積極的に打ち出す姿勢をとっており、「地域に根差した博物館」を強く打ち出してもいいように思われる。
現状もひとはくに社会見学などで来館する学校をみると地元三田市及び隣接する市町の学校が多いが、基本的にはいずれも単発での訪問となっており、子どもたちが自発的に何度も通うような「身近に学びを得られる場所」として深く認識されるまでには至っていないように感じる。
三田市では、ひとはくに協力を求め、自由研究作品の展示や表彰、「サイエンス・トライやる事業」の「スペシャリストによる特別授業」として小学校に研究員が出向いての特別授業などを実施していると伺っている。
例えば、小中学校の地学の単元で、授業としてひとはく研究員による体系立った講義を受講することで、研究員が単なる「外部の人」ではなく、「授業をしてくれる先生」となって、ぐっと身近になれば、普段開催されているひとはくのセミナーへの受講や、自由研究や日々の学習の中でも、足を運び質問や相談をするようなファンになってくれるし、兵庫県における教育の魅力や評価を高めることにもつながると考える。
そこで、このように県下の市町や学校からのさらに踏み込んだ連携や協力の要請等があった場合、県としてこうした要請の受け入れについてどのような対応が考えられるか。人と自然の博物館のさらなる活用について当局の所見を伺う。
7 県立高等特別支援学校の老朽化対策について
三田市にある県立高等特別支援学校は、昭和22年に国立兵庫療養所内に開設された養護施設を起源とする上野ケ原特別支援学校の一部を改修して平成8年に開校された。職業自立を目指す知的障害者を対象とした、職業科の特別支援学校のさきがけとして、寄宿舎も備え、これまで県下各地から多くの生徒を社会に送り出してきた。
本年、開校30年目を迎え、令和4年に改訂された兵庫県公共施設等総合管理計画にもある大規模修繕の目安時期となっているだけでなく、開校時も純粋な新築ではなかったことから、新築で30年経過した施設と比べてもさらに老朽化が深刻になっており、早期にかつしっかりとした改修計画の策定が望まれている。
また、学校の特性上、トイレなど水回りの改修による衛生面、安全性の向上についてより高い配慮が必要であると考えることから、今後の整備方針について当局の所見を伺う。
8 県立学校における離婚後の親(非親権者)への対応について
昨年5月に民法が改正され、父母の離婚後の子の養育に関するルールが見直された。
これによると、「親権や婚姻関係の有無にかかわらずこどもの心身の健全な発達を図るために、父母がこどもを養育する責務を負うこと」等が明記された。
これまでの単独親権制度下においては、「親権者=こどもの養育者=保護者」という扱いがなされ、例えば親権を認められなかった親が子どもの学校行事に参加が認められないというような状況もあったと聞いている。
しかし、不仲になって別居しようが離婚しようが子どもにとって親であることに変わりはなく、子どもが親の愛情を受けたり、親との関わりのなかで多くの成長を得られたりすることなどについても何ら変わるものではない。
当然、虐待事案や一方の親との交流が子どもにとってよくない影響を与える場合には、交流させるべきでないが、そうでない限り、親や周りの都合でこうした子どもの権利が妨げられることがあるとすれば不幸なことである。
平成22年7月5日の大阪高裁の判決でも、「子と非監護親との面会交流は、子が非監護親から愛されていることを知る機会であり、子の健全な成長にとって重要な意義があるため、面会交流が制限されるのは、面会交流することが子の福祉を害すると認められるような例外的な場合に限られる」とし、「学校行事については、親として参加するのは自然なことであり、参加に際して未成年者の心情への配慮を要することは当然のこととして、参加自体を制限すべき特段の事情があればともかく、そうでなければ参加を制限されるものではな」いとしている。
こうした背景のなかで、市の例にはなりますが、大東市教育委員会では、昨年末に親権者か非親権者に関わらず別居親への対応として「別居親の行事参加について」というフローチャートを作成して学校園の対応指針を示している。
それによれば、
(1)同居親が別居親の行事参加を認めないよう学校へ依頼した場合と
(2)別居親が行事参加したい旨を学校へ依頼した場合に、
(3)学校は相談内容、接近禁止命令等の有無を市教委に報告し、
(4)市教委は学校と連携し、対応可能な案を指導・助言し、
(5)学校は法的根拠に基づいて、対応可能な案を親に説明するというもので、
(6)説明により理解が得られない場合にも工夫して別居親が行事参加できるようにするとしている。
大切なのは「子どもの利益のため」という視点に立ったわれわれ大人の対応であると考える。
現在、県立学校では、個別の対応は学校が個々の状況を踏まえて対応しているということであるが、先に示した法改正や裁判例の趣旨を踏まえた対応が徹底されなければ、子どもの利益が損なわれる事態が起きかねないのではないかと危惧する。
そこで、「子どもの利益のため」という視点に立った、離婚後の親(非親権者)への対応指針の必要性について当局の所見を伺う。
〇動画URL(第371回6月定例会6月9日 質疑・質問(一般)):https://smart.discussvision.net/smart/tenant/pref_hyogo/WebView/rd/schedule.html?year=2025&council_id=115&schedule_id=609